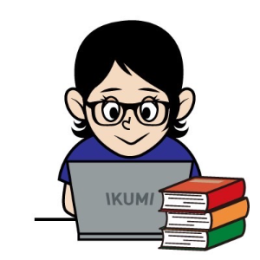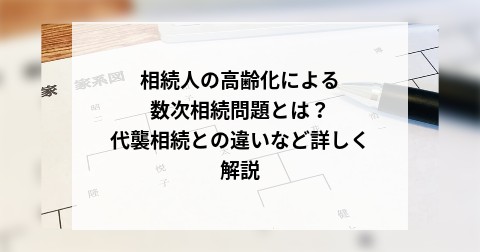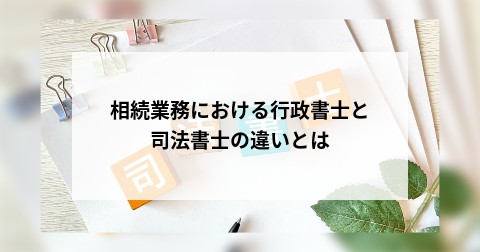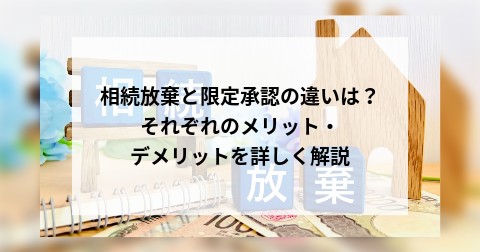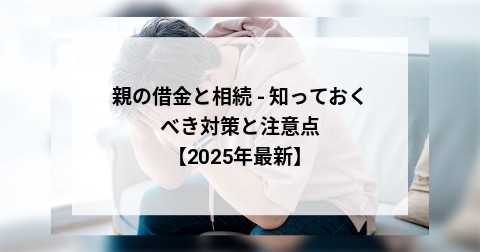相続人が認知症|相続手続きの進め方や注意点をわかりやすく解説
相続手続きは遺産分割や相続税申告など、さまざまな手続を定められた期限内に進めていく必要があり、相続人にとって重い負担となる作業です。さらに、相続人の中に認知症を患っている方がいる場合、遺産分割は一筋縄ではいかない問題に直面します。
高齢社会の日本では認知症を患う方も増加しており、相続時に思わぬトラブルに発展するケースも少なくありません。そこで、本記事では相続人が認知症だった場合の相続手続きの進め方について、注意点も交えながら詳しく解説します。
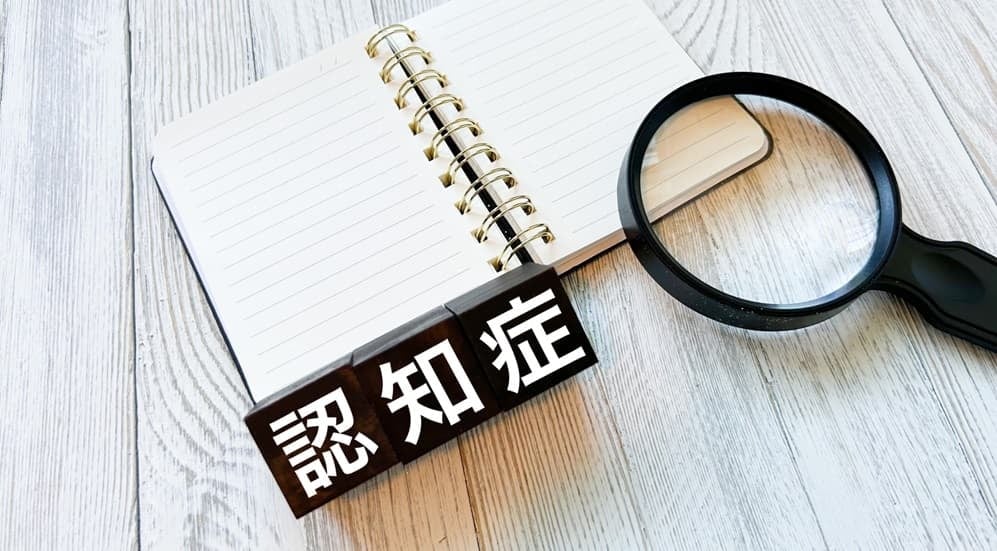
相続人に認知症の方がいる場合は遺産分割を進められる?
相続が開始されると、被相続人が所有していた相続財産を、相続人に分割することになります。この手続きは「遺産分割」と呼ばれており、複数人の相続人がいる場合は「遺産分割協議」を行って、誰がいくら財産を取得するのか決めます。
では、認知症を患っている方が相続人だった場合、遺産分割は進められるのでしょうか?
遺産分割協議は原則そのままでは行えない
相続人に認知症の方がいる場合、原則としてそのままでは遺産分割協議を進めることはできません。
遺産分割協議は相続人全員が参加し、互いの意思に基づいて遺産の分け方に合意する手続きです。法的な効力を持つ合意を形成するためには、相続人全員が自身の行為の意味を理解し、判断できる能力(判断能力)を持っている必要があります。
認知症の進行度合いにもよっては医師の判断の上で協議を進めることも可能です。しかし、判断能力が不十分と判断されるにもかかわらず無理に遺産分割協議を進めても、無効となるリスクがあります。
認知症の方がその場に同席し、形式的に署名・捺印をしたとしても、後からその合意が無効であると主張され、相続争いに発展する可能性が非常に高いため注意が必要です。
相続放棄や限定承認もできない
注意すべきは遺産分割協議だけではありません。相続人が認知症の場合、相続放棄や限定承認といった重要な選択も、原則として本人の意思では行えません。
①相続放棄
被相続人に高額の債務がある、被相続人と生前から疎遠だった場合などにおいて、相続権を一切放棄する手続きです。
②限定承認
相続人が取得する被相続人のプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も引き継ぐ手続きです。複雑な手続きを要するため利用されるケースは少なくなっています。
これらの手続きも、遺産分割協議と同じように、相続放棄や限定承認を選択することのメリット・デメリットを理解し、ご自身の意志で申立てを判断できる判断能力が必要です。
認知症で判断能力が不十分な状態では、相続放棄などの重要な法的手続きも進めることができません。
相続放棄と限定承認の違いは以下の記事を参考にしてください。
相続放棄と限定承認の違いは?それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説
すでに成年後見人が付いている場合
相続が発生する前(被相続人が存命)の時から、すでに認知症の方に対して成年後見人が選任されている場合は、成年後見人が認知症の方の法定代理人として、遺産分割協議に参加することができます。
遺言書がある場合
被相続人が法的に有効な遺言書を残していた場合、遺産分割協議はしなくてよくなります。
遺言書で遺産の分け方が明確に指定されていれば、原則としてその内容に従って相続手続きを進めるためです。ただし、以下2つの注意点(認知症が重い場合)もあります。
■相続登記はできない
遺言書で認知症を相続人が不動産を取得することになっても、相続時の名義変更手続きである「相続登記」を進めることができません。相続登記は2024年4月1日より義務化もされている重要な手続きですが、判断能力が低下している方が進められる手続きではないためです。相続登記が必要なら、成年後見人が必要となります。
■相続税申告もできない
相続税の申告が必要な場合でも、認知症の相続人については無断で申告することはできません。
認知症の方とともに遺産分割を進める方法
相続人に認知症の方がいる場合、どのように遺産分割を進めれば良いのでしょうか。認知症が進行し、医師の診断でも重い症状であると判断された場合には、成年後見制度を利用することが大切です。
成年後見制度とは認知症などにより判断能力が不十分な方を法的に支援するための制度です。この制度を利用することで、選任された成年後見人が、認知症の方に代わって遺産分割協議に参加できます。
成年後見制度の概要
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
①法定後見制度
すでに本人の判断能力が低下している場合に、家庭裁判所に申し立てて利用する制度です。申立人になれる人は限定されており、本人・配偶者・4親等内の親族・成年後見人等・任意後見人・成年後見監督人等・市区町村長・検察官です。
本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
家庭裁判所が親族や弁護士など、本人に適していると考えられる人を成年後見人として選任します。必要に応じて成年後見監督人や、特別代理人が求められることもあります。
選任された成年後見人は、本人の財産管理や介護や医療に関する契約などについて、法律行為を代理したり、取消したりする権限を持ちます。遺産分割協議への参加もこの権限に含まれます。
②任意後見制度
本人がまだ判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人が選んだ任意後見人(信頼できる人)と、公正証書で契約しておく制度です。
遺産分割協議を進めるために利用されているのは、すでに認知症が進行しているケースが多いため法定後見制度です。
相続時に成年後見制度を利用する際の注意点
相続時に必要に迫られ、認知症の相続人に成年後見人を申し立てる場合は、あらかじめ知っておきたい注意点があります。この章で簡潔に解説しますので、申立ての前に必ずご一読ください。
成年後見人の選任には時間を要する
成年後見制度の利用開始については、家庭裁判所に申し立ててから、実際に成年後見人が選任されるまでに数ヶ月程度の期間を要するのが一般的です。申立ての準備や家庭裁判所での調査、後見人候補者との面談などに時間がかかるため、相続税の申告期限に間に合わない場合は、相続税の申告が未分割申告となるおそれがあります。
申立てや成年後見人には費用が発生する
成年後見人の申立てには医師の診断書や鑑定費用が必要となるケースもあり、費用がかかります。また、成年後見人が専門職(弁護士、司法書士など)になった場合、後見人への報酬が発生します。この報酬は、本人の財産から支払われることになります。詳しい費用については以下の東京家庭裁判所サイトを参考にしてください。
参考URL 東京家庭裁判所 申立てにかかる費用・後見人等の報酬について 東京家庭裁判所後見センター
一度選任されると原則として辞められない
成年後見人は本人の判断能力が回復しない限り、原則としてお亡くなりになるまで職務を全うすることになります。途中で辞めるためには家庭裁判所の許可が必要です。
成年被後見人以外の親族は自由に投資・運用などはできなくなる
成年後見人が選任されると、本人(成年被後見人)の財産は成年後見人が管理することになり、家庭裁判所からの監督も受けます。同居親族であっても、成年後見人以外の親族が本人の財産を自由に投資・運用などはできなくなるため注意が必要です。
例として、親族が本人の介護費用を捻出するために本人名義の不動産を売却したいと思っても、家庭裁判所の許可が必要になったり、成年後見人の判断に委ねられたりすることになります。
認知症の親族が不利になるような遺産分割はできない
成年後見人は、本人(成年被後見人)の利益を守るために遺産分割協議を進める義務があります。例として、特定の相続人に不利な分割案は認められないため、公平な遺産分割を目指すことになります。例として、他の相続人が「認知症で介護施設にいるのだから財産は不要」と主張しても通りません。
認知症の家族がいる場合の相続対策とは
相続発生後に成年後見制度を利用することも可能ですが、成年後見人の選任に要する時間や費用の負担、手続きの複雑さを考えると、認知症になる前から対策を講じておくことも大切です。
そこで、この章ではすでに認知症の家族がいる方向けに、相続対策をご紹介します。
成年後見制度を早めに利用する
先に触れたように、成年後見制度は申立てに時間を要するため、すでに認知症の家族がおり、別の親族の相続発生のリスクがある場合「成年後見制度」を早めに利用開始することがおすすめです。
成年後見人への報酬等が発生するため負担はかかりますが、スムーズな相続手続きができるため、相続税申告が遅れるなどのトラブルは避けられます。
また、認知症の家族が消費者トラブルや詐欺被害に巻き込まれるリスクも下げられるため、遠方に暮らす家族の判断能力に疑問があった場合は、早期の対策を行うことが望ましいでしょう。
遺言書の作成で遺産分割協議を回避する
相続対策の中でも、特に有効な方法は「遺言書」を作成しておくことです。遺言書があれば、遺産分割協議が不要となるため、円滑に遺産の分割を進められます。
遺産の分け方を巡る相続人同士の争いを未然に防いだり、認知症の家族を介護する方へ多くの財産を与えたりすることも可能です。介護への謝意を付言事項で述べることもできます。
ただし、遺言書は書き方を誤っている場合は無効となるおそれがあります。遺言書は公証役場で作成され、形式不備による無効のリスクが低い公正証書遺言が望ましいでしょう。
認知症になった親の遺言書の有効性については以下の記事を参考にしてください。
認知症になった親が作成した遺言書は有効なのか?
まとめ
本記事では、相続人に認知症の方がいる場合の相続手続きや、注意点について詳しく解説しました。相続人に認知症の方がいる場合、遺産分割協議は判断能力の観点から原則として進めることができず、成年後見制度の利用が必要です。
しかし、成年後見制度の利用には時間や費用がかかります。遺産分割を滞りなく進めるためにも、遺言書の活用などの相続対策を講じておくことがおすすめです。