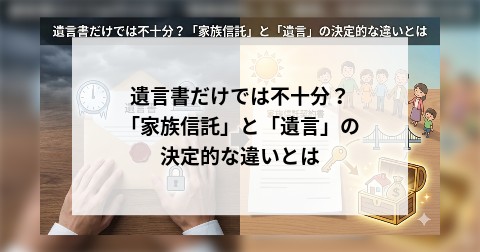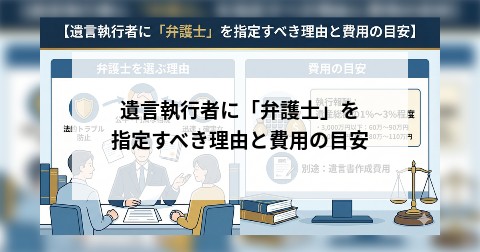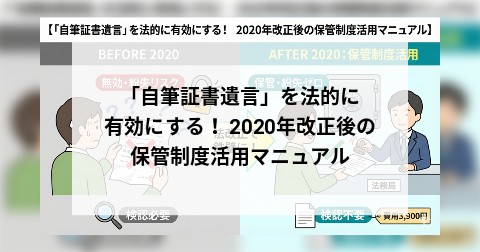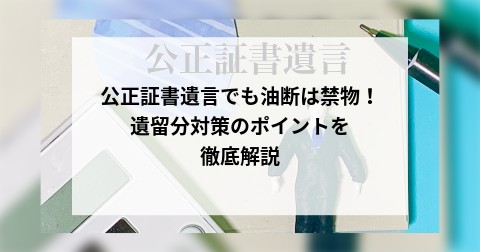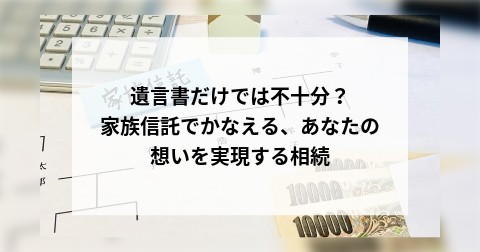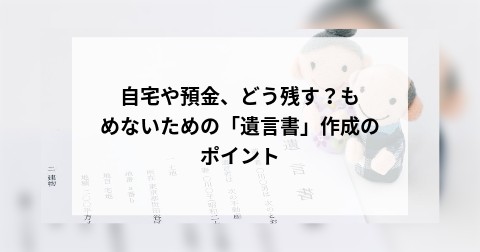認知症になった親が作成した遺言書は有効なのか?
親(被相続人)が認知症になると、相続時に親族間の争いが発生する可能性があります。認知症の被相続人が書いた遺言書は有効なのか?認知症がどの程度までなら遺言書は有効か? など不安に思われる方は少なくありません。
本記事では、どの程度の認知症の人が書いた遺言書なら有効なのか等を詳しく解説していきます。
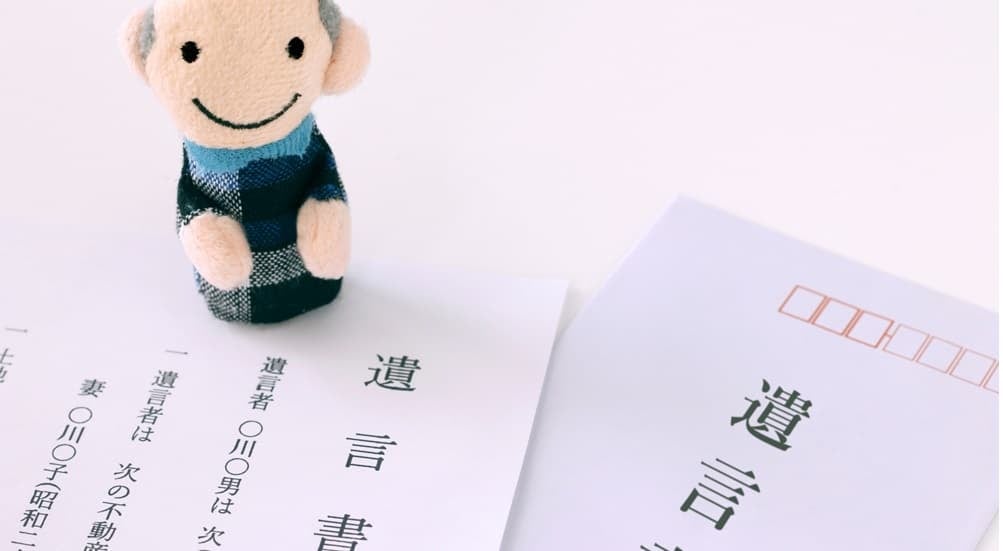
認知症の親が書いた遺言書は有効か無効か?
認知症だからといって、必ずしも遺言能力がないとはいえず、直ちに遺言書が無効になるわけではありません。
遺言書が有効か否かは、遺言者において遺言書の作成時に遺言能力があることが必要です(民法963条)
遺言能力とは?
遺言能力とは、遺言者が遺言事項を具体的に決定し、その遺言によって自分が死んだ後にどのような結果をもたらすのかを理解できる能力のことをいいます。
遺言者が満15歳以上で遺言の内容を理解し、その遺言によって自分の死後にどのような結果をもたらすのかを理解できていれば、遺言能力があると判断されます。
逆に、遺言者に遺言能力がないと判断されると、たとえ民法で定められた方式で作成された遺言書であっても、法的に無効になってしまいます。
遺言能力の有無の判断基準
認知症の人が書いた遺言能力の有効性の判断基準は、主に、次の3点の事情を総合的に考慮して判断されることになります。
・遺言時における遺言者の精神上の障害の有無・内容・程度
・遺言書の内容の複雑性
・遺言をするに至った経緯等
遺言時における遺言者の精神上の障害の有無・内容・程度
遺言能力の判断においては、遺言作成時の遺言者の心身状態が重要な事情となります。
遺言能力の有無については、以下のような医師が客観的に診断した資料が参考とされます。
・医師の診断書
・長谷川式認知スケール
・要介護認定の資料
遺言書の内容の複雑性
遺言能力の判断にあたっては、遺言の内容や効果を遺言者が理解していたかどうかもポイントになります。そのため、単純な内容であればあるほど、遺言能力があったと認められやすくなります。
遺言をするに至った経緯等
遺言者が遺言をしようと考えた理由がどのようなもので、その理由自体に一定の合理性があり、かつ、実際に作成された遺言の内容と作成理由がマッチしていれば、遺言作成に至った経緯に合理性があることになり、遺言能力が認められやすくなります。
遺言能力なしと判定されないための対処法
公正証書遺言で作成する
公正証書遺言は、作成時には公証人と証人2名が立会いのもと直接遺言者の言動を確認する段取りになっていますので、作成時点で遺言者の判断能力があったと判断される可能性が高い点が、認知症患者の遺言書作成に適していると言えるでしょう。
医師の診断を受けておく
遺言書作成と近い時期に、医師の診察を受けて、認知症ではないこと、あるいは認知症であるとしても軽度であることを記録に残しておくことが効果的です。
後のことを考えて、このような医師の診断を受けた上で診断書を発行してもらうと共に、長谷川式認知症スケール(HDS-R)などの検査で、評価を受けておくのも良いでしょう。
早期に遺言書を作成する
時間の経過とともに認知症が進行し、遺言能力を失う可能性が高まることを考慮し、早期に遺言書を作成することも重要です。また、遺言能力を認められやすくするためにも、遺言の中身を単純にしておくことも大切です。
遺言書が無効となるケース
遺言書が民法上の方式になっておらず不備がある場合
遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。法的に有効な遺言を作成し、確実な執行を望む場合は公正証書遺言が一般的です。
各方式については民法で厳密にルールが定められており、不備があると遺言書が無効になってしまいます。特に自筆証書遺言は、方式不備が原因で無効になってしまうことが少なくありません。
遺言能力がない状態で作成された場合
先述したように、遺言能力がないと判断されれば遺言書は無効になります。ただし、認知症=遺言能力無し、ではありません。進行状況によっては医師の立会いのもと作成することで有効な遺言書になる可能性もあります。
内容が不明確な場合
遺言書では、「どの財産を誰に相続させる」という遺志が正確に記載されている必要があります。遺言内容に不明確な条項が含まれている場合、その条項は無効となる可能性があります。
詐欺、強迫により遺言書が作成された
遺言者が詐欺、または強迫を受けたなどの事情で作成された遺言書は、取り消すことができます。ただ、詐欺や強迫は、すでに遺言者が亡くなっている以上、主張立証が困難であるため、実務上争点になることは比較的少ないと言えます。
内容が公序良俗に違反している場合
遺言書の内容が公序良俗に反する場合、その遺言書は無効となり得ます。公序良俗とは、公の秩序や善良な風俗を指し、社会的に受け入れられる基準を意味します。
証人の不適格
公正証書遺言には証人が2人必要ですが、その証人が法律の要件を満たしていない場合、遺言書は無効となります。証人は遺言者と利害関係がない人でなければならず、相続人やその配偶者、直系血族は証人になることができません。
証人が不適格であると、その遺言書は無効となります。
遺言書の有効・無効を確定する方法
認知症患者が作成した遺言書の有効・無効を主張する場合には、どのような方法があるのでしょうか。
遺言無効確認調停
被相続人の遺言が無効であることについて、相続人全員が合意できない場合には、家庭裁判所に対して遺言無効確認調停を申し立てます。
調停での話し合いの結果、遺言書を無効にすることについてすべての相続人の同意が得られたら、調停は成立となります。
遺言無効確認訴訟
遺言無効確認調停で話し合っても相手が納得しなければ遺言書の無効は確認できません。
その場合は地方裁判所で遺言無効確認訴訟を提起する必要があります。
認知症を理由として遺言無効確認訴訟を提起する場合には、原告において、前述の遺言能力の判断基準を踏まえて、遺言者に判断能力が無かったことを具体的に主張・立証していかなければなりません。法的な証明ができれば裁判所が「遺言書は無効である」という判決を下します。
遺産分割協議
判決で遺言の無効が確認された場合には、当該遺言は、無効となり存在しないものとして扱われます。
そのため、判決が確定した後は、相続人同士であらためて遺産分割協議を行って被相続人の遺産の分割方法を決めなければなりません。
遺言無効確認訴訟では、あくまでも遺言が無効かどうかについて判断されるだけであり、具体的な遺産の分割方法まで決まるわけではない点には注意が必要です。
まとめ
今回は親が認知症になった場合の遺言の有効性について解説しました。
遺言者が認知症の場合、作成された遺言書が有効か無効かを判断するには様々な要因などから判断されます。
基本的には症状が軽いうちに作成することが重要ですが、多少症状が進行していた場合にも、遺言書の形式や内容を工夫することで、有効と判断される可能性を高めることもできます。
認知症患者が遺言書を作成する際には、ぜひ早めの行動と、弁護士などの専門家からの適切な助言やサポートを活用することをご検討ください。