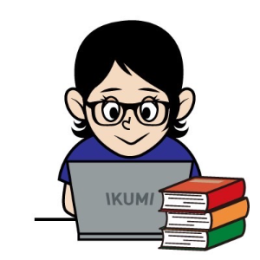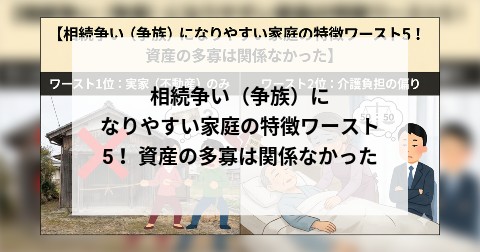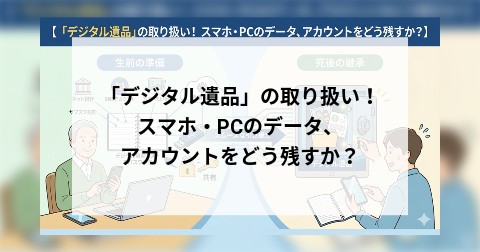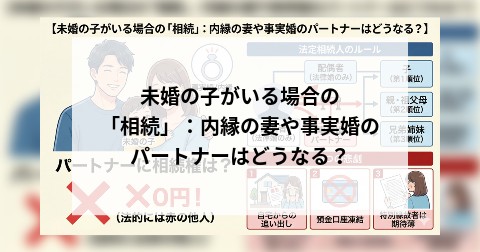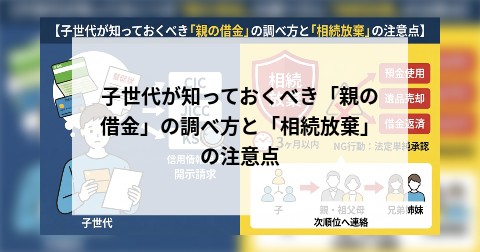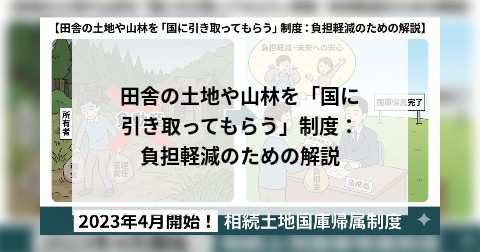相続の割合で揉めるよくあるケースとその対策
相続の割合を決める際には、家族関係などの影響によってトラブルが起きることがあります。遺産総額に寄らず、遺言書の作成や生前贈与などの方法でトラブルに備えましょう。

「家族の仲は良いから、相続を迎えてももめるわけがない」
「相続を円満に進めたいけど、もめる遺産の割り方ってあるの?」
相続が始まる前はそのように思っていた家族でも、実際に相続開始後には対立してしまうケースは決して少なくありません。特に、遺産の分け方、つまり相続の割合をめぐって相続人間が激しく対立するケースは多く、遺産分割調停や審判へと発展してしまうことがあります。
そこで本記事では、相続の割合を決める時によくあるトラブルケースや対策をわかりやすく解説します。円満な相続を実現するために、ぜひ最後までお読みください。
なぜ相続の「割合」でもめる?
相続の「割合」とは、被相続人の大切な遺産を相続人に分けることを意味します。遺言書がない相続で、複数の相続人がいる場合は相続人間で「遺産分割協議」を行い、遺産を誰が・いくら取得するか決めます。
では、割合を決める際にトラブルとなる原因にはどのような理由が挙げられるでしょうか。その背景には、単に財産を分けるという経済的な側面だけでなく、家族それぞれの複雑な感情、長年の関係性などのさまざまな要因が絡みあっているからです。
割合でもめる理由の多くは「不公平さ」が原因
遺産を分ける際には、基準となる「法定相続分」が民法により定められています(以下民法900条引用)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
|
1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 |
しかし、実際の遺産分割協議では被相続人との同居・非同居や、長年の関係性、生前の介護の有無などを考慮しながら話し合いを重ねて、各相続人が取得する遺産の割合を決めます。
法定相続人の中には長年疎遠であっても、遺産を取得する相続権がある人が協議に参加することもあります。
すると、長年介護や扶養で被相続人の生活を支えていた人は「なぜ遺産を欲しがるのか?」と不満を持ってしまうことも少なくありません。このような不公平さへの感情から、相続の割合をめぐる対立が発生するのです。
遺産総額が少なくても対立する
相続がもめる時は、高額の遺産をめぐって対立すると思っている人が少なくありません。しかし、実際には遺産総額が高額ではなくても、家族間で対立に発展するケースは多くなっています。
令和5年度の司法統計では、家庭裁判所で遺産分割調停に至った相続案件について、遺産総額別に分けており、以下の結果が出ています。
・争いが多い遺産総額のゾーンは1,000万超・5,000万円以下で3,166件
・次いでもめている遺産総額ゾーンは1,000万以下で2, 448件
つまり、億単位の遺産をめぐるトラブルよりも、よくある一般家庭の遺産分割こそもめやすいと言えるのです。
相続の割合を決める時によくあるトラブルケースを紹介
実際に遺産分割協議を迎えた時、遺産の取得割合をめぐるトラブルに発展するケースとはどのような内容でしょうか。この章ではよくあるトラブルのケースをわかりやすく紹介します。
1.疎遠な家族が相続人の中にいるケース
長年連絡を取っていない家族や、被相続人の前妻の子など、ほとんど顔も知らない兄弟姉妹相続人に名を連ねることがあります。疎遠な家族が相続人の中にいる場合、遺産分割協議はもめやすくなります。同居・非同居問わず、相続人になっている方は遺産を取得する権利があるため、遺産分割協議に参加してもらう必要があるのです。
法定相続分どおりに遺産分割をする場合も、長年介護していたか・扶養で貢献していたか考慮されることはありません。あくまでも遺産分割協議の中で話し合うしかなく、納得できない場合は調停へ移行する必要があります。疎遠を理由に、相続人に一切の遺産を無理矢理放棄させることはできません。
2.生前贈与が特定の相続人に対しては行われていたケース
被相続人が生前に特定の相続人に対して、暦年贈与や結婚資金、住宅購入資金など多額の贈与をしていた場合、他の相続人から「それは特別受益にあたる」として、相続財産に持ち戻して計算すべきだと主張されることがあります。
贈与は相続人間に不公平感をもたらしやすく、遺産分割の割合を決める際に火種になりやすいのです。
3.被相続人の介護・療養などに貢献した相続人がいるケース
被相続人の介護や療養に長年尽力した相続人は、「寄与分」を主張するケースがあります。わかりやすくいうと、生前に苦労した相続人は、他の相続人よりも多く遺産を取得できるという考え方です。
しかし、寄与分の主張は複雑な計算や証拠を必要とするため、必ずしも認められるとは限りません。相続人間に不公平感をもたらしやすく、遺産分割協議時にトラブルに発展しやすいケースです。
4.不動産が多く遺産分割をしにくいケース
遺産の中に多くの不動産が含まれている場合、現金や預金よりも分割しにくいため、もめやすくなる傾向があります。不要な田畑や、利益率が高い収益物件があるなど、不動産の種類が混在している場合はさらにトラブルになりやすいため注意が必要です。
分割が上手く進まない場合は、不動産を「共有名義」にすることも検討できますが、共有名義には以下のデメリットもあります。
・売却、賃貸、建て替えなど、将来的に不動産を処分・活用する際に、共有者全員の同意が必要となる
・共有名義者の死亡で相続が発生し、共有名義者がさらに増えてしまう
共有名義は問題をさらに複雑化させるおそれがあるため、できれば避けるべきでしょう。不動産を適切に分けるためには、代償分割や換価分割といった別の方法を検討する必要があります。
相続でもめないコツとは?3つの対策を解説
相続で遺産分割をめぐって争いが起きると、協議がまとまらず相続税申告が遅れてしまったり、調停・審判といった手続きに時間と費用を要したりするおそれがあります。そこで、この章では相続でもめないために、3つの対策方法を解説します。
対策1:遺言書の作成(生前にできること)
家族関係が複雑であったり、介護や扶養で貢献してくれた家族に財産を与えたい場合は生前に「遺言書」を残すことが有効な対策方法です。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことになりますが、それぞれの主張が異なると合意に至るまでに時間と労力がかかり、感情的な対立を生む可能性があります。遺言書があれば、誰に何を相続させるのかを故人が具体的に指定できるため、相続人間の争いを防ぐ大きな抑止力となります。
対策2:生前贈与を活用する(生前にできること)
特定の財産を確実に承継させたい場合には、生前贈与が有効な手段です。生前に財産を少しずつ贈与していくことで、相続時の遺産分割の対象となる財産を減らし、特定の相続人への財産移転をスムーズに行うことができます。
贈与には「暦年贈与」や「相続時精算課税制度」などの方法がありますが、一定額を超える贈与には贈与税がかかります。非課税枠や制度を理解し、計画的に行うことが重要です。
特定の相続人のみに多額の生前贈与が行われた場合、相続時に他の相続人から特別受益として主張される可能性があります。他の相続人への配慮も忘れずに行いましょう。また、生前贈与の計画や税金については、税理士に相談することがおすすめです。
対策3:相続人全員でしっかりと話し合う機会を持つ(相続開始後)
相続開始後は相続人全員で話し合う機会を持つことが非常に重要です。故人の想いや各相続人の希望を共有することで、お互いの理解を深め、感情的な対立を避けられます。
遺産分割協議には期限はありませんが、相続放棄や相続税申告、相続登記といった手続きには期限があります。早めに各相続人が取得する遺産の割合を決めましょう。
まとめ
本記事では相続の割合を決める際に起きやすいトラブルや、対策について詳しく解説しました。相続のトラブルは遺産総額が大きいから起きるとは限らず、生前の家族関係が色濃く影響します。遺言書の作成や生前贈与などの方法で、相続トラブルの回避に向けた準備がおすすめです。
遺産分割協議が長引いてしまうと相続税申告などに影響するため、お困りの際にはお早めに税理士などの専門家へご相談ください。