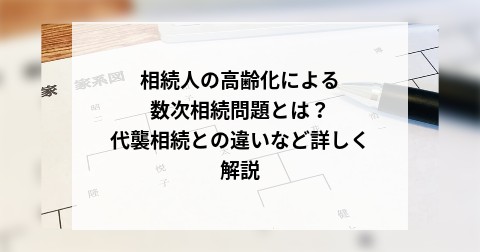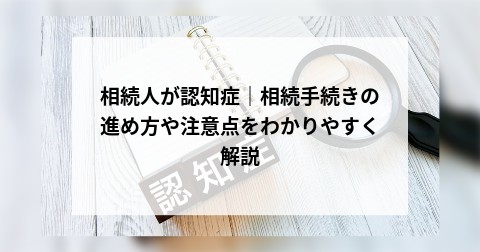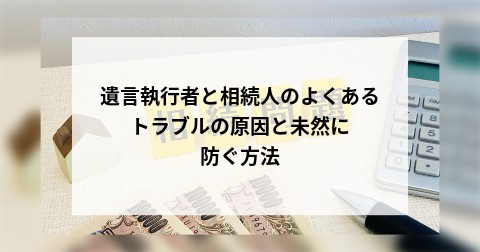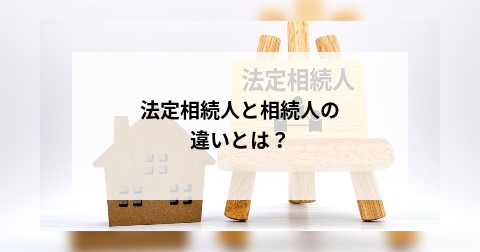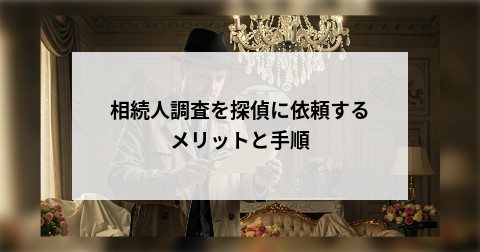二次相続対策がカギ!残された配偶者の生活を守るための相続戦略
両親のうち、一人目が亡くなったときの相続を「一次相続」、二人目が亡くなったときの相続を「二次相続」といいます。
相続税対策しだいでは、二次相続でも多額の支払いを回避できる可能性があります。
この記事では、二次相続について詳しく解説します。

二次相続とは?
二次相続とは、両親のうちどちらかが先に亡くなり、その相続人となった配偶者も亡くなって発生した相続のことを指します。
一方、両親のうちどちらかが先に亡くなって発生した相続を一次相続と言います。
二次相続は、一次相続と比べて相続税が高くなる傾向があります。
相続税が高くなりやすいのは、一次相続に比べ、下記のような理由があります。
- 基礎控除額の低下
- 相続額の増加
- 配偶者控除がなくなる
基礎控除額の低下
相続税は相続をしたら必ず支払わなければならないものではありません。
相続した財産のうち一定の金額を超えた財産にのみ課税されます。一定の金額を「基礎控除額」といい、相続人が多いほど、金額が高くなります。
つまり相続人が多いほど相続税を支払う金額が少なくなります。
具体的には、相続人1人あたり600万円が基礎控除額に足されるため、配偶者がいない二次相続では一次相続よりも600万円分基礎控除額が低くなります。
相続額の増加
一次相続では、配偶者が財産の半分を相続し、子どもの相続人は残りの半分を等分して相続します。
しかし、二次相続では、半分の財産を相続する配偶者がいないため、子どもだけで財産を等分して相続することになります。
結果として二次相続では、課税対象となる相続額が一次相続よりも高額になるのです。
また、二次相続の相続人は、一次相続で継承した財産と、もともと配偶者が所有していた財産の合計金額を相続するため、一次相続よりも高額な財産を相続することが多いです。
配偶者控除がなくなる
配偶者控除とは、相続人が配偶者の場合、1億6千万円、もしくは、配偶者の法定相続分までの課税価格のうち、大きいほうの額まで非課税となる制度です。
この制度を利用して、節税のために一次相続では配偶者へ多くの財産を相続することがあります。
一次相続で相続税を支払う必要がなかった相続人でも、二次相続では配偶者控除を利用した相続税対策ができないため、支払う可能性があります。
一次相続と二次相続の違いは?
一次相続と二次相続の違いは、相続が発生するタイミングと相続人の構成にあります。一次相続は、配偶者と子どもが相続人となる最初の相続を指し、二次相続は、一次相続後に残された配偶者が亡くなった際に発生する、子どもだけの相続を指します。
相続人の構成
一次相続では配偶者と子どもが相続人となりますが、二次相続では配偶者が亡くなっているため、子どもだけが相続人となります。
相続税の計算
相続人が減ることで、基礎控除額が少なくなり、相続税の税率が高くなる可能性があります。また、配偶者の税額軽減の特例が使えなくなるため、相続税の負担が増える傾向があります。
相続税対策
一次相続で配偶者に多くの財産を相続させると、二次相続で子どもへの相続税負担が大きくなる可能性があります。そのため、一次相続と二次相続の両方を考慮した相続税対策が重要になります。
二次相続対策の具体例
財産の分割
一次相続で全ての財産を配偶者に相続させるのではなく、子供にも分配することで、二次相続時の税負担を分散させる方法があります。例えば、評価額の高い不動産を子供が相続し、配偶者には現金や預貯金を相続させるといった分割が考えられます。
生命保険の非課税枠を活用する
生命保険の受取金は、「法定相続人×500万円」までの非課税枠が活用できます。
受け取った生命保険金は相続税の課税対象となりますが、非課税枠を利用すれば相続税の節税につながります。
例えば受け取った保険金が300万円で子ども一人の場合、200万円分課税対象額が減るということです。
ただし一次相続時に保険金の受取人は子どもにしておく必要があります。
一次相続の段階から生前贈与しておく
一次相続の段階から生前贈与を行うことで、被相続人(亡くなった人)の財産を減らせるため、相続税が安くなります。
生前贈与とは、生前中に財産を贈与することで、年に110万円以下であれば非課税で贈与できます。
ただし、110万円以上の財産を贈与したり、110万円以下でも継続して贈与し続けたりすると、贈与税の課税対象となるため注意が必要です。
また、相続から過去3年以内の生前贈与も相続税の対象となるため、早めに贈与しておくことをおすすめします。
まとめ
二次相続の負担を軽減するためには、一次相続から計画的に対策を行うことが欠かせません。配偶者控除や生前贈与、生命保険の活用など、適切な方法を選ぶことで家族の負担を減らすことが可能です。
相続税対策を考えるときには、夫婦の相続を合わせて考えることが非常に重要になるため、まずは専門家である税理士にご相談ください。