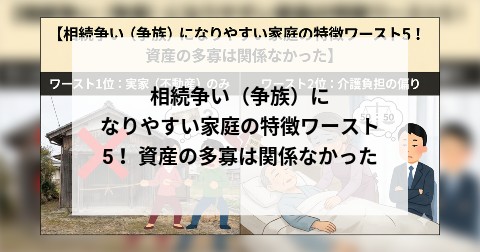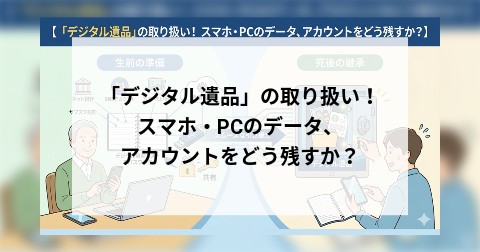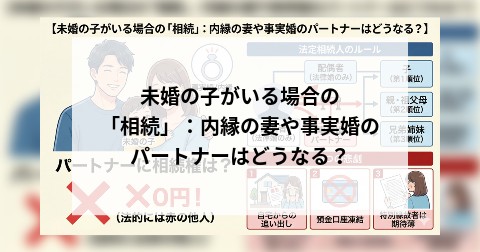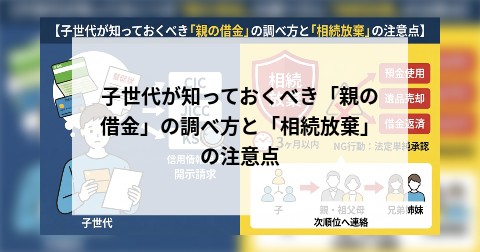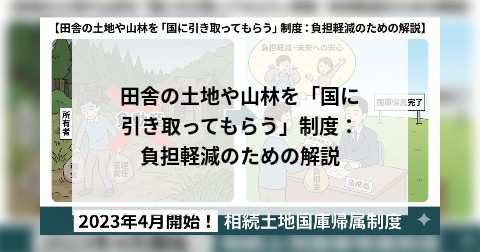遺言執行者と相続人のよくあるトラブルの原因と未然に防ぐ方法
相続問題にはトラブルがつきものという印象がありますね。
本記事はトラブルの中でも、遺言執行者と相続人の間で生じるよくある問題について扱っていきます。
円滑な相続手続きにお役立ていただけると思いますので、最後までお付き合いください。

本記事から学べるポイント
|
遺言執行者は遺言を作成する時に選任できる信頼のおける人が選ばれます。 |
本記事で、上記の内容をさらに詳しく分かりやすく解説していきますので、最後まで読んで参考にしていただければ幸いです。
遺言執行者とは
遺言執行者の任命は、故人が指定し遺言で残した内容を実現させる方法と、相続人が家庭裁判所に申し立てる方法があります。
いずれの場合も、相続人の代表として相続関係の手続きをする権限と義務を持ちます。
では誰が遺言執行者になれるでしょうか。また選任されることでどんなメリットがあるでしょうか。具体的に解説していくことにしましょう。
遺言執行者になれる人とは
遺言執行者には、特別な資格は必要とされておらず、18歳以上の成年で破産者以外なら誰でもなれます。
とはいっても、相続についての経験と知識を持ち合わせている人が望ましいです。
なぜなら、相続には膨大な必要書類を扱わねばならず、経験と知識がないと書類を収集するだけで挫折し、任務を果たせなくなる可能性があるからです。
さらに時間的な余裕を持っている人であることも重要な要素となります。相続業務は多くの面倒な手続きが求められるからです。
遺言執行者が選任されているメリット
遺言執行者が存在するメリットとして、一つ目は遺産相続で相続人間のトラブルが起きた時に発揮されます。
遺言執行者が選任されていると、強い権限を持ち独立した立場でトラブルに関係なく、あくまで遺言を執行できるので、スムーズな相続手続きを進める上で大いに助かります。
また2つ目のメリットとして煩雑な相続手続きの手間が省けることです。
相続人が多くなると手間も増え、相続人一人ひとりの署名捺印が必要とされる書類も増え複雑で煩雑になってきます。
しかし、遺言執行者が選任されていると、それらの書類がなくても手続きが進められるのです。これは手間を大きく省略できるのでメリットといえるでしょう。
よくある遺言執行者と相続人の間でのトラブル
遺言執行者が選任されるメリットを説明しましたが、反対に遺言執行者が相続トラブルの元となることがあります。どんな場合でしょうか。以下に説明していきます。
遺言執行者と相続人が同一である場合に起こりやすい
遺言執行者は信頼のおける人なら誰でもなれるとこれまで説明しましたが、遺言執行者が相続人の一人である場合に特にトラブルの原因となることがあります。
以下の2つの理由が考えられますので注意しましょう。
公平性に欠ける
遺言の内容によって、多くもらえる相続人と法定相続分より少ない額の相続人が出てくることがあります。その時がもめる原因となるうえ、遺言執行者に指定されている相続人は、遺産を多く受け取る側であるケースが多いのです。
そうなると、公平性に欠けるということで、当然その他の相続人から不満が噴出することになり、遺言の執行が妨げられてしまいます。
感情的に対立しやすい
普段は仲の良い相続人同士の関係も、利害関係が絡むとトラブルになりやすいのが相続問題です。それで、遺言執行者と相続人との間で元から関係性があまり良くない時は特に、感情的な対立が一層起こりやすくなるでしょう。
遺言内容の解釈に相違がみられる
遺言の内容にあいまいな部分があると、遺言執行者と相続人の間で解釈が違ってくることがあります。
そうした解釈の相違はトラブルの原因となりますから、遺言を作成する時には誰が読んでも一目瞭然にわかる明快な内容にしておくことが必要ですね。
遺言執行者の報酬額が高すぎる
遺言執行者の報酬が高すぎる時もトラブルの原因となります。
遺言執行者の報酬は、遺言に記されている場合と相続人が遺言執行者の経験を基にして本人と話し合って決める場合があります。
しかし、不相応に高額な報酬が請求されトラブルになった場合は、家庭裁判所に申し立てて減額を求めたり、代わりに決定してもらったりできます。
遺産分割協議で相続人同士と遺言執行者がもめる
遺言がない場合は、相続人全員が集まって遺産分割協議をしなければなりませんが、その際に相続人同士でもめることが多くあります。
さらに、遺言執行者が選任されている場合でも、その遺言執行者と意見が対立しトラブルに発展すると、相続問題が泥沼化していきます。
遺言執行者と相続人間のトラブルを未然に防ぐ方法
先述のよくある遺言執行者と相続人のトラブルを解説しましたが、それを基にトラブルを未然に防ぐ方法を考えてみましょう。
遺言執行者と相続人を同一にしない
相続人同士で揉めやすいのですから、遺言執行者と相続人を同じにしない方がいいというのはよく理解できますね。
遺言執行者は、遺言執行においては、あくまで厳正中立で相続と利害関係が絡まない信頼できる第三者にしておくことは賢明といえるでしょう。
遺言内容を明確にする
遺言内容に明確に不明瞭な部分を残さないため、遺言書を作成する時には専門家のアドバイスを受けながら作成するのがベストです。
相続人同士のコミュニケーションを円滑にする
日ごろから相続人同士がコミュニケーションを取り合い、いい関係性を築いておく必要があります。
そうするなら互いの立場や意見を尊重しあうことで感情的な対立を避け、相続問題にも対処できる下地を作っておけるでしょう。
弁護士などの専門家を頼る
続問題はとかくトラブルが発生しやすい問題です。
トラブルは、資産家が起きやすいと思われがちですが、遺産が5000万円以下の場合でも頻発している現状なのです。
そうしたトラブルは深刻化しないうちに、弁護士などの専門家に相談して対応してもらうことが重要なポイントとなります。
遺言執行者は辞任・解任できる
遺言執行者として選任を受けていても、やむを得ない事由がある時は辞任・解任が可能です。
遺言執行者の辞任
遺言執行者は、就任を承諾した以上は「正当な事由」がない限り、自由に辞任できないことになっています。
正当な事由として、長引く病気、長期の出張、多忙すぎて遺言の執行が困難になった場合などが挙げられ、相続問題が嫌になったとか面倒になったということでは辞任は認められません。
また辞任するときには、相続人に伝えるだけでなく、家庭裁判所の申し立てを行い、辞任の許可が必要です。
遺言執行者の解任
遺言執行者が職務を怠った、相続人をえこひいきする、相続財産の使い込みなど正当な理由があるとき、家庭裁判所に申し立てることで遺言執行者を解任できます。
まとめ
本記事から遺言執行者とのトラブルのよくある事例から、トラブルを未然に防ぐ方法などを解説してきました。
相続問題は複雑で膨大な作業ですが、遺言執行者と快い関係を保ちながら遺言執行を進めることで、相続期限にスムーズに間に合わせ、故人の遺志を尊重した結果を刈り取れるでしょう。