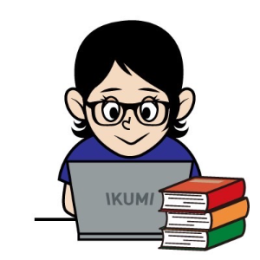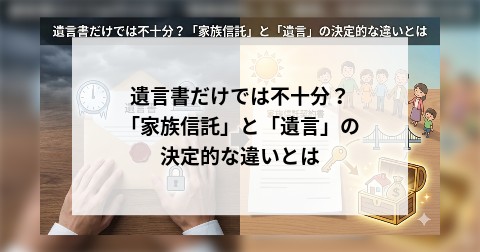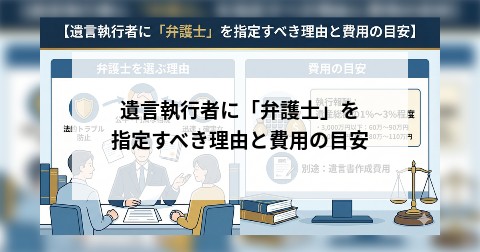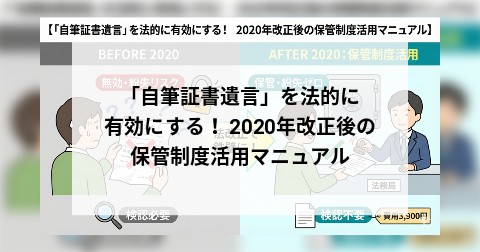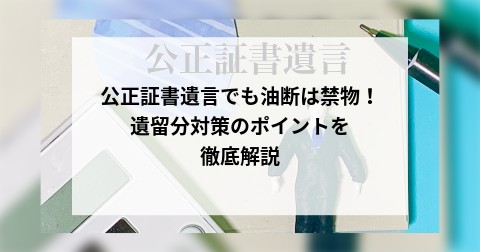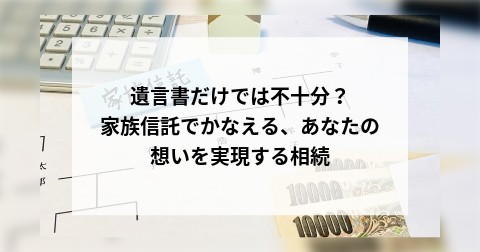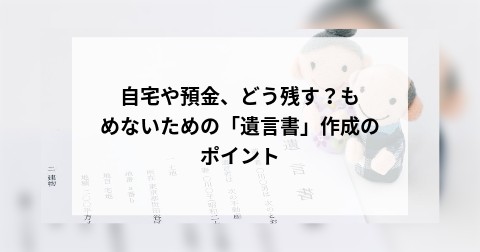遺言書がトラブルになりやすいパターンと対処法
遺言書が原因で家族がもめるケースは少なくありません。本記事ではよくあるトラブルのパターンと、もしトラブルに直面した場合の対処法をわかりやすく紹介します。

「遺言書トラブルになりやすいパターンとは?対処法や注意点も解説」
家族が自分の相続で揉めないように、そんな思いを込めて作られることが多い「遺言書」ですが、遺言書がきっかけとなりトラブルが起きてしまうケースも少なくありません。また、遺言書は書き方を誤ってしまうと「無効」となるおそれもあるため、注意しながら書く必要があります。
そこで、本記事では遺言書についてトラブルになりやすいパターンをご紹介します。トラブル時の対処法や注意点もあわせて解説しますので、ぜひご一読ください。
よくある遺言書トラブルのパターンとは|8つの事例を紹介
遺言書に関するトラブルは、原因も内容も多岐にわたります。この章では、特に多く見られる8つのパターンを紹介します。
1.遺言書が無理矢理作成されたおそれがある
遺言書は、遺言者(遺言書を書く人)の自由な意思に基づいて作成されるべきものです。しかし、相続人の一人や第三者から「この内容で遺言書を書くように」と強く指示され、本意ではない内容の遺言書を作成させられるケースがあります。
もしも特定の相続人に有利過ぎる内容の遺言書だった、被相続人が生前に話していた遺言内容とはあまりにもかけ離れている場合、無理矢理作成された可能性があり、相続人間でトラブルに発展するおそれがあります。
2.遺言書の記載内容が不明瞭
遺言書の記載内容が曖昧な場合も、遺言書トラブルに発展するおそれがあります。複数の解釈ができる、誰に何の財産を遺すのか不明瞭などのケースが該当します。
例として、「私の財産は大切な土地を長男に、その他は次男に相続させる」とだけ書かれていたとします。大切な土地、がどこの土地を意味するのかこれでは理解が難しいでしょう。長男と次男の間で、土地を巡って対立するおそれもあります。
この他にも、預貯金の口座番号が間違っていたり、多数の財産が表記されていない場合、一体どのように相続すればいいのかわからず、トラブルになりやすいでしょう。
3.遺言書の改ざんなどの不正が疑われる
遺言書が作成された後に、明らかに一部が書き換えられたり、破棄されたりするなどの不正行為が疑われる場合も大きなトラブルに発展します。特に「自筆証書遺言」は、保管状況によっては改ざんされやすいため注意が必要です。(※1)
(※1自筆証書遺言書保管制度なら、法務局で原本と画像データが保管されます)
4.遺言の内容に多くの相続人が納得できない
遺言書の内容が特定の相続人にのみ有利で、他の相続人の期待していた相続分とあまりにもかけ離れている場合、不満を抱いた相続人が遺言の有効性を争う可能性が高まります。
特に、長年親の介護をしてきた相続人に考慮がない遺言内容だった場合、納得できずにもめるケースは少なくありません。
5.遺留分の侵害が発生している
遺留分の侵害も、遺言書トラブルのよくあるパターンの1つです。「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された、最低限の遺産の取り分を意味します。
遺留分を侵害する内容の遺言書を書くこと自体には、法的な問題はありません。しかし、実際に遺留分を侵害する内容が書かれていた場合、遺留分を侵害された相続人は、多く財産を取得する相続人などに対して「遺留分侵害額請求」を行う可能性があります。
6.法定相続人以外への遺贈が記載されている
法定相続人以外への遺贈が遺言書に書かれている場合、法定相続人は納得できずトラブルになるおそれがあります。遺贈は個人だけではなく、地方公共団体やNPO団体などの団体へ行うことも可能ですが、相続人が争う可能性も考慮する必要があるでしょう。
7.遺産分割後に遺言書が見つかってしまった
遺言書がない場合、複数の法定相続人がいる場合は遺産分割協議を行います。しかし、すでに遺産分割協議が成立した後に、遺言書が発見されるというケースもあります。
新たな遺言書の内容が、すでに完了した遺産分割の内容と大きく異なる場合、相続人は再び遺産分割について協議し直さなければならなくなる可能性があります。
8.認知した子がいるなど、特殊なケースの遺言書であった
生前に認知していなかった子を、遺言書で認知することができます。しかし、法定相続人が被相続人に家族が知らない子がいたことを死後に知ることとなり、大きなショックと共に遺言内容についても争う可能性は高くなります。なお、認知した子がいる場合、その子も法定相続人に数えます。
また、再婚などによって複数の配偶者との間に子がいる場合や、養子縁組をしている場合なども、相続関係が複雑になり、遺言書の解釈や遺産分割で意見が対立することがあります。
このようなケースは多くはないものの、発生する可能性はあります。
遺言書のトラブルに直面したらどうする?
遺言書のトラブルに直面したら、一体どのように対処すればよいでしょうか。この章では対処法を簡潔に解説します。
まずは相続人間で協議を行う
法定相続人全員で合意ができたら遺産分割協議を優先することが可能です。ただし、内縁の配偶者などへの遺言内容を覆す場合は弁護士に相談し、どのように相続を行うべきか慎重に進めることが望ましいでしょう。
遺言無効確認訴訟を行う
遺言書の有効性を争う場合は、家庭裁判所に遺言無効確認訴訟を提起できます。
この訴訟では、遺言書の作成過程や内容に法的な問題があったかどうかを裁判所に判断してもらうことになります。
遺留分の侵害は請求できる
遺留分の侵害があった場合は、多くの財産を受けた人に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。遺留分侵害額請求には時効(※2)があるため、早めに弁護士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。
(※2)遺留分の侵害を「知った時」から1年で時効、相続開始から10年で除斥期間が終わります。
トラブルのない遺言書を作るコツとは
遺言書は気軽に残すことができるものの、ここまでの解説のとおり慎重に作らなければ大きなトラブルにつながるおそれがあります。では、トラブルのない遺言書はどのように作ればよいでしょうか。
専門家へ相談する
遺言書は弁護士・税理士・司法書士・行政書士の士業が扱っており、依頼すると法的なアドバイスを受けながら作成できます。遺留分など専門知識が必要なケースにも対応しており、必要に応じて「遺言執行者」(※3)に関しても依頼できます。
(※3)遺言を実現するためにさまざまな手続きを担う人のこと
自筆証書遺言は避ける
無料で気軽に作れる「自筆証書遺言」ですが、改ざんや紛失のリスクも高く、ミスの多さから無効となる可能性もある遺言方式です。できれば公正証書遺言のように、安全性が高い遺言書を作るようにしましょう。
税理士なら相続税シミュレーションもできる
税理士へご相談いただくと、相続税対策(生前含む)や相続税シミュレーションも交えながら遺言書を作成することが可能です。事業継承や多くの財産の相続が予定されている場合は、税理士に依頼することもおすすめです。
まとめ
本記事では遺言書について、トラブルになりやすいパターンや、安全な遺言書の作り方を紹介しました。遺言書は、遺された家族への大切なメッセージですが、書き方や内容によっては、予期せぬトラブルを引き起こしてしまう可能性があります。
実際に作成する際には専門家に相談しながら、慎重に遺言書を作成していくことが望ましいでしょう。
この記事の監修者
中澤 泉(なかざわ・いずみ)
弁護士(東京弁護士会所属)
法律事務所にて、債務整理、交通事故、離婚、相続など、幅広い市民法務を担当。その後はメーカーの法務部にて、契約審査や社内法務体制の整備など企業法務にも従事した。
また、事務所勤務時には法律事務所のウェブサイト立ち上げやコンテンツ監修にも携わった経験を持つ。
現在は、弁護士登録を維持しながらフリーランスのライター・編集者として活動し、法律分野を中心に記事の執筆・監修を行っている。
「法律をもっと身近に、わかりやすく届ける」をモットーに、専門性と伝わりやすさを両立した情報発信に取り組んでいる。