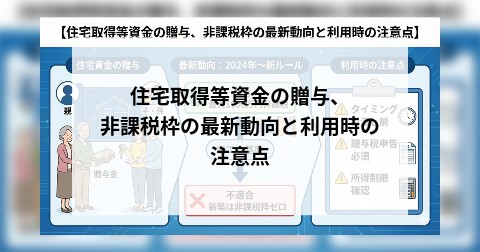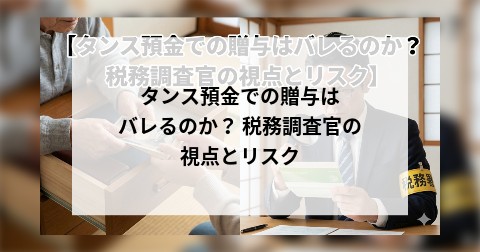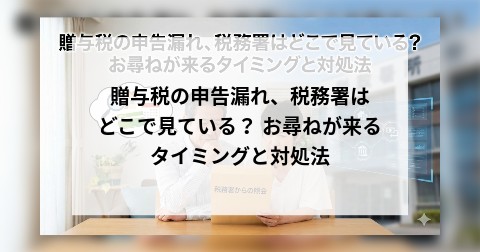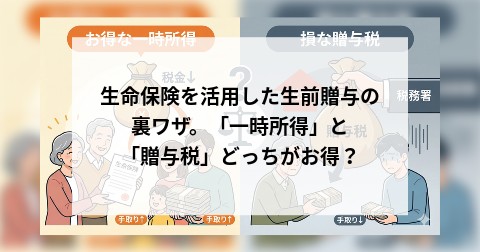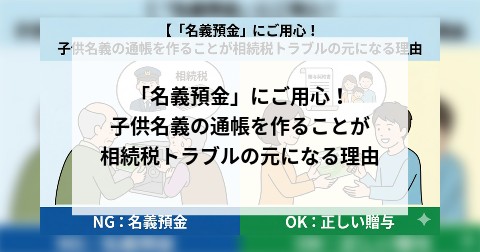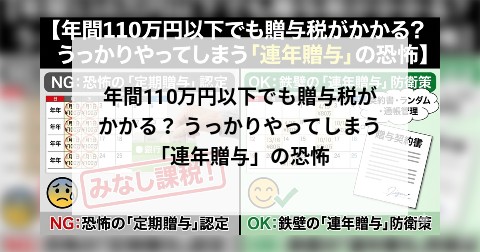税理士なら誰でもいいは危険!相続税で税理士を選ぶポイントと注意点
遺産を相続する際は、財産の金額によって相続税が発生します。
相続税の計算や申告を税理士に相談しようと考える方は多いと思われますが、税理士なら誰でもいいだろうと考えて、あまり吟味せずに税理士を選ぶのは危険です。
本記事では、相続税ではなぜ税理士選びが重要なのか、税理士の選び方や注意点についても解説していきます。

相続税は税理士選びが重要な理由
相続税の申告を税理士に依頼する場合、相続に強い税理士を探して依頼することが重要になります。
税理士なら誰でもいいだろうと考えて適当な税理士に依頼すると、税金を余分に払う事態になったり、後々税務調査で追徴課税が発生し、税金を追加で納付しなければならなくなったりする可能性があります。
相続税を依頼する場合に、税理士選びが重要になる理由を解説します。
「税理士=全ての税務に詳しい」ではない
税務は所得税や法人税、贈与税など多岐に渡り、どの税務を主に扱っているかは税理士によって異なります。
また、税理士試験において相続税は選択科目のため、相続税を集中的に勉強していない税理士もいます。
他にも、公認会計士や弁護士、国税OBなど一定の要件を満たした方は、税理士登録をするのに税理士試験が免除されます。
このような理由から、税理士だからといって全ての税務に詳しいというわけではなく、中には相続税の知識があまりない税理士もいます。
相続税の計算は難しい
相続税を計算する際は、遺産の種類ごとに法令や通達などで定められた方法により相続税評価額を求める必要があります。
不動産や株式、生命保険など遺産の種類ごとに計算方法が細かく決まっており、相続税に詳しくないと計算を間違う可能性が高まります。
また、土地や非上場株式などは計算方法が複雑であり、知識だけでなく実務経験が必要です。
さらに、相続税では税負担を軽減する特例制度が多くあり、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例による土地の評価減などは、特例を適用するかどうかで税負担が大きく違ってきます。
各特例制度の存在を把握し、適用できるかを正しく判断するには相続税に対する知識が必要のため、相続税を普段あまり扱っていない税理士が相続税計算を担当した場合、相続税が高く計算される可能性があります。
相続税申告はほとんど経験していない税理士もいる
令和4年度の相続税申告件数は150,858件なのに対し、税理士登録者数は約8万人であり、単純計算で税理士1人あたりが年間で扱う相続税の件数は1~2件ほどになります。
しかし、実際には相続に強い税理士が年間におおよそ10件以上の相続税を扱っており、相続税申告の経験がどれほどあるかは税理士によってかなりばらつきがあります。
相続税の申告では多数の資料を用意する必要があり、相続税申告の経験があまりない税理士だと、効率的な資料の準備ができません。
他にも土地の相続税評価額を算定する場合、評価するのが難しいケースも多数存在し、適切な評価計算をするには件数をこなし経験を積む必要があります。
相続税申告の経験があまりない税理士が1人で相続税申告を行うのは難しいため、相続税の申告を税理士に依頼する場合、担当の税理士が相続税の経験を積んでいるかを確かめる必要があります。
相続税を相談する税理士の選び方
相続税は計算が特殊で難しいため、税理士に相談する際は相続税に強い税理士を選ぶ必要があります。
それでは、どういった基準で税理士を選べばいいのか、判断材料について解説します。
相続税の申告件数はどれくらいか
一般的な税理士が年間に扱う相続税の申告件数は0~2件である一方、相続を専門とする税理士の場合、年間でおおよそ10件以上の相続税を扱います。
規模の大きい税理士事務所などの場合、年間で数百件を扱う場合もあります。
担当する相続税の申告件数が多いほど、知見やノウハウが蓄積されているため、適切な申告により相続税を抑えるだけでなく、二次相続など将来の相続についてアドバイスもしてくれます。
また、多くの申告で依頼者と接してきた経験から、依頼者が不安に思う点を先回りすることができ、相続税の申告期限までにやるべきことやスケジュールなど、依頼者が不安に思わないようしっかり説明があります。
そのため、相続税について税理士を選ぶ際は、年間でどれくらいの相続税申告を担当しているかを確かめるといいでしょう。
税務調査対応ができるか
税務調査とは、税務申告をした後に税務署が財産などの調査をしにくることです。
調査対象になるのは、申告書の内容に不明点や申告もれがあるケース、単純に相続財産が多く相続税額が多いケースなどです。
仮に税務調査が入った場合でも、税務署とのやり取りまで同じ税理士が担当してくれるかがポイントです。
税務調査対応が豊富な税理士や、国税庁出身・税務署出身の税理士が在籍している税理士事務所や税理士法人であれば、税務調査の際に税務署がどういった点を確認するか把握しやすいため、スムーズに対応ができます。
依頼を考えている税理士事務所や税理士法人が、その後の税務調査まで対応してくれるかを確かめるようにしましょう。
二次相続まで踏まえた提案ができるか
二次相続とは相続を受けた方が亡くなり、更に相続が発生することです。
例えば、両親と子1人で、父が亡くなり父の財産を母と子が相続した後、母が亡くなって、父の相続財産と母の相続財産を子が相続するようなケースが二次相続です。
一次相続で税額を最小に遺産分割した場合でも、二次相続の税額までを合わせるとかえって税額が高くなってしまう場合もあり、二次相続までを含めて税額を抑えるにはシミュレーションをする必要があります。
ただし、シミュレーションには一次・二次相続の相続税を算定しないといけないため、税理士に頼むのが確実です。
その場合でも、遺産の分割パターンに応じて、どうすれば税金が最小になるかを把握するには、ある程度の相続の経験が必要です。
今回の一次相続を二次相続まで合わせて考えたいことを税理士に伝え、どういった提案をしてもらえるかで税理士を選ぶのも1つの手です。
弁護士など他の専門家と連携しているか
税理士ができるのは税務相談と税金の申告の範囲までであり、例えば不動産登記は司法書士など、遺産分割調停や審判の申し立ては弁護士に依頼する必要があります。
これらの手続きは自分ですることも可能ですが、手間と時間がかかります。
また、専門知識がないと遺産分割で紛争が起きた場合に不利になったり、話がこじれたりする可能性があります。
他の専門家と連携している税理士や、他の専門家も在籍している税理士事務所や税理士法人を選ぶと、税務申告以外の相続手続もスムーズに行えます。
また、相続専門の税理士事務所や税理士法人では、相続財産の保守・運用やファイナンシャルプランニングを提供する専門家と連携している場合もあります。
そのため、相続税申告をきっかけに金融商品の仲介、不動産の売買、保険紹介といった資産運用についても併せて提案を受けられます。
ただし、税理士や弁護士に別々に依頼しても手間がかかる以外に特段の問題はなく、また、税理士と連携している専門家だからといって報酬が安くなるとは限りません。
相続財産の資産運用まで提案してくれるのは大手の税理士事務所や税理士法人が多く、その場合は中小規模のところに比べ報酬が高くなる傾向があります。
税理士報酬は適正か
相続税の税理士報酬の相場は一概にはいえないものの、概ね下記が目安です。
「遺産総額×0.5%~1%」
例えば遺産総額が2億円の場合、税理士報酬は100万円~200万円ほどが相場といえるでしょう。
なお、遺産総額はプラスの財産合計のことで、借入金などのマイナスの財産は含めず、小規模宅地等の特例や生命保険金の非課税など評価を減額する前の金額を報酬計算の基準にしているケースが多いようです。
ただし、相続人が多い、相続税の申告期限まで間近で急な対応を要する、評価の難しい財産があるなどのケースの場合、追加報酬が発生することもあります。
「安い方が良い」というのではなく、適正報酬で誠実に向き合ってくれる税理士を選ぶようにしましょう。
価格が気になる場合、事前に税理士報酬の見積りを出してくれる税理士事務所や税理士法人もありますので、いくつか候補を選び、相見積もりを取るのもいいでしょう。
税理士を選ぶ際の注意点
税理士に相続税の申告を依頼した際に、場合によっては期待していたサービスが受けられなかったり、予想よりも多額の税理士報酬がかかったりする場合があります。
そういった事態にならないように、税理士を選ぶ際の注意点について解説します。
「相続専門」という言葉だけで選ばない
最近は税務業界で低価格競争が起こっており、相続税の案件を獲得したいと躍起になっている税理士事務所や税理士法人が多数存在し、実態に関わらず「相続税に強い」「相続専門」と謳っているケースが存在します。
そのため、ホームページに相続専門と書いているから、という理由だけで税理士事務所や税理士法人を選ぶのはやめた方がいいでしょう。
実際に年間どれくらいの相続税申告を担当しているのか、二次相続まで踏まえた提案をしてもらえるかなどの事項を基準に税理士を選ぶようにしましょう。
成功報酬制の場合は注意する
一見すると税理士報酬が安くても、「成功報酬」を別途設けている税理士もおり、その場合はかえって税理士報酬の総額が高くなってしまった、という場合もあります。
成功報酬とは、例えば評価が難しい相続財産があった場合に、評価額を低く抑えた結果、相続税が少なくなったとします。
その安くなった部分に対して数%の報酬が発生する、というものが成功報酬です。
成功報酬が法律で禁じられているわけではなく、成功報酬を取っている税理士がただちにダメというわけではありません。
しかし、数千万円の節税に対して数百万円の税理士報酬を要求されるなど、基本報酬を大きく上回る額が発生し、依頼者との間でトラブルになるケースもあります。
そのため、税理士に依頼する前に料金体系についてよく確認する必要があります。
依頼前に契約書による説明を要求し、どのような場合に成功報酬が発生するのか書面にそって説明を受けることで、そのようなトラブルを回避できるかもしれません。
報酬が相場より大幅に安い税理士には注意する
税理士報酬が他の税理士より大幅に安い場合は注意が必要です。
その場合、相続が専門外だったり、薄利多売でとにかく時間をかけずに大量に相続案件を処理したりする税理士の場合があるからです。
そういった税理士の場合、相続税の申告書にあまり時間や手間をかけず、税金を抑える検討をせずに通り一遍の処理をして終わらせる可能性があります。
その結果、本来は適用できる特例や控除が使われず、相続税を余分に支払う必要があったり、申告書にミスや不備があり、税務調査が入り追徴課税が発生したりするリスクが発生します。
まとめ
相続税は計算が難しく、税理士によってはほとんど相続税の申告を経験していない場合があります。
さらに、相続税は特例の適用により税額を大幅に抑えられる場合があります。
そのため、相続税の申告を税理士に依頼する場合は、相続税申告の経験が豊富な税理士かを確認して依頼するようにしましょう。
また、報酬が相場より大幅に安い税理士を選ぶと、本来は適用できる特例や控除を適用せずに申告をし、余分に相続税が発生したり、申告書のミスや不備により追徴課税が発生したりする危険性があります。
相続税の申告件数や税務調査対応の可否、二次相続を踏まえた提案をしてもらえるかなどを基準に、相続に強い税理士を探して相談をするようにしましょう。
この記事の監修者
濵川誠司(濵川誠司税理士事務所)
資格:税理士
出身地:愛知県
経歴:税理士法人、コンサルティング会社での税務担当業務(相続税、贈与税、事業承継、法人・個人事業主の事業サポート)
得意分野:相続税
趣味:ドライブ