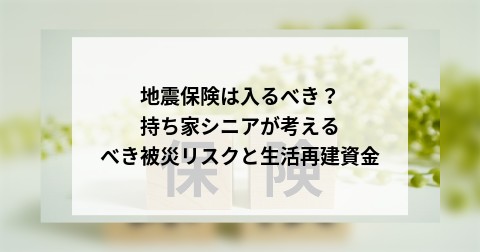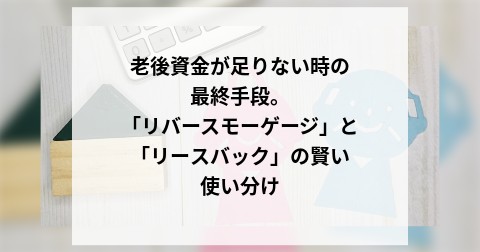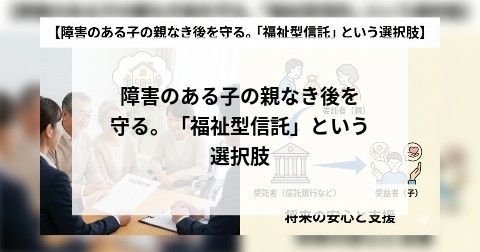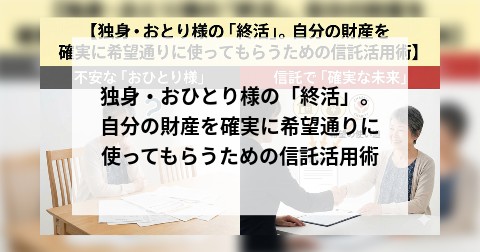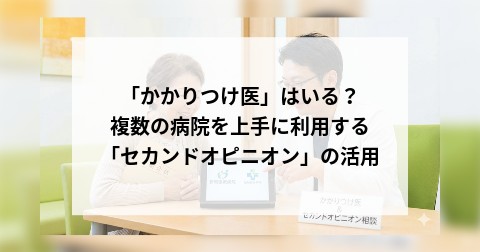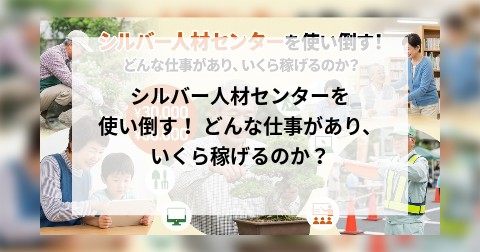医療費控除、確定申告。シニアが知っておくべき「税金」の賢い活用法
公的年金収入が主な生活の柱となるシニア世代にとって、税金の負担はできるだけ抑えたいものです。しかし、所得税や住民税に関する知識がないために、本来受けられるはずの控除を見過ごしているケースも少なくありません。
この記事では、シニア世代が知っておくべき「税金」の賢い活用法として、特に「医療費控除」と「確定申告」に焦点を当て、そのメリットと手続きのポイントをわかりやすく解説します。

年金と税金の基本
公的年金は、雑所得として課税対象になります。ただし、一定額までは「公的年金等控除」が適用され、課税所得から差し引かれます。この控除額は年齢によって異なり、65歳以上の方が優遇されています。
-
65歳未満:公的年金等の収入金額が70万円以下の場合、控除額は60万円。
-
65歳以上:公的年金等の収入金額が120万円以下の場合、控除額は110万円。
ご自身の年金収入と控除額を確認し、確定申告が必要かどうかの目安にしましょう。
知らないと損する!シニアに特化した控除制度
①医療控除
負担した医療費が、1年間の合計で10万円以上になった場合、所得税が軽減されて税金が戻ってくるのが「医療費控除」です。確定申告で手続きを行えば、税金が還付される形で、支払った医療費の一部を取り戻すことができます。
医療費控除の対象としては、以下のようなものが認められます。
【治療・検査のための費用】
- 医師、歯科医師による治療の費用
- 自由診療(全額自己負担の治療)や、先進医療の費用
- あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の費用
- 保健師や看護師等による療養上の世話に対する支払い
- 患者の通院費(交通費)や医師に往診してもらう送迎費
- 入院の際の部屋代、食事代
- 治療のためのコルセット、義手・義足・松葉づえ、補聴器、義歯などの購入費
- 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせん料、日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植あっせん料
【医薬品購入の費用】
- 医師の処方箋をもとに調剤薬局で購入した医薬品の購入費用
- 街の薬局で購入したかぜ薬・胃腸薬などの一般医薬品の購入費用 など
【介護に関する費用】
- 介護福祉士などによる喀痰吸引及び経管栄養の対価
- 介護老人福祉施設や介護老人保健施設に支払った施設サービス料 など
これらを見ても分かるとおり、対象となるものは、公的保険が使えるかどうかに関わらず、医療費控除は可能であることがわかります。がん治療の先進医療や自由診療を受けた場合、自己負担額が大きくなることがありますが、これらも医療費控除の対象となりますので、確定申告を行って少しでも費用負担を減らしたいものです。
医療費控除のための具体的な手続き
医療費控除は税金を取り戻す仕組みですので、控除を受けるためには確定申告を行うことが必要です。サラリーマンの場合、会社が年末調整を行ってくれるため、確定申告にあまり縁がない方もいるかもしれませんが、医療費控除を受けるためにはサラリーマンであってもご自身で確定申告を行う必要があります。医療費が高額になった翌年は忘れずに確定申告を行いましょう(確定申告は、毎年2月16日〜3月15日の間に、前年分の申告を税務署に提出します)。
申告手続きを進めるにあたり、いくら実際に税金を支払ったか、治療費を負担したかを証明する書類を残しておかなければなりません。具体的には、
- 給与の源泉徴収票(サラリーマンの場合)
- 支払った医療費の明細書(自分で作成)
が必要になります。2017年分の確定申告から、医療費の領収書の添付は必要なくなりましたが、必要となった場合のために手元にはしばらく保管しておきましょう(5年間の保存義務あり)。
また、家族の誰が申告しても構いませんので、収入が高い家族が申告したほうが戻るお金も増えて、お得です。
②セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制とは、1年間(1月1日〜12月31日)に特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費用が12,000円を超えた場合に、その超過分を所得から差し引くことができる制度です。
控除額:実際に支払った購入費用の合計額 - 12,000円(上限88,000円)
軽い風邪薬や胃腸薬、湿布薬なども対象になります。ご自身や家族の健康維持のために購入した医薬品のレシートは、必ず保管しておきましょう。
年金以外の所得がある場合の確定申告
公的年金収入のみで源泉徴収されている場合、確定申告は不要なケースが多いですが、以下のような場合は確定申告が必要です。
-
給与所得や事業所得など、年金以外の所得がある
-
年間400万円を超える公的年金収入がある
-
生命保険の満期金など、一時所得がある
-
医療費控除やセルフメディケーション税制などを利用したい
確定申告を行うことで、納めすぎた税金が還付される場合があります。特に医療費控除などは、ご自身で申告しなければ適用されません。
相続・贈与に関する税金の知識
シニア世代にとって、相続や贈与は身近な問題です。
-
贈与税の基礎控除:年間110万円までは贈与税がかかりません。生前贈与を検討する際は、この非課税枠を有効活用できます。
-
相続税の基礎控除:3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)の控除額があります。相続財産がこの金額を超えない場合は、相続税はかかりません。
まとめ:まずは「知る」ことから始めよう
税金の制度は複雑で難しく感じられるかもしれませんが、ご自身に適用される制度を知るだけで、手元に残るお金は大きく変わります。
-
医療費や薬の領収書は必ず保管する。
-
給与や年金、その他所得を正確に把握する。
-
不明な点があれば、お近くの税務署や税理士に相談する。
まずは「知る」ことから始めて、賢く税金を活用し、豊かなセカンドライフを送りましょう。