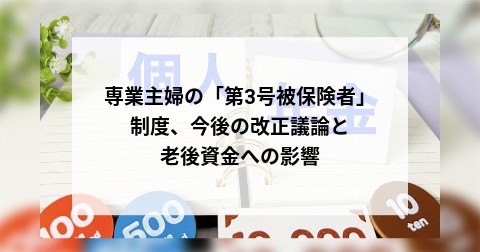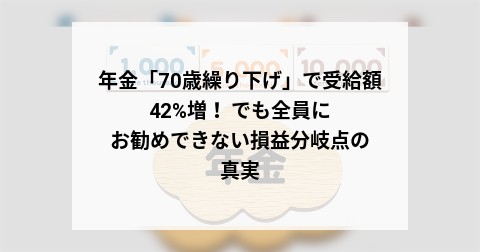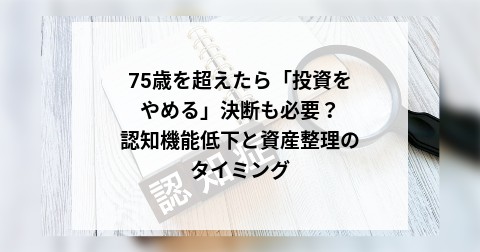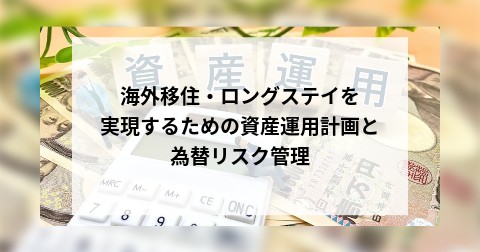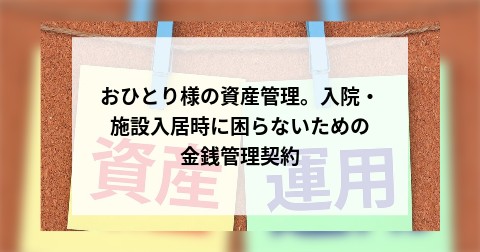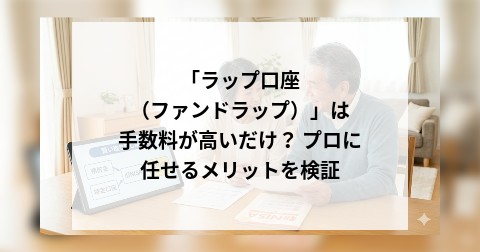年金だけじゃ心細い?「月3万円」のゆとりを作るシニアの資産運用術
長寿化が進む現代、公的年金だけで豊かな老後を送るのは難しいと感じている方は少なくありません。そこで注目されているのが、老後の生活資金を自分で作り出すための資産運用です。
この記事では、年金に「月3万円」の上乗せを目指すシニア世代向けに、無理なく始められる資産運用のポイントと具体的な方法をわかりやすく解説します。

なぜ「月3万円」を目指すのか?
高齢夫婦無職世帯の平均的な生活費は、月26万円程度と言われています。一方、公的年金の平均受給額は、夫婦二人で月22万円程度です。単純計算でも、毎月約4万円の不足が生じることになります。
この不足分を補い、さらに少しのゆとりを作るために、「月3万円」の資産収入を目標に設定します。この目標額なら、リスクを抑えながら現実的に目指すことが可能です。
いくら資産運用に回せるのかを考える
資産運用は、余裕資金(しばらく使う予定がないお金)で行うのが原則です。今の家計の状況ならいくらくらい運用に回せそうかを考えてみましょう。
運用にお金を回しすぎたせいで生活が圧迫されたり、近いうちにやりたかったことができなくなったりするのはよくありません。また、そもそも貯金がまったくない状態や生活がギリギリな状態なら、資産運用より先に貯金を優先するべきでしょう。
万が一の事態に備えるため、まずは生活費の3〜6ヶ月分を目安に、いつでも引き出せる普通預金として確保しておきます。これを超えた分が、運用に回せるお金となります。
生活費として確保すべき金額を無視して運用に回してしまうと、急な出費に対応できなくなり、最悪の場合、損をしている状態で資産を売却せざるを得ない状況に陥る可能性があります。
資産運用の基礎知識を身に付ける
リスクについての考え方
資産運用には「リスクとリターンは比例する」という原則があります。高いリターンを求めるには高いリスクを取る必要があり(ハイリスク=ハイリターン)、リスクを抑えようとするとリターンが少なくなる(ローリスク=ローリターン)ということを覚えておきましょう。リスクなしで、お金を大きく増やせる投資はありません。
リスクやリターンは、どんな資産運用をするかによって変わります。また、どれくらいのリターンを求めるか、どこまでのリスクに耐えられるか(リスク許容度)は人によって異なります。
なお、リスクを抑えたい場合は「長期・積立・分散投資」が有効とされています。初心者は特に、1つの商品に大金を一気に投入するのではなく、数十年先を見据えて、少額ずつコツコツと、複数の商品に分散して資産運用し続けるのがおすすめです。
資産運用の基礎知識を身に付ける方法
資産運用に関する基礎知識を身に付けたいなら、例えば以下のような方法があります。
- 書籍(本、雑誌など)を読む
- セミナー(証券会社などが開催する初心者向けの講演、オンラインの動画講座など)を受講する
- 資格取得(ファイナンシャルプランナーの資格など)の勉強をする
- 金融や経済に関するニュースを日々チェックする
- 金融庁などの公的機関が公開している教材や情報サイトで学ぶ
まずは、投資初心者向けの解説本をいくつか手に取って読んでみるのがおすすめです。なぜなら基本的な仕組みや専門用語などが丁寧に説明されていて、体系的な知識を得やすいからです。複数冊を読み比べれば、知識の偏りを防ぎつつ、どの本でも触れられている重要なポイントを頭に入れることができるでしょう。
月3万円のゆとりを生み出すための運用方法
毎月3万円のゆとりを生み出すには、元本をただ増やすだけでなく、「定期的に収益を得る」仕組みを作ることが重要です。
ここでは、比較的リスクが低いと考えられる2つの方法をご紹介します。
①毎月分配型の投資信託
毎月分配型投資信託は、分配金が毎月払い出されることで、資産を取り崩しながら残余資産を運用できる商品です。
分配金は定額ではありませんが、分配金が減額された場合でも、投資信託の一部を解約(換金)することで、資産の計画的な取り崩しを継続することが可能です。
また、運用利回りの高い銘柄であれば、取り崩す期間が長くなることも期待できます。ただし、リターンの高い銘柄はリスクも高い傾向があるため、注意が必要です。
毎月分配型のおさえておきたいポイントは以下になります。
分配金は、資産を取り崩して支払われる
押さえておきたい分配金の知識の1つ目は、「分配金は資産の取り崩しである」です。
預貯金や債券、株式の場合は、利子・利息や配当金が支払われたからといって、その元金や価格は変わりません。しかし、投資信託の場合は、分配金が支払われると基準価額がその分だけ下がります。
この違いは、それぞれのお金を「誰が支払うか」という点に由来します。利子・利息や配当金であれば、それを支払うのは銀行や企業ですが、分配金は、その投資信託の純資産(投資信託が保有する株式や債券の時価総額から、経費などを差し引いた資産のこと)を取り崩して支払われます。
そして、基準価額は、この純資産を総口数(すべて投資家の持ち分の合計)で割ったものなので、分配金によって純資産が減れば、その分だけ基準価額は下がるというわけです。
分配金は、必ずしも利益を意味しない
押さえておきたい分配金の知識の2つ目は、「分配金が必ずしも利益を意味するわけではない」です。
投資信託では、株式などを売買したり、配当金などを受け取って得た利益が、分配金の原資になります。分配金はその一部が支払われたものなのですが、分配原資の範囲内でしか分配金は支払えない決まりになっています。
とはいえ、分配原資は、相場が下落して基準価額が下がったからといって減るものではなく、また、すべてを一度に払い出す必要もありません。そのため、仮に500円の分配原資があれば、基準価額が下がっていても今期に100円、来期に100円、その次の期にも100円といった具合で分配することも可能です。
分配金が定期的に振り込まれていると、「運用が順調」「利益が出ている」と思いがちです。ただ、分配方針が、「安定的に分配金を支払うことを目指す」というようなものであった場合などには、分配金が支払われたとしても、利益が出ているとは限らないという点は、押さえておく必要があります。
②高配当株・ETFへの投資
企業が稼いだ利益の一部を、株主に還元するお金を「配当金」と呼びます。
高配当株とは、この配当金を多く支払う企業の株式のことです。また、ETF(上場投資信託)とは、特定の指数(日経平均株価など)に連動するように運用される投資信託で、こちらも配当金(分配金)が支払われるタイプがあります。
-
メリット:業績が安定している企業の株を選べば、比較的安定した配当金収入が期待できます。
-
注意点:企業の業績が悪化すると、配当金が減額されたり、無配になったりするリスクがあります。また、株価が下落する可能性も考慮する必要があります。
まとめ
資産運用は、必ず儲かるものではありません。しかし、ご自身のライフプランに合わせて、無理のない範囲で賢く活用することで、豊かなセカンドライフを送るための大きな支えになります。
ご紹介した運用方法を参考にしながら、まずは少額からでも始めてみてはいかがでしょうか。