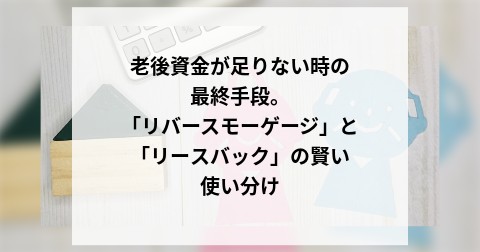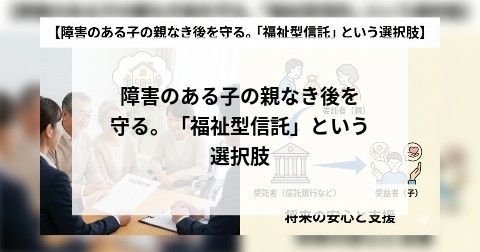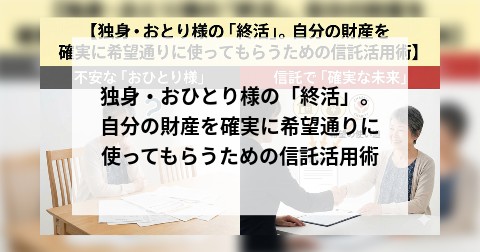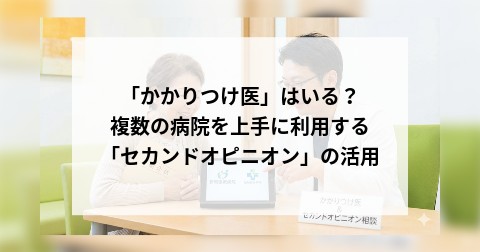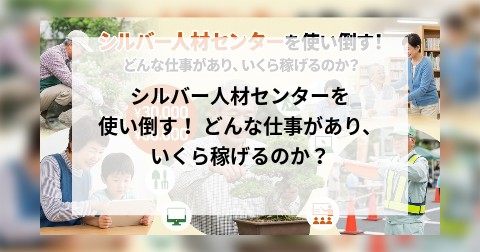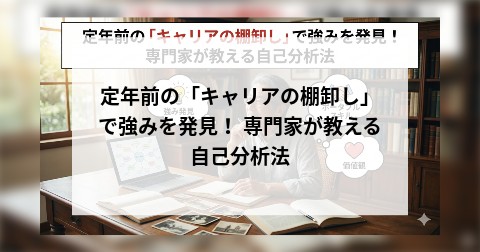シニアこそ狙われる!巧妙化する詐欺から資産を守る「防犯リテラシー」
「まさか自分が騙されるなんて」。そう思っていても、現代の詐欺は驚くほど巧妙です。特にシニア世代は、長年かけて築き上げた大切な資産を持っていることに加え、他人を信じやすい、電話や訪問によるコミュニケーションに慣れているといった点から、詐欺のターゲットにされやすい傾向があります。
大切な資産を守るためには、もはや「詐欺に注意」という漠然とした意識だけでは不十分です。
本記事では詐欺の手口を知り、自ら危険を回避する力を身につける「防犯リテラシー」を向上させるための方法を記載していきます。

なぜシニアが狙われるのか?
高齢者が特殊詐欺の主要なターゲットとなる背景には、複数の要因があります。
認知機能の低下と判断力の衰え
加齢に伴い、記憶力や判断力が低下することがあります。詐欺師は、この衰えを利用し、巧みな話術で高齢者をだまします。多くの人が詐欺の手口を知っていても、「自分だけはだまされない」という過信に陥りやすい傾向があります。しかし、加齢による判断力の鈍化は自覚しにくく、この「自分は大丈夫」という思い込みが詐欺師に付け入る隙を与えます。
社会的孤立と寂しさ
家族や友人との交流が減り、社会的に孤立しがちな高齢者は、詐欺師にとって格好のターゲットとなります。詐欺師は「あなたの力になりたい」「一緒に解決しましょう」などと言葉巧みに近づき、高齢者の寂しさにつけ込みます。
豊富な資産の存在
高齢者は長年にわたって蓄積した年金、貯蓄、不動産など豊富な資産を持っていることが多く、詐欺師にとって魅力的なターゲットとなっています。そのため、「必ず儲かる投資話」や「お得な土地の購入話」など、高齢者の資産を狙った巧妙な話術で近づく詐欺師は後を絶ちません。
情報リテラシーの不足
インターネットやスマートフォンの普及に伴い、オンライン詐欺が増加しており、情報リテラシーの不足が高齢者が詐欺被害に遭う要因の一つとなっています。フィッシング詐欺やワンクリック詐欺など、巧妙化するネット詐欺の手口に高齢者は翻弄されがちです。
SNS型投資詐欺やロマンス詐欺は、1件あたりの被害額が高額になる傾向があります。情報リテラシーの不足は、単にITツールの使い方が分からないだけでなく、オンライン上の情報の真偽を見極める能力の不足にもつながります。これにより、高齢者は、一見すると正規の情報源に見える偽サイトやメッセージに容易にだまされてしまいます。
特殊詐欺の定義
「特殊詐欺」とは、被害者に電話をかけるなどして直接対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振り込みやその他の方法によって、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪の総称です。
かつては「振り込め詐欺」という呼称が一般的でしたが、手口の多様化に伴い、2020年以降、警察庁は特殊詐欺を10種類に分類しています。特に高齢者を主なターゲットとするのは、主に電話を介したオレオレ詐欺、預貯金詐欺、還付金詐欺、架空料金請求詐欺、融資保証金詐欺、キャッシュカード詐欺盗といった「振り込め詐欺」の類型です。
高齢者を狙う詐欺の代表的な手口
詐欺の手口は時代とともに進化し続けていますが、基本的なパターンを理解しておくことで、被害を未然に防ぐことができます。以下に代表的な詐欺の手口をご紹介します。
【特殊詐欺】オレオレ詐欺、還付金詐欺の手口
特殊詐欺の中でも最も多いのが「オレオレ詐欺」です。子どもや孫を装って「事故を起こした」「会社のお金を使い込んだ」などと電話をかけ、示談金や弁償金名目でお金を要求します。警察官や弁護士、銀行員になりすましたりするケースも増えています。
また、「還付金詐欺」では市役所や税務署の職員を装い、「医療費の還付金がある」「保険料の払い戻しがある」などと言って、ATMへ誘導し、実際には振り込み操作をさせる手口です。公的機関がATMの操作を指示することは絶対にありません。この点を覚えておくだけでも、被害を防ぐことができます。
フィッシング詐欺と架空請求
スマートフォンやパソコンを利用する高齢者が増えるにつれ、オンライン詐欺の被害も増加しています。フィッシング詐欺では、実在する銀行や通販サイトを装ったメールが送られ、リンク先の偽サイトで個人情報やクレジットカード情報を入力させます。
架空請求では、利用していないサービスの料金を請求するメールが届きます。支払わないと法的措置をとると脅し、高齢者を恐怖に陥れ、お金を振り込ませようとします。
ネット詐欺を防ぐためには、不審なメールを開かないことが重要です。
また、URLをよく確認し、怪しいサイトにアクセスしないよう注意しましょう。請求内容に覚えがない場合は、決して支払いに応じてはいけません。
訪問販売と悪質商法
訪問販売による詐欺も高齢者を狙った手口の一つです。「屋根の無料点検」と言って訪問し、実際には問題がなくても「このままでは危険」と不安をあおり、高額な修理契約を結ばせる手口があります。また、「特別価格」「今日だけ」などと言って、健康食品や浄水器などの高額商品を契約させる事例も多いです。
訪問販売の被害を防ぐには、むやみに自宅に入れないことが大切です。また、契約書をよく読み、内容を理解してから署名するよう心がけましょう。
クーリングオフ制度を利用できる場合もあるので、トラブルにあったら消費生活センターに相談することをおすすめします。
高齢者を詐欺から守るための対策
高齢者を詐欺から守るためには、家族や地域、社会全体での取り組みが必要です。特に身近な家族ができる対策から、より専門的な支援まで、段階的に取り組むことが効果的です。
日常的なコミュニケーションと情報共有
詐欺防止の第一歩は、家族間の定期的なコミュニケーションです。週に1回程度は電話や訪問で近況を確認し、金銭的な話題も自然に会話に取り入れることが大切です。最近の詐欺事例について新聞記事やニュースを共有し、「もしこんな電話がきたらどうする?」と具体的な対応を話し合っておきましょう。
家族間で「合言葉」を決めておくことも効果的です。例えば、本当の家族からの電話かどうか確認するための秘密の言葉や、緊急時の連絡方法などを事前に取り決めておくことで、なりすまし詐欺を見破ることができます。
通信機器の整備
詐欺の多くは電話から始まります。迷惑電話防止機能付きの電話機への交換や、電話会社が提供する迷惑電話ブロックサービスの導入を検討しましょう。最近では、AIが怪しい電話を自動検知して警告してくれるサービスも増えています。
また、留守番電話を活用するのも効果的です。「知らない番号からの電話には出ず、まず留守番電話に録音してもらう」というルールを徹底することで、冷静に対応する時間を確保できます。スマートフォンを使用している場合は、迷惑メール対策アプリの導入も検討しましょう。
金融機関の防犯サービス活用
多くの銀行では、高齢者向けの詐欺防止サービスを提供しています。例えば、一定額以上の引き出しや振込みに制限をかけたり、普段と異なる取引があった場合に家族にも通知が行くサービスなどがあります。こうしたサービスを利用することで、被害を未然に防いだり、早期発見につなげたりすることができます。
また、キャッシュカードの利用限度額の引き下げも効果的な対策です。普段使わない分のお金は定期預金にするなど、すぐに引き出せない形で管理することも検討しましょう。必要に応じて、家族が共同で口座を管理できる「家族信託」などの仕組みを活用することも一つの方法です。
まとめ
詐欺は、年々手口が巧妙化し、誰にでも被害に遭う可能性があります。大切なのは、詐欺の手口を知り、自ら危険を回避するための「防犯リテラシー」を身につけることです。「怪しいな」と感じたら、一人で悩まず、家族や警察、消費生活センターに相談してください。
相談先
-
警察相談ダイヤル(#9110): 詐欺の疑いがある場合や、不安なことがあった場合に相談できます。
-
消費生活センター: 契約トラブルや悪質な商法などについて相談できます。