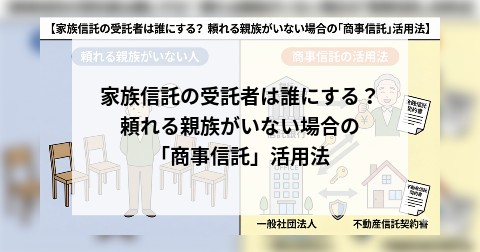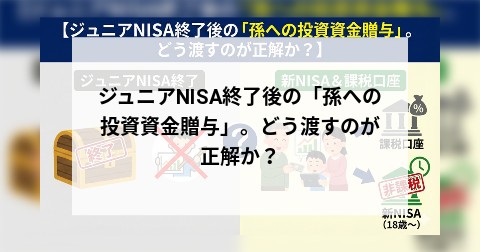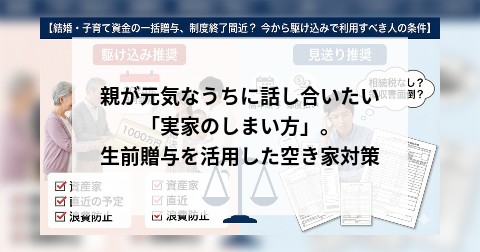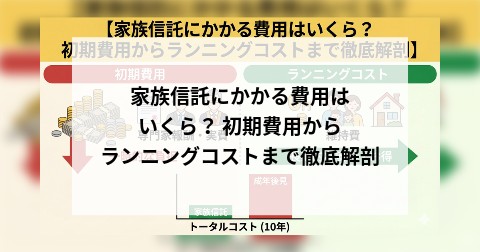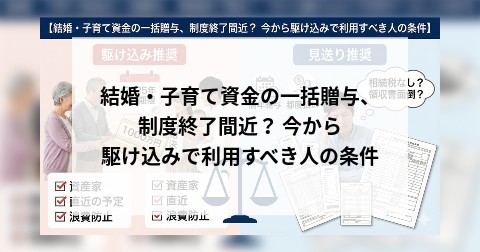贈与 vs 相続、どっちがお得?後悔しないための生前贈与活用ガイド
大切な財産を次の世代に引き継ぐ際、「贈与」と「相続」、どちらの方法を選ぶべきか迷う方は少なくありません。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分の状況に合った方法を選ぶことが、後悔しないための第一歩です。
この記事では、贈与と相続の基本的な違いから、賢く生前贈与を活用するためのポイントまでをわかりやすく解説します。

相続税とは
| 法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 一億円以下 | 30% | 700万円 |
| 二億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 三億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 六億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 六億円超 | 55% | 7,200万円 |
贈与税とは
贈与税とは、個人から年間110万円を超える財産の贈与を受けた際に課される税金です。相続とは異なり、贈与は財産を渡す側の人が生きているときでもおこなえます。
贈与と相続の基本的な違い
| 贈与 | 相続 | |
| 時期 | 生前に行う | 死亡時におこなわれる |
| 課税されるタイミング | 贈与の都度、贈与税が課税される | 死亡時、相続税が課税される |
| 税率 | 贈与税の方が、一般的に高い | 相続税の方が、一般的に低い |
| 特徴 | 財産を計画的に分割できる | 遺産分割協議が必要になる場合がある |
贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額に対して課税されます。贈与税には「暦年贈与」と「相続時精算課税」の2つの制度があります。
相続税は、亡くなった方の財産を相続した際に課税されます。相続税には基礎控除があり、遺産総額が一定額以下であれば相続税はかかりません。
生前贈与のメリット・デメリット
生前贈与をすることによって、どのようなメリット、あるいはデメリットがあるのでしょうか。以下では一般的なものについて記載します。
生前贈与のメリット
生前贈与のメリットとしては、相続税の節税効果や遺産分割・財産の承継対策等が考えられます。
①相続税の節税効果
生前贈与が相続税の節税効果になるのは、生前贈与をすることで、相続開始時の相続財産が少なくなるからです。
相続税は、相続開始時に被相続人が有していた財産の額が基準となります。したがって、生前に110万円の暦年贈与や相続時精算課税制度を利用し、財産を移転させておくことで、相続開始時の相続財産を減らすことができます。
贈与税は高額の税金が課税されるというイメージがあり、実際税率は高いのですが、課税される税金が高いのは、一度に財産を移転させた場合です。
例えば1100万円を一度に移転させた場合、贈与税(一般贈与の場合)は271万円となります。しかし、年間110万円ずつ10年間贈与し、その合計が1100万円の場合は、贈与税はゼロです。
このように、移転させる額や時期、受贈者を分散させることによって、贈与税は相続税よりも税負担が少なくなる場合があります。
②遺産分割効果
特定の相続人に特定の財産を取得させたい場合に、生前贈与を利用することができます。
例えば、居住用不動産や同族株式・事業用財産を、特定の相続人に取得させたい場合が考えられます。相続が開始した後の遺産分割協議によって、相続人間で合意できればよいのですが、そのようにまとまる保証はありません。
そのため、生前贈与によって特定の相続人に財産を移転させる方法も考えられます。
③相続人以外の第三者に財産を贈与できる
生前贈与は、誰に対しても行うことができます。例えば、内縁の妻(夫)やお世話になった方、親しい友人やNPO法人などの公益団体でも構いません。
相続の場合、相続財産は原則として法定相続人に帰属するため、法定相続人以外の第三者に財産をあげたい場合は、生前贈与を検討してもよいでしょう。なお、遺言によって遺贈することも可能ですが、遺言の方式や記載内容によっては、スムーズに手続ができない可能性もあります。
生前贈与のデメリット
①手続費用がかかる場合がある
生前贈与をする財産(主に不動産)によっては、手続のための費用や税金がかかることがあります。
例えば、不動産を暦年贈与する場合、毎年110万円に相当する持分を移転することが多いですが、その際、不動産の名義変更にかかる費用(司法書士費用、登録免許税、不動産取得税等)が発生します。
なお、贈与によって(推定)相続人に不動産の名義を変更する場合の登録免許税は、相続による場合と比べて、4倍かかります。不動産取得税も相続を原因とする場合はかかりませんが、生前贈与の場合は通常通り課税されます。
また、相続時精算課税制度や居住用不動産贈与の配偶者控除、贈与税の非課税制度(住宅取得資金の贈与等)を利用する場合も、不動産の名義を変更する場合は上記費用がかかります。仮に自分で手続きをする場合であっても、登録免許税などの税金は支払う必要があります。
さらに、相続時精算課税制度や居住用不動産の配偶者控除、贈与税の非課税制度を利用するには、その旨の税務申告が必要となります。自分で行う場合は必要書類の取得費用だけで済みますが、税理士などの専門家に依頼する場合はその費用もかかります。
なお、単に現金を暦年贈与(毎年110万円以内で贈与)する場合は、そのような手続費用は不要です。
②相続開始から3年以内の贈与は相続税の対象となる
被相続人から相続人に対し、相続開始から3年以内になされた贈与は、相続税の課税対象となります。
賢く生前贈与を活用するポイント
非課税制度をフル活用する
生前贈与には、さまざまな非課税制度があります。これらを上手に活用することで、贈与税の負担を大幅に減らすことができます。
-
暦年贈与の基礎控除(年間110万円): 贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。この範囲内であれば贈与税はかかりません。長期間にわたって少しずつ贈与することで、贈与税をかけずに財産を移転できます。
-
教育資金の一括贈与: 30歳未満の子や孫に対し、教育資金として一括で贈与する場合、最大1,500万円まで非課税となります。
-
結婚・子育て資金の一括贈与: 20歳以上50歳未満の子や孫に対し、結婚・子育て資金として一括で贈与する場合、最大1,000万円まで非課税となります。
-
住宅取得等資金の贈与: 住宅の購入や増改築のための資金として贈与する場合、一定の金額まで非課税となります。
「相続時精算課税制度」の活用も検討する
この制度は、2,500万円までの贈与について、贈与税を非課税とし、贈与者が亡くなった時に、その贈与額を相続財産に加算して相続税を計算する制度です。
-
メリット: 2,500万円という大きな枠で非課税贈与ができるため、一度にまとまった財産を移転できます。
-
デメリット: 一度この制度を選択すると、暦年贈与に戻すことはできません。また、贈与時の財産の評価額が相続時の評価額になるため、将来値上がりする財産には不向きな場合があります。
まとめ
「贈与」と「相続」、どちらがお得かは、一概には言えません。ご自身の財産状況、家族構成、将来設計などを総合的に考慮して判断する必要があります。生前贈与を賢く活用すれば、相続税の負担を軽減し、円満な財産承継を実現できます。しかし、安易に行うと後悔することもあります。この記事で紹介したポイントを参考に、後悔しないための計画を立てていきましょう。