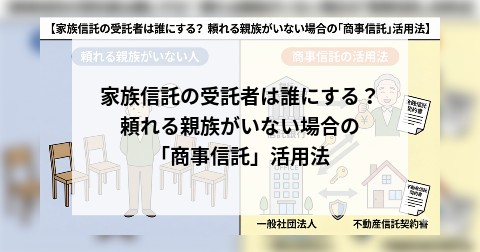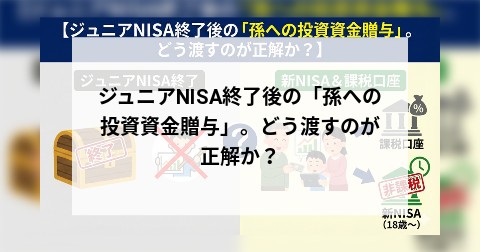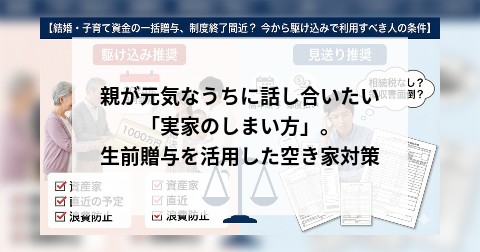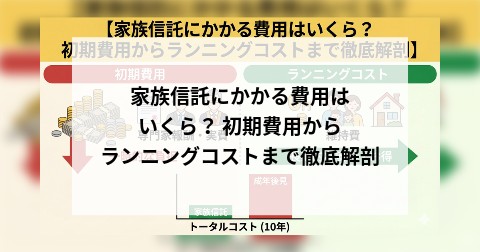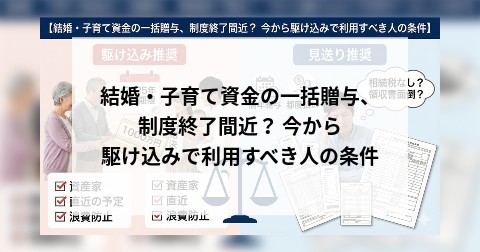シニア世代が陥りがちな相続トラブルとその回避策
高齢化社会が進む日本において、シニア層の相続問題はますます重要なテーマとなっています。
「遺産分割のトラブル」「相続税の負担」「介護リスク」など、老後に潜む落とし穴を避けるために、今から考えうる相続トラブルについて検討をはじめておいたほうが安心できますよね。
そこで今回は、シニア世代向けに相続トラブルや相続対策について解説します。

よくある相続トラブル
相続財産の取り分について意見が食い違う
遺産分割の争いは相続財産の額にかかわらず発生しており、遺産分割に関する調停・審判申立ては、近年増加傾向にあります。
相続には「法定相続分」というものがあり、その割合は相続人の数やケースによって異なります。
遺産分割を行う際に相続人全員が「法定相続分で良い」と納得すれば良いですが、相続人のひとりが被相続人の介護をしていた、同居していたなどの場合には、話し合いに決着がつかない可能性も考えられます。
相続財産の大半が不動産
預貯金や現金のように細かく分割できない不動産を複数名の相続人で相続する場合には注意が必要です。不動産を分割する方法としては、以下の3つが挙げられます。
代償分割
相続人のひとりが不動産を相続し、他の相続人に代償金を支払う方法。不動産の価値によって代償金の額は変動します。
換価分割
不動産の名義変更を行った後で売却・現金化し、その金銭を相続人で均等分割する方法
共有
不動産を複数名の相続人の共有名義で相続する方法
面識がない・連絡のとれない相続人がいる
相続人に該当する方は遺産を承継する権利を有しているため、面識がなかろうが連絡がとれなかろうが相続人である以上、遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。
遺産分割協議において合意に至った内容は「遺産分割協議書」という書類を作成し、とりまとめることになりますが、協議書には相続人全員の署名・押印と印鑑登録証明書が必要です。面識がなかったり遠方に住んでいたりする相続人がいる場合には、メールや電話、手紙などの連絡手段を用いて参加してもらうのもひとつの方法だといえるでしょう。
生前贈与が行われたケース
生前贈与が行われた場合も、遺産相続で揉めることがあります。高額な生前贈与を受けた方がいる場合は相続人の間で公平さを保つため、遺産分割の際に特別受益分を計算に入れて分配することになります。このことを「特別受益の持ち戻し」といいます。
しかし、贈与を受けた相続人が「贈与されていない」もしくは「特別受益の持ち戻し計算は免除されている」などと主張するトラブルもあります。
相続トラブル防止のための具体策
家族間での話し合いの場の設定
相続に関する意見の食い違いを解消するためには、家族全員で話し合いの場を設けることが重要です。
遺産を誰にどのように相続させたいかという被相続人の思いや相続人の言い分を伝え合って調整を全員が納得できる相続のかたちを決めておき、将来相続が発生した際に、これを尊重して遺産の分け方を決めることで、相続争いになる可能性を減らすことが期待できます。
ただし、被相続人の生前に遺産分割をすることはできないため、法的な拘束力まではありません。
遺言書の作成
遺言書は、相続トラブルを防ぐための強力なツールです。法的に有効な形式で作成し、自分の意思を明確に伝えることができます。
遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つが主流です。
自筆証書遺言は、誰にも見せずに自分で簡単に作成でき、費用がかからないというメリットがあります。
しかし、家庭裁判所の検認が必要なこと、内容や方式の不備で無効になる、紛失・偽造・改ざんのリスクがあるなどのデメリットがあります。
公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要、方式不備で無効になる心配が少ない、紛失・改ざんのリスクが少ないなどのメリットがあります。
財産が多い場合や相続トラブルを防ぎたい場合は、公正証書遺言の方をおすすめします。
信頼できる家族との間で信託契約書を作成する(家族信託)
家族信託とは、信頼できる家族や親族などと信託契約をして財産管理を任せる仕組みです。家族信託では、遺言書と同様に、自分が亡くなった際の財産の承継先を決めておくことができます。
さらに、遺言書と異なって、家族信託では自分の死後、配偶者が亡くなったときの二次相続での財産の承継先を決めておくこともできます。たとえば、自宅不動産を自分が亡くなった際(一次相続)は妻に、妻が亡くなった際(二次相続)は長男に承継させることができます。
まとめ
60代は相続対策を始める最適な時期です。健康で判断力があるうちに、財産の把握や整理を進め、家族とのコミュニケーションを図ることができます。
トラブルを避け、遺産分割協議をスムーズに進めるためには、専門家に相談することをおすすめします。専門家を多く抱える事務所では、無料相談を行っているところもありますので、遺産相続に悩んだ際には利用してみましょう。