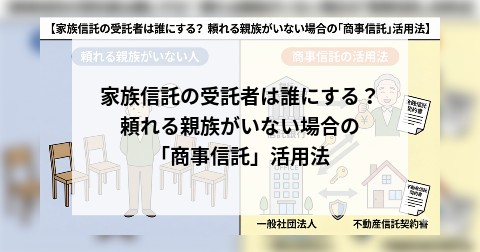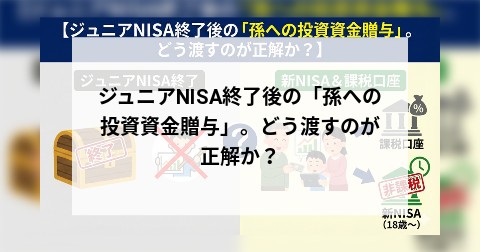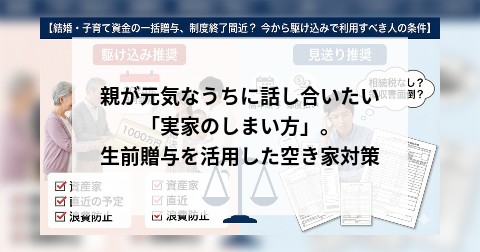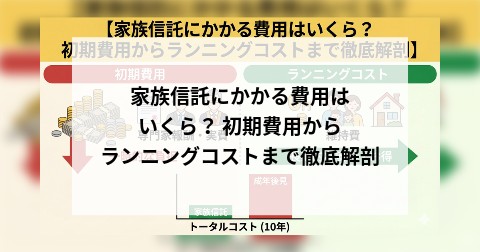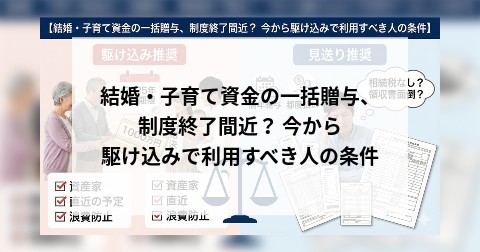介護費用、認知症リスクから資産を守る!「家族信託」という選択肢
高齢者が財産管理を家族らに託す「家族信託」の活用が増えています。将来の介護や認知症、相続のことを考えると、財産管理の問題は避けて通れません。
今回は親の介護費用や認知症のリスクに備えた家族信託について解説します。
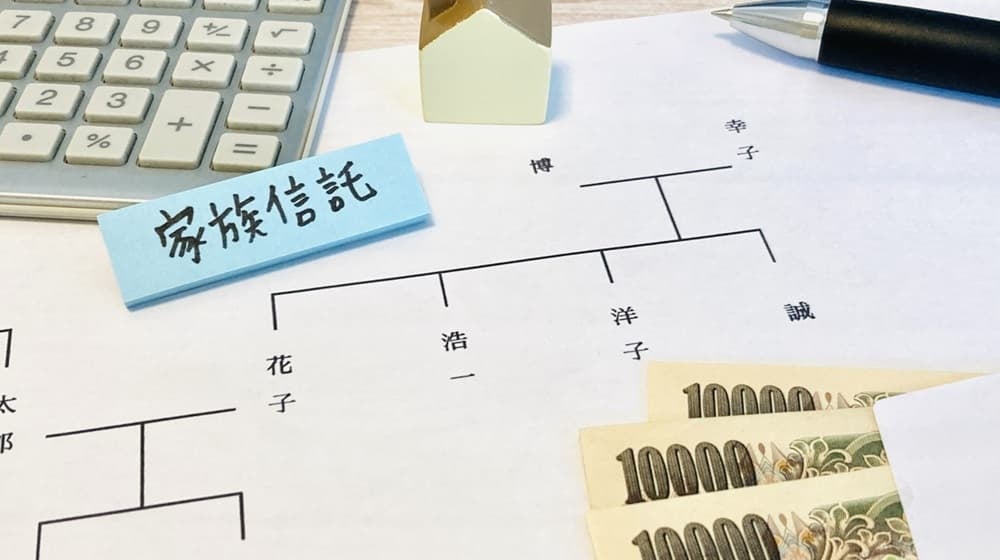
認知症のリスク
認知症になり、自分の意思を外部に伝える能力が低下したり失われたりすると、その人は、自分の財産の管理や処分が自分でできなくなります。具体的には、銀行口座からお金をおろしたり、所有している不動産を賃貸したり、売却したりできなくなるということです。
では、親が認知症になった場合にその子供が親の代わりに親の銀行口座からお金を引き出したり、親名義の不動産を売却したりできるでしょうか。
認知症の親名義の財産を子どもが代わりに管理するのは、原則として認められていません。たとえ親の入院費用など、親自身が必要な資金を用立てるためであっても、子供が親の銀行口座からお金を引き出すことはできないのです。財産管理ができるのは、「その財産の所有者だけ」であることを理解しておきましょう。
介護費用はどれくらい?
家族や親族が高齢になると介護を意識し始める人は少なくありません。そして、将来自分も介護が必要になるときが来るかもしれないと思うと、介護費用が心配になるのではないでしょうか。
生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」によると、過去3年間に介護経験がある人に、どのくらい介護費用がかかったのかを聞いたところ、介護に要した費用(公的介護保険サービスの自己負担費用を含む)は、住宅改造や介護用ベッドの購入費など一時的な費用の合計が平均47.2万円、月々の費用が平均9.0万円となっています。
また、介護を行った場所別に介護費用(月額)をみると、在宅が平均5.3万円、施設が平均13.8万円となっています。
介護期間は?
介護を行った期間(現在介護を行っている人は、介護を始めてからの経過期間)は、平均55.0カ月(4年7カ月)になりました。4年を超えて介護した人は約4割となっています。
家族信託とは?
家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理を任せる制度です。認知症などで意思能力・判断能力が低下すると、預金口座は凍結され、不動産関連の契約もできなくなってしまいます。親がまだ元気なうちに、家族信託で財産の管理・運用・処分を子どもに任せることで、老後に備えることが可能になります。また、家族に財産を託す制度なので、費用は契約時の公正証書作成費などだけで済み、維持費はかかりません。
家族信託の仕組み
家族信託では、財産を信託する人を「委託者」、任される人を「受託者」、財産からの利益を得る人を「受益者」と呼びます。委託者から任された預貯金や不動産を、受託者は委託者の希望に沿って管理・運用・処分し、利益は受益者が得ます。多くの場合、委託者と受益者は親、受託者は子どもとなります。
既に認知症でも家族信託ができる?
認知症を発症して判断能力が失われている場合、基本的に家族信託の契約はできません。
2020年4月1日に施行された改正民法第3条の2で定められた通り、家族信託の契約時には、契約者が判断能力を有しているかどうかが問われます。
以下の条件を満たす場合、十分な判断能力があるものとみなされるでしょう。
認知症が軽度の場合
認知症が軽度の状態であれば、家族信託を利用できる可能性があります。
MCIと呼ばれる軽度認知障害の場合、日常生活への影響が少なく、判断能力にも問題がないため、認知症とは診断されません。
軽度認知障害は物忘れの自覚があるものの、判断能力の低下には至っておらず、いわゆる「認知症予備軍」といわれる状態です。
公証人の質問に答えられる場合
家族信託を利用する場合、信託契約書を公正証書にするケースが一般的です。
公正証書を作成する際、委託者となる人が公証人の質問にはっきりと答えられるようであれば、家族信託契約を締結できる可能性があります。
公証人の質問は主に家族信託契約に関わるものなので、委託者の立場や受託者の役割、信託する財産や、信託の効果などを理解している必要があるでしょう。
高齢者の財産管理を支援するほかの制度
成年後見制度
成年後見制度は認知症の高齢者などの財産管理や契約行為を支援する制度です。家族信託は財産管理の制度のため、介護施設の入居契約などの身上監護はできません。身上監護をするには成年後見制度を利用する必要があります。
支援を担当する成年後見人は家庭裁判所によって選任されます。そのため、家族が選ばれるとは限らず、多くの場合に司法書士や弁護士などの専門家が選任されます。家族信託と成年後見制度の主な違いは、以下を参照してください。
| 家族信託 | 成年後見人制度 | |
| 財産を管理する人 | 受託者 | 成年後見人 |
| 財産管理を始める時期 | 家族信託契約の締結時 | 成年後見人の選任時 |
| 監督機関 | 特になし | 家庭裁判所 |
| 初期費用 | 公正証書作成費用など | 専門家への相談費用:10万〜20万円 |
| 月々の費用 | 一般的に費用はかからない |
成年後見人が家族の場合:0〜5万円/月 |
日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業は、全国の社会福祉協議会が実施している事業です。社会福祉協議会の専門員や生活支援員が、日々の生活に使うお金の出入金や通帳の預かりなどを支援します。金銭の管理だけでなく、福祉サービスの利用手続きなどの幅広い支援が受けられます。一人暮らしの高齢者だけでなく、福祉施設や病院に入っている人も利用可能です。
まとめ
認知症などで判断能力が低下した場合、通常は資産凍結されてしまいますが、成年後見制度や家族信託の手続きを行っておけば資産凍結されずスムーズな資産管理が可能です。
成年後見制度、家族信託どちらにもメリット・デメリットがあり、一概にどちらが優れているとはいえません。
専門家と一緒にニーズを整理しながら自分達にあった使い方を検討できると安心です。