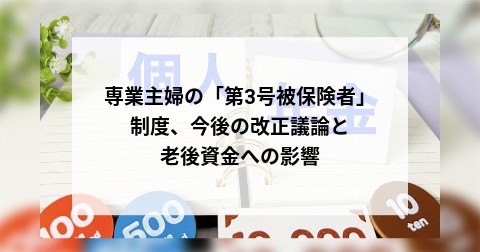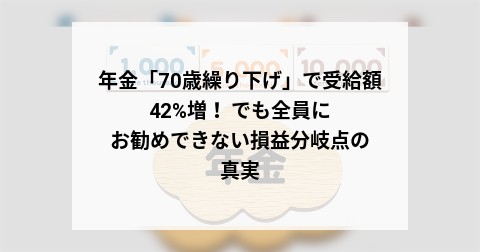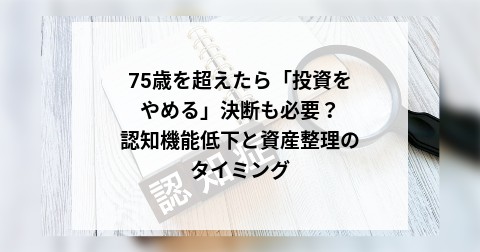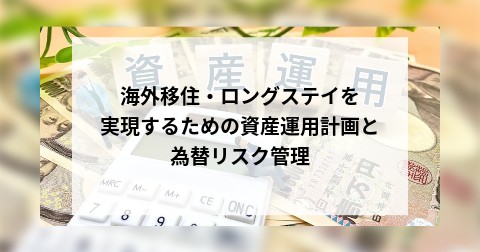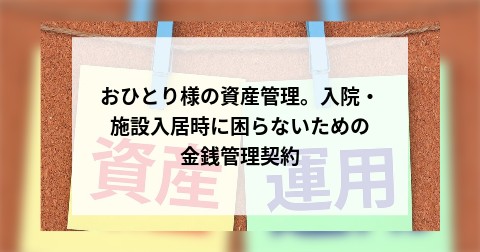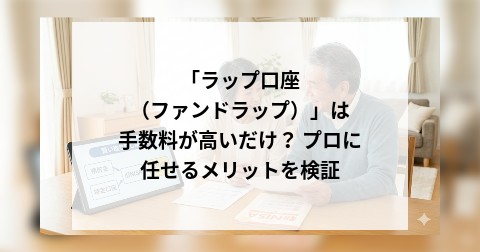インフレに負けない!預貯金だけではもったいないシニアのお金の守り方
「老後の備えは預貯金で十分」と考えていませんか?
しかし、日本は近年、物価が継続的に上昇する「インフレ」の時代に入りつつあります。せっかく貯めたお金も、インフレによって実質的な価値が目減りしてしまう可能性があります。
例えば、銀行に100万円預けていても、物価が年率2%上がれば、1年後には同じ100万円で買えるものが少なくなってしまいます。つまり、お金の価値が下がってしまうのです。
ここでは、預貯金だけでなく、インフレに負けないための資産の守り方をご紹介します。

現状の資産を把握する
現状の財産と収入の正確な把握は、適切な管理の第一歩となります。金融機関での取引履歴や通帳を確認し、年金の受給額や支払い状況の整理から始めましょう。
不動産や保険契約の有無、株式などの金融商品についても確認が必要です。必要書類を整理し、資産状況を一覧にまとめておくと、今後の管理がスムーズになります。
金融機関からの通知や税金関係の書類なども重要な情報源となるため、書類の保管場所も確認してください。
収支バランスを把握すれば、将来の生活設計や介護に備えた資金計画も立てやすくなるでしょう。
老後の長い生活期間では、インフレによって生活費が増加する可能性があり、対抗するにはインフレに強い資産運用が重要になります。
株式や不動産など価値が上がる可能性のある資産に投資し、将来のリスクへの備えが老後資金を守るポイントです。
資産運用で失敗しないポイント
資産運用の目的をはっきりさせる
目的が不明確だとリスク管理が難しくなり、無駄な損失を招く可能性があります。
たとえば、資産運用の目的が「退職後に安定した収入を得る」であれば、比較的リスクの低い運用方法を選ぶべきです。
一方、「資産を大幅に増やしてリタイア後に贅沢な生活を送りたい」という目的であれば、多少のリスクを覚悟して高リターンを狙う運用方法の選択が必要です。
目的を明確にすると、投資対象や投資期間、リスク許容度を適切に設定できます。運用を始めた後も目的を定期的に見直し、状況に応じて運用方針の修正が大切です。
貯蓄を全額投資しない
資産運用において、全ての貯蓄を投資に回すのは止めましょう。
投資には常にリスクが伴うため、万が一のときのために生活費や緊急時の資金を別に確保しておくことが不可欠です。
老後の医療費や介護費用など、急に大きな支出が必要になるケースは少なくありません。全額を投資に回してしまっていると、必要なときに現金が不足してしまいます。
投資には余裕資金を使い、生活費や予備資金は安全な場所への保管が必要です。
投資先を複数つくる
資産運用のリスクを減らすには、投資先の分散が非常に重要です。
1つの投資先に集中すると運用が成功した場合に大きなリターンを得られる反面、失敗した場合のリスクが非常に高いです。
株式や債券、不動産、投資信託など、異なる資産に分散投資をおこなうと、一方の資産が低迷した場合でも、別の資産でカバーできる可能性が高まります。
長期間で投資する
長期投資であれば、時間をかけて市場の成長の恩恵を受けられ、安定したリターンを期待できます。
株式市場は短期的には大きな変動がありますが、長期的には成長を続けてきた歴史があります。
長期投資をおこなうと、市場の一時的な低迷を気にせずに資産の成長を見られるでしょう。
長期間の投資は複利効果も受けられるため、時間が経つにつれてリターンが大きくなる傾向があります。資産運用を成功させるためには、焦らずに長期間での計画が重要です。
シニアにおすすめの資産運用
老後資金を効果的に運用するには、自分にあった投資方法の選択が大切です。
ここからは、リスクとリターンのバランスを考慮した、オススメの資産運用方法を紹介します。
各方法の特徴を理解し、自分の目的やリスク許容度にあった運用プランを立てる参考にしてください。
投資信託
投資信託は、多くの投資家から資金を集め、専門家がその資金を運用する商品です。
以下のようなメリットとデメリットがあります。
メリット
- 少額から始められる
- プロが運用をしている
- 分散投資が容易である
デメリット
- 運用管理費用(信託報酬)がかかる
- 元本保証がない
初心者でも簡単に分散投資ができ、リスクを分散しながら資産を増やすことが可能です。
少額から投資を始められるため、これから資産運用を始める方にも適しています。
インデックスファンドと呼ばれる市場全体に連動する投資信託は、手数料が低く、長期的に安定したリターンを期待できるため、老後資金の運用に向いているでしょう。
投資信託には多くの種類があり、国内外の株式や債券、不動産に投資するものなど、選択肢が豊富です。
自分のリスク許容度や投資目的に応じて、適切な投資信託の選択をしましょう。
個人向け国債
個人向け国債は政府が発行する債券であり、元本保証があるため非常に安全な投資商品とされています。
メリット
- 元本保証がある
- 利率が固定されている(固定金利型の場合)
- 少額から購入可能である
デメリット
- 利回りが比較的低い
- 中途換金時に手数料がかかる
固定金利型と変動金利型の2種類があり、それぞれのメリットやデメリットの理解が大切です。
固定金利型は、購入時に決まった金利が満期まで続くため安定した利回りを確保できます。
変動金利型は市場金利に応じて利率が変わるため、金利上昇時に有利です。
個人向け国債は、安全性を重視したい方や元本割れのリスクを避けたい方にとって、魅力的な商品です。毎月定期的に購入すると、利率の変動リスクも分散できます。
退職金定期預金プラン
退職金定期預金プランは、退職金を一定期間、高い利率で預けられる定期預金です。
以下のようなメリットとデメリットがあります。
メリット
- 通常の定期預金より高金利である
- 元本保証がある
- 手続きが簡単である
デメリット
- 預け入れ期間や金額に制限のある場合が多い
- インフレに対応できない
通常の定期預金よりも利率が高く設定されているため、安全に退職金を運用したい方に適しています。
定期預金であるため、元本割れがない点も魅力です。
退職後定期預金プランは、退職後に大きなリスクを取らずに安定した利息を得られます。
退職金の一部をこのプランに預けると、ほかの資産運用方法と組みあわせてリスク分散ができます。
ただし、利率が固定されているため、インフレによる実質的な価値の減少には注意しなければなりません。
新NISA
新NISA(少額投資非課税制度)は、一定額まで投資で得た利益が非課税となる制度です。
通常、投資で得た利益には税金がかかりますが、新NISAを利用すると税負担を軽減しながら効率的に資産を増やせます。
メリット
- 投資が非課税でできる
- 非課税期間は無期限である
デメリット
- 既存NISA口座との併用ができない
- 投資で損失が出た場合ほかの口座との損益通算ができない
とくに、長期的に資産運用をおこないたい方にとっては、新NISAを活用すると大きなメリットを得られるでしょう。
新NISAは、株式や投資信託を購入する際に利用できるため、リスク分散しながら資産運用が可能です。
年間の非課税枠が設定されているため、その範囲内で投資をします。
まとめ
老後資金を増やすために資産運用は非常に有効な方法ですが、同時に資産防衛のための対策も欠かせません。
運用する際には、リスク管理を徹底し、無理のない範囲での投資が大切です。
投資先の分散や長期的な視点を持つと、リスクを抑えつつ着実に資産を増やせるでしょう。
資産運用と資産防衛のバランスを取ると、安心して老後を迎える準備ができます。