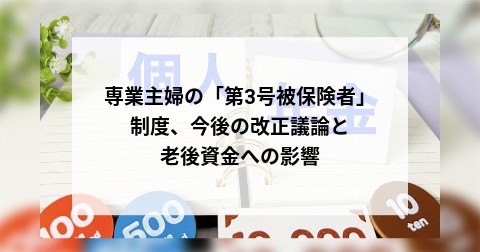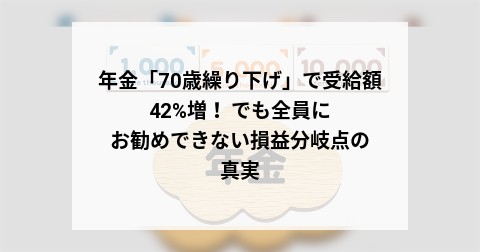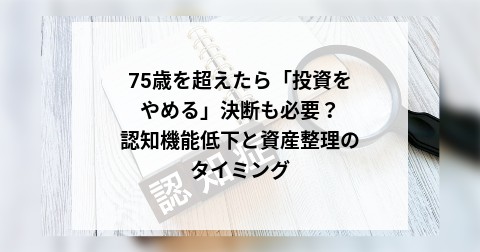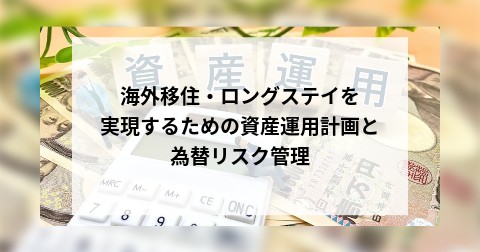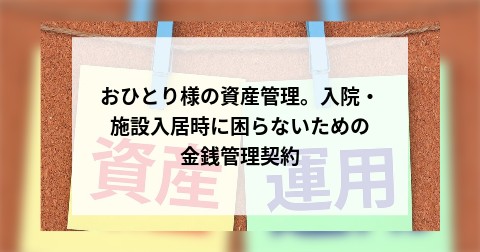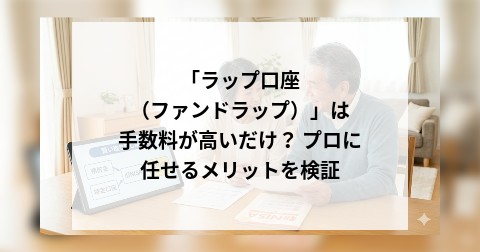【資産管理の基本ステップ】 何から始める?ロードマップを徹底解説
「資産管理を始めたいけど、何から手を付ければいいかわからない」という方は多いのではないでしょうか? 資産管理は、特別なお金持ちだけのものではなく、老後や今後の将来の安心を手に入れるための全ての人に必要な習慣です。
この記事では、資産管理を始めるためのロードマップを、初心者でも迷わないように5つの基本ステップに分けて徹底的に解説します。

資産形成を始める前に整理しておきたい4つのステップ
ステップ1:資産形成のための現状把握
資産管理の第一歩は、自分が今、どれだけの資産を持ち、どれだけの負債があるのかを正確に把握することです。
1. 資産をリストアップする
銀行預金(普通・定期)、株式、投資信託、保険の解約返戻金、不動産など、現金化できるものを全て洗い出します。
2. 負債をリストアップする
住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、クレジットカードのキャッシングなど、返済すべきものを全て洗い出します。
3. 純資産を計算する
資産の合計 − 負債の合計 = 純資産を計算します。 この純資産が、あなたの現在の経済的な基盤となります。この数字を把握することで、「これから何をすべきか」が明確になります。
ステップ2:具体的な目標を設定する
資産形成の前に、最も大切なのが「明確な目標」を持つことです。
周りの人が始めているからと、資産形成を急ぐ必要はありません。まず、自分は何のために資産を作るのか、自分なりの目的を整理しましょう。
自分の年齢から考え、結婚資金のため、出産や子育てのため、マイホーム購入のため、老後の備えのためなど、将来のライフイベントを思い描くと計画が立てやすくなります。そのライフイベントにお金がいくらかかるのか、人生設計とお金を関連づけて考えると、将来のビジョンを明確にしていくことができます。
- 毎月の支出を洗い出す
家賃、食費、光熱費、交際費、娯楽費など、すべての項目に分けて記録します。
- 無駄な支出を削減
毎月の支出の中で「満足度の低い支出」をピックアップして、削減できる支出を見つけます。
- 余剰資金の確保
削減したお金を生活防衛資金として貯蓄して、その後に投資資金とします。
ステップ3:緊急資金の確保と負債の整理で「土台」を固める
具体的な投資を始める前に、必ずやっておくべきことがあります。それが「生活防衛資金の確保」と「負債の整理」です。
1.緊急資金(生活防衛資金)の確保
病気や失業など、もしもの時に備えて、生活費の3ヶ月~6ヶ月分(自営業者なら1年分)を普通預金などすぐに引き出せる形で準備しておきましょう。これが、あなたの生活と資産を守るセーフティネットになります。
2.家計の見直しと負債の整理
貯蓄ができる家計にすることは、資産形成をするための一番大切な要素です。まずは、家計の見直し、不要な支出のコントロール、家計管理の方法の改善、などを行い計画的に貯蓄ができるようにしましょう。
さらに、金利の高い借金(カードローンなど)がある場合は、優先的に返済しましょう。金利の高い借金があると、どんなに運用で増やそうとしても、それ以上に利息で資産が目減りするリスクがあるため、最優先で取り組むべきです。
この土台がしっかりしていれば、不測の事態が起きても、大切な資産運用を途中で止めることなく継続できます。
ステップ4:NISA、iDeCoなど非課税制度を最大限に活用する
土台が整ったら、いよいよ資産運用の準備です。まずは、国が用意した税制優遇制度(NISA、iDeCo)の活用を検討してみるのはいかがでしょうか。
- NISA
投資で得た利益に対する税金(通常20.315%)が非課税になる制度。2024年1月以降、投資できる金額が大きくなる、期間が無制限になるなど、大幅に拡充された。金融庁が定めた基準をクリアした投資信託だけに投資できる「つみたて投資枠」と、株式にも投資できる「成長投資枠」がある。 - 自分で自分の将来の年金を用意するための制度。NISA同様、投資で得た利益に税金がかからなくなるほか、掛金の全額が所得控除の対象になるなど、より大きな税制優遇を受けられる。ただし、原則として60歳までお金を引き出せないという制限がある。
NISAとiDeCo、「どちらを優先すべきか」「どの商品を選ぶべきか」といった疑問を持たれる方もいますが、ご自身のライフプランやリスク許容度に合わせて、最適な活用法を考えることが重要です。
ステップ5:目標に合わせた「資産配分」を決める(運用開始)
- リスク許容度を知る
あなたが「どれくらいの損失まで耐えられるか」を把握します。年齢や家族構成、収入の安定度などによって、取るべきリスクの大きさは変わります。 - 資産配分(アセットアロケーション)を決める
目標達成の期間とリスク許容度に基づき、「どの資産に、どれくらいの割合で投資するか」を決めます。
例:国内株式20%、外国株式40%、債券30%、現金10%など - 少額から積立投資を始める
NISAやつみたてNISAなどの税制優遇制度を最大限活用し、無理のない金額から毎月定額で積立投資を始めます。投資の経験がない方は、まずは低コストのインデックスファンドから始めるのが定石です。
まとめ:資産管理は「成長の習慣」
資産管理は、一度やったら終わりではありません。これは、あなたの人生のフェーズや経済状況の変化に合わせて**見直し、改善していく「成長の習慣」**です。
まずは、今日ご紹介した「ステップ1:現状の把握」から始め、少しずつ自分のペースで資産管理のロードマップを進めていきましょう。
このロードマップを参考に、あなたも安心できる未来に向けた一歩を踏み出してみませんか?