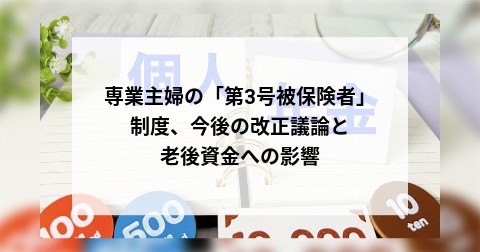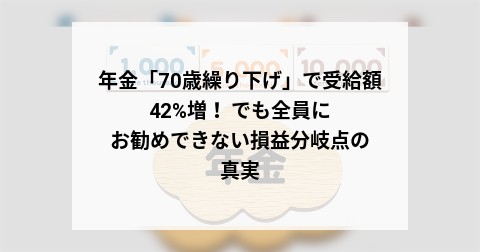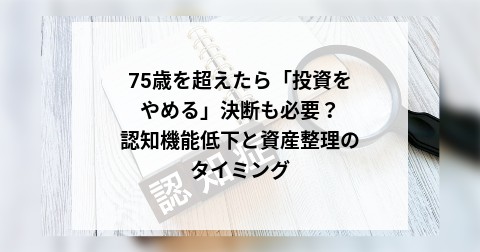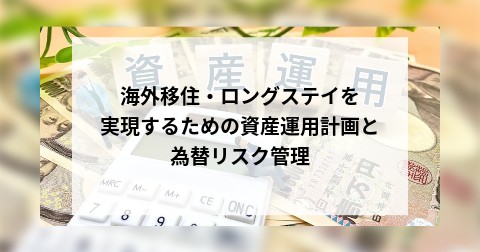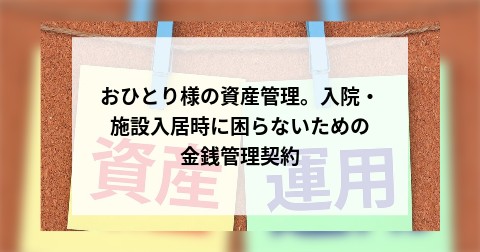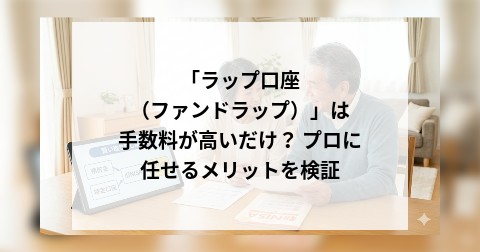あなたの資産、どれくらい把握できてる?資産の「見える化」とリスト作成のコツ
「貯金はあるはずなのに、具体的な総資産額がわからない」「何となく不安」と感じていませんか?
資産管理の第一歩は、自分が持っている全てのお金とモノ、そして負債を正確に把握することです。これを「資産の見える化」といいます。
あなたの経済状況をクリアにし、不安を自信に変えるための「見える化」と「リスト作成のコツ」を解説します。

資産の「見える化」とは?家計版バランスシートを作成しよう
資産の見える化とは、ご自身の財産を会社でいうバランスシート(貸借対照表)のように一覧で把握することです。
資産の合計から負債の合計を差し引いたものが、あなたの純資産、つまり「本当に使える財産」の総額となります。この純資産を把握することが、資産形成の第一歩です。
純資産=資産合計−負債合計
お金の管理のためには、今ある資産をしっかりとリスト化することがおすすめです。使用している預貯金口座、自宅以外の不動産、証券、保険など、保有している資産をすべてリスト化すると、現状の資産を把握できます。
【資産リストの作成項目】
| 種類 | 具体例 | 把握方法 |
| 預貯金 | 普通預金、定期預金、ネット銀行、タンス預金など | 通帳記帳、残高証明書、Web明細で確認 |
| 金融資産 | 株式、投資信託、iDeCo、NISAなど | 取引残高報告書、証券会社のWebサイトで評価額を確認 |
| 保険 | 生命保険、個人年金保険などの解約返戻金 | 保険証券、契約内容のお知らせなどで「解約返戻金」を確認(現時点の価値の目安) |
| 不動産 | 自宅、投資用物件など | 固定資産税課税通知書、不動産登記簿謄本、時価の目安(査定など) |
| その他 | 金、美術品、会員権など換金性のあるもの | 証書などで価値を確認 |
【負債リストの作成項目】
| 種類 | 具体例 | 把握方法 |
| 住宅ローン | 住宅購入のためのローン | 金融機関の残高証明書、返済予定表で残高を確認 |
| その他ローン | 自動車ローン、教育ローンなど | 金融機関の残高証明書、返済予定表で残高を確認 |
| 未払い金 | クレジットカードの未払い残高(リボ払い含む)、未払いの税金など | カード会社のWeb明細、支払い通知で確認 |
資産リスト作成のコツ:挫折しないためのコツ
資産リストの作成は「大変そう」と感じるかもしれませんが、以下のコツを押さえればスムーズに進められます。
1: プラスの財産とマイナスの財産に分ける
資産リスト作成のコツは、プラスの財産とマイナスの財産を分け、漏れなく詳細にリスト化することです。預貯金、不動産、保険、株式などの具体的な金融資産・負債を金融機関名や口座番号、所在地などの詳細情報とともに記載し、証拠資料を添付すると正確性が高まります。また、リスト作成の目的(相続対策、財産分与、家計管理など)を明確にし、目的達成のために必要な情報項目を洗い出すことも重要です。
2: 「どこに」「何が」「どれくらい」あるか詳細に記載する
- 金融資産: 銀行名、支店名、口座種別、口座番号、残高まで正確に記入します。通帳のないネット銀行や、同じ金融機関で複数の口座がある場合もあるため、残高証明書で確認し、漏れがないようにしましょう。
- 不動産: 不動産の種別、用途、所在地、面積、評価額、権利関係(共有者など)を記載します。登記事項証明書などを参考に正確な情報を把握し、登記内容の不備は直しておきましょう。
- その他: 株式の証券会社名、保険の契約内容、有価証券の証券区分、自動車の車種、ナンバープレート番号、貴金属の品名などを細かく記載します。
3: 証拠資料を添付する
通帳の写し、保険証券、契約書、登記簿謄本など、各資産・負債の証拠資料を添付することで、リストの信頼性が高まります。
4: 目的を明確にして必要な項目を洗い出す
資産リストを作成する目的を明確にすることで、記載すべき項目や詳細度が決まります。例えば、相続対策では遺産分割が公平になるように、家計管理なら純資産の把握ができるように作成するなど、目的に応じて項目を調整しましょう。
5: 使っていない資産や負債は整理・解約を検討する
使っていない預金口座やクレジットカード、不要なローンなど、管理の手間やコストがかかるものは、この機会に見直して解約することも、財産をシンプルにするコツです。
リストアップした資産を分類しよう
リストアップした今ある資産の中から、どこに使うのか、目的別に分けていきましょう。
使って良いお金、残しておきたいお金を把握すると、金銭を契約的に管理できます。
生活費に使用するお金
毎月の食費や医療費など、生活費に必要なお金です。特に長生きした場合を想定して、年間の使用額を決めたうえで100歳までのお金を計画しておきましょう。
たとえば、現在60歳であれば100歳までどれくらい年間の生活費が必要なのか計算したうえで、赤字になりそうであれば、今の資産が目減りしない運用方法を検討するなど、老後の経済破綻につながらないよう早めに準備することがコツです。
将来の医療や介護に備えるためのお金
現在は健康に問題がなくとも、将来的に病気やケガのリスクはあります。
その際の医療や介護にそなえて、100~300万円程度を残しておくと、急な出費が続いてもある程度対応可能です。
将来老人ホームや高齢者向け住宅へ移住する予定であれば、入居にかかる費用も今ある資産でまかなえそうか、計算しておくと安心です。
住宅リフォーム・車の買い替えなどの生活費以外のお金
毎月の生活費以外で、大きな出費に備えておくためのお金です。具体的には住宅のメンテナンス、リフォームに、車の買い替えといった大きな買い物です。
ほかにも、旅行や趣味に使いたい娯楽費なども、生活費以外で用意しておくと、老後の生活をさらに豊かにしていけることでしょう。
住宅や車にまつわる費用は、何年後どれくらいかある程度見積もっておいて、合計額を出すことをおすすめします。
遺族に渡したい資産
将来的に残った遺産を、誰にどの資産を渡したいのかを考えておきましょう。
また、不動産については現金化しにくかったり、複数の相続人がいる場合は分けるのに難しく争いに発展してしまう事も多いのが現実です。すでに持っている資産全体を把握して、どれくらい価値があるのか計算することもおすすめです。
ちなみに遺産額が相続税の基礎控除を上回るようであれば、税金対策の検討が必要です。
資産をリスト化することが、老後の生活の安定やスムーズな相続につながっていくのです。
まとめ
資産をリストアップすることで、どのような葬儀を執り行いたいか、お墓を建てられるかなど、より具体的な内容を考えるきっかけとなります。そして認知症や介護になってしまった時、施設に入所する際にも役に立ちます。
お金の終活は、老後の生活を不安なくより佳く生きるためにも、目に見える形で資産を把握して管理しやすくしておくことが大切です。