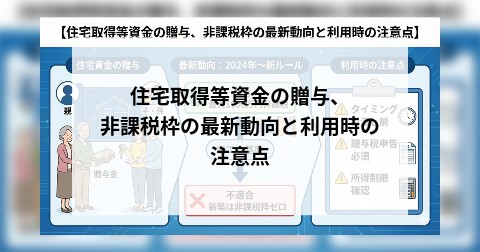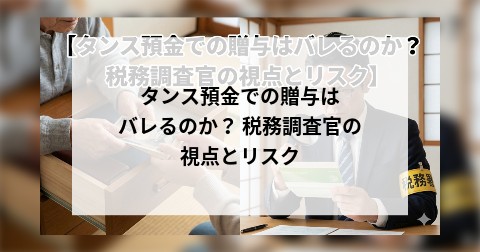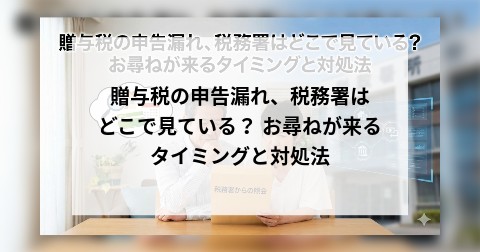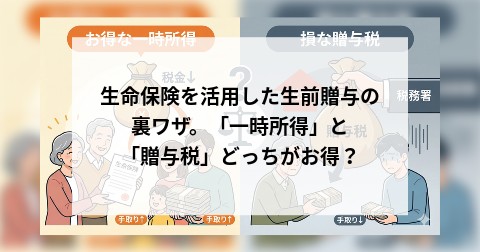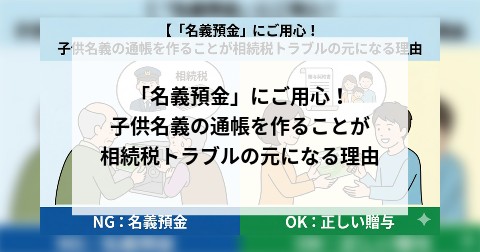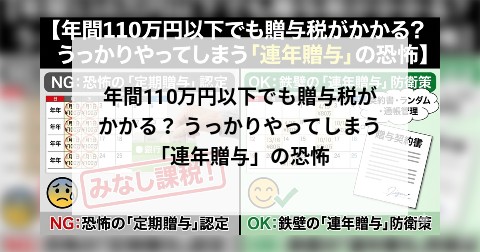遺産相続の基本から税金の仕組みまで詳しく解説!事前に知っておくべき対策と注意点

そもそも遺産相続とは?
遺産相続には「法定相続」と「遺言相続」がある
遺産相続とは、ある人が死亡した際に、その人の所有していた資産や財産をその家族や親族などが引き継ぐことをいいます。相続には法律に基づいて行われるものと、遺言によって行われるものがあります。
簡単に、遺言がない場合に適用される相続方法が「法定相続」で、親族の順位に基づいて相続人が決定されます。死亡者が遺言書を残していて、その内容に従って相続が行われる場合は「遺言相続」になります。
遺産相続の基本の流れ
- 死亡の確認
- 遺言の確認
- 法定相続
- 相続税の計算
- 財産の分割
まず最初に、被相続人(財産の元の所有者)が死亡したことが確認されます。次に遺言が残されているかどうかを調べ、遺言があればその内容に従って相続が行われます。遺言がない場合や遺言が不完全な場合には、法定相続が適用されます。
法定相続の場合では、親族の順位に基づいて相続人が決定され、遺言相続や法定相続に問わず、相続財産の内容によっては、相続税が課されることがあります。相続人が複数いる場合、遺産は相続人の間で分割されます。
「単純承認」と「限定承認」と「相続放棄」の違い
実情では故人の財産状況を知らないケースは多々存在します。何も知らずに相続した場合、相続人に不利益になることがあるので、それを回避できる手段を民法が規定しています。
遺産相続する場合に、相続人が被相続人(財産の元の所有者)の全ての権利義務を無限定に承継する「単純承認」と、相続人が得た財産の範囲内でしか債務を弁済しないことを条件に相続を承認する「限定承認」を民法に基づいて行うことができます。
単純承認は、相続人が被相続人の財産や債務を全て引き継げて、手続きも簡単ですが、債務まで全て継承するリスクがあります。
限定承認は相続人全員の合意が必要であったり、家庭裁判所への申請手続きがありますが、相続財産の限度を超えて債務を弁済する義務がないので、負債リスクが軽減できます。ですが、遺産相続できる財産よりも負債や借金が多い場合は、限定承認でも相続人の負担が大きくなります。
そのため、プラスの財産もマイナスの債務も全く引き継がない「相続放棄」という制度が用意されています。限定承認と同様に家庭裁判所への申請が必要ですが、相続人一人でも手続きが可能なので、相続自体に関与したくない方や、負債を引き継ぎたくない場合に知っておくべき制度になります。
遺産相続で必要な行政への手続きや工程
ー 遺産相続の詳細な手続きの流れ ー
- 死亡届の提出
- 世帯主変更届の提出
- 遺言書の有無の確認
- 相続人の確定
- 相続財産の確定
- 相続方法の決定(単純承認・限定7]承認・相続放棄)
- 遺産分割協議
- 相続財産の名義変更
- 所得税の準確定申告
- 相続税の申告と納付
- 相続登記
遺産相続が発生した瞬間から、様々な手続きや工程が必要になります。まず被相続人(財産の元の所有者)死亡届の提出が必要で、死亡から7日以内に死亡届を役場に提出します。そして、死亡から14日以内に世帯主変更届を自治体に提出します。遺言書があれば家庭裁判所で検認手続きをします。さらに戸籍謄本などを用いて相続人を確定しつつ、相続財産を確認し、通帳や不動産などを調査していきます。
死亡日、または相続開始を知った日から3ヶ月以内に単純承認・限定承認・相続放棄を相続人は検討することになります。相続を継承し遺産分割する場合は、相続人全員で遺産を分割する方法を話し合い、協議書を作成します。その際に相続財産の名義変更の手続きとして、預貯金や不動産などの名義を相続人に変えていきます。
死亡日から4ヶ月以内に準確定申告を行います。相続の開始を知った日から10ヶ月以内に相続税を申告・納付し、相続登記する場合、遺産分割が成立した日から3年以内に行う必要があります。
遺産相続にかかる税金
遺産相続は「相続税」として税金を納める必要があります。相続税は、被相続人の財産を相続する際に発生する税金で、相続税の税率は10%から55%まで変動します。
一方で、相続税にも税金の負担軽減ができる「基礎控除」があり、非課税財産や債務を全て差し引いた遺産額から、基礎控除額(3,000万円 + 法定相続人1人につき600万円)を差し引けるため、相続人の人数が多いほど、税金の負担が軽くできるようになっています。
また、故人の配偶者の負担を減らす措置として、相続税の配偶者控除という制度があり、1億6,000万円、または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかからない仕組みがあります。
内縁関係は対象外であったり、 相続税の申告期限までに遺産分割が完了しているなどの条件がありますが、配偶者が相続した財産に対して、一定の範囲内で相続税が非課税となる制度なので、対象の人は必ず確認しておきましょう。
遺産相続の手続きで見落としがちな注意点
遺言書が財産分割後に見つかった場合
まず、遺言書の検認(遺言書の有効性を確認するための手続き)が必要になるため、家庭裁判所への提出が必要になります。並行して他の相続人への連絡が必要になるため、遺言書が見つかったことを全ての相続人に通知し、遺言書の内容の確認をしていきます。
既に財産の分割を行われている状態ですが、遺言書が有効であれば、既存の遺産分割は無効となる可能性があります。特に、遺言で特定の財産が指定されている場合には、その財産については遺言の内容が優先されます。
一般的に既に行われた遺産分割をやり直すかについては、相続人の間で協議するケースが多いですが、遺産相続をやり直す場合は、新たな遺産分割協議書を作成し、全員の署名と捺印をしていきます。相続税の再申告が必要な場合があるときは、修正申告書、相続税納付書などの用意に加えて、相続税の法定申告期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)から5年以内に行う必要があるので、手続きの期限に注意しましょう。
著作権や死亡直前に出金したお金はどうなる?
相続財産の範囲として創作物に対する著作権は相続対象になり、経済的価値があれば相続税の対象として扱われるため、注意が必要です。また、名義預金に関して親が子ども名義で預金口座を作っていた場合、その預金は相続税の課税対象になります。
死亡直前に出金した預金も相続税の対象となる可能性があるので、親から子へお金を継承する場合は、事前に進めておくことが減税対策につながります。生前贈与する場合、それがどのように評価されるか確認し、相続人の間で不公平感を生まないようにすることも重要でしょう。
疎遠な相続人がいる時は?
遺産分割協議は法定相続人全員が参加しなければ無効です。そのため、戸籍謄本などを活用して相続人の範囲を明確にすることが必要です。疎遠な相続人がいる場合、遺産分割協議が難しくなることがあるので、手紙や電話などで意思確認をし、協議書に署名捺印してもらいましょう。直接会わずに遺産相続を進められるケースがあります。
遺産相続でもめないために
遺産相続で親族とトラブルが発生しないためにも、生前から話し合いを進めることが大事です。被相続人(財産の元の所有者)の生前から、法定相続人全員で遺産相続に関する話し合いを進めておくことで、遺産相続の手続きや話し合いが円滑に進みます。特に分割のトラブルになる不動産や事業の継承者、生前贈与、介護負担に関する寄与分などは家族間で事前に話し合うことが大切です。
また遺言書の作成は、被相続人の意思を反映し、法定相続人間での争いを未然に防ぐ効果があります。遺言はビデオや録音は無効で書面で作成する必要があったり、日付と氏名を記載して押印する必要があったりと、一定のルールが存在するため、遺言書が無効にならないように専門家からのアドバイスを受けるのも良いでしょう。