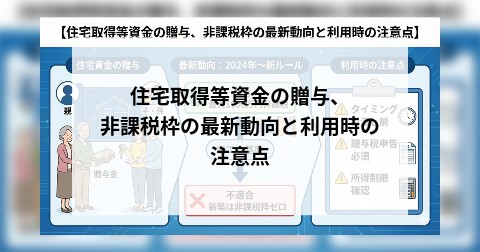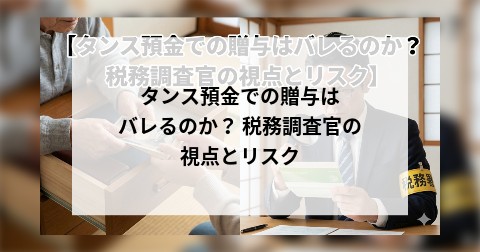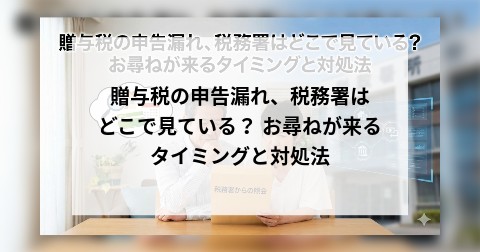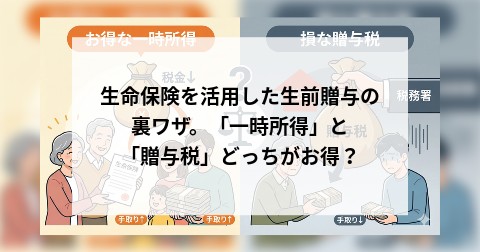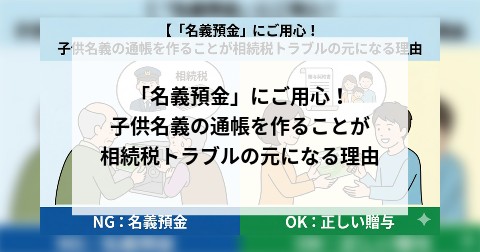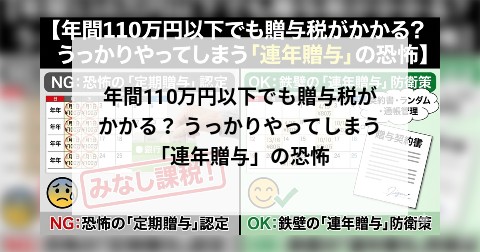贈与税いくらからかかる?親子間での贈与で損をしないやり方法とは?
血縁関係のあるなしにかかわらず、個人が個人へと無償で財産を与えることを財産を人にあげることを、贈与といいます。もちろん親から子へ、祖父母から孫へと生前に財産を少しずつでも渡すことも贈与になり、贈与額によっては、受けとった側が「贈与税」を支払わなければならなくなります。
贈与税は相続税と並んで税率が高いといわれており、贈与税のことを知らずに多額の財産を贈与してしまうと、思わぬ税負担に直面しかねません。
本記事では、親子間での贈与税がかかるケースや非課税にする方法について解説します。

|
■この記事を要約すると ・親子間でも贈与税がかかる場合とかからない場合がある ・教育資金や住宅取得資金の特例で税負担を軽減可能 ・無申告や延滞で重い加算税が科されるリスクがある |
贈与税には、親や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子どもや孫に贈与する「特例贈与財産」と、それ以外の人に贈与する「一般贈与財産」の2種類があります。
贈与を受ける人の年齢は、令和4年3月31日以前の贈与については20歳、それ以後は18歳以上で、年齢が該当するかどうかは、贈与を受けた年の1月1日時点の受贈者の年齢で判断されます。
| 項目 | 特例贈与財産 | 一般贈与財産 |
| 贈与者 | 直系尊属(父母、祖父母など) | 直系尊属以外(兄弟姉妹、配偶者、叔父叔母など) |
| 受贈者 | 直系卑属で、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上 | 直系卑属で、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上以外、もしくは、直系卑属でも18歳未満の場合 |
| 税率 | 特例税率(一般税率より低い) | 一般税率(特例税率より高い) |
| 贈与時期 | 2015年1月1日以後の贈与 | 特に制限なし |
| 主な目的 | 親から子、祖父母から孫への財産移転の促進 | 特に目的は限定されない |
親子間でも贈与税がかかるもの
贈与されたお金を教育費・生活費以外に使った場合
扶養義務者からその都度渡される教育費や生活費は原則として非課税ですが、趣味に関する買い物や投資、不動産の購入など他の目的で使用したり、預金に充てたりした場合は課税対象となります。
また、教育費や生活費はその都度渡す性格のお金なので、一括して送金すると贈与とみなされます。
親が生命保険の保険料を負担した場合
保険料の負担者である親が生きている間に、満期や解約、被保険者の死亡で子どもが受け取った生命保険金も贈与税がかかります。
借金の肩代わりをした場合
「借金を背負った子供がかわいそう」と、借金を肩代わりをする親もいるかもしれません。ですが、親が子どもに代わって借金を支払った場合も贈与となるので注意が必要です。
自分が払うべき借金100万円を親が全額肩代わりしてくれたら、子どもは100万円分の重荷がなくなり、その分子供は100万円分を別な用途に利用できるため、実質親からもらったとみなされます。
高額な美術品を安く譲ってもらった場合
高額な美術品や宝飾品を親から格安で譲ってもらうと贈与税がかかります。課税されるのは譲ってもらった時点での財産の時価と支払った金額の差額部分です。
親子間で贈与税がかからないもの
日常の生活費や教育費
親が子どものために支払う授業料や給食費、交通費、文房具代など常識的な出費はほとんどが非課税です。子どもの留学費も必要なものなら非課税です。この他、親への生活費の仕送りも税金はかかりません。
年間の贈与が110万円以下である場合
生活費や教育費ではない贈与でも、1年間に贈与する財産額が110万円以下の場合は、基礎控除が110万円あるので贈与税は課税されません。
よって、150万円を一度に贈与すると110万円を差し引いた40万円に課税されるので、可能であれば100万円と50万円を2年間に分けて贈与するなどのほうが望ましいです。
贈与税の特例
贈与税に関しては、非課税となる特例がいくつかあります。それらを活用すれば、節税にも役立つので覚えておいて損はありません。ただし、贈与税がかからない方法にはそれぞれに要件や対象となる金額が定められています。
1.教育資金一括贈与の特例
30歳未満の孫や子に対して、祖父母や親が教育資金を贈与する場合、1人につき一括1,500万円までが非課税となります。
最大1,500万円まで金融機関等に資金を預け、子どもが小学校入学、高校入学、大学入学時等に資金を払出して使うことができます。
制度を利用するには、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を特例措置間である、2026年3月31日までに提出する必要があります。
2.結婚・子育て資金の一括贈与の特例
18歳以上50歳未満の人が祖父母や両親から、孫や子の結婚資金や子育てに必要な資金を贈与する場合、1人当たり最大1,000万円までは非課税対象です。このうち結婚資金の非課税枠は300万円までとされています。
50歳までに使いきれずに余った場合は、残りの金額に一般税率をかけた贈与税が発生します。
本特例の期限は2027年までとなっています。
3.住宅取得等資金の非課税の特例
親や祖父母といった直系尊属から住宅の購入や増改築のためのお金を受け取っても、一定額まで贈与税がかからない制度です。非課税限度額は、省エネ等住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅の場合は500万円です。
非課税制度を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。
住居の要件
・日本国内にある住宅であること
・対象となる家屋の床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつ床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるもの
受贈者の要件
・これまでに住宅資金に関する贈与の非課税措置を受けていないこと
・贈与を受けた年の所得税の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合には、1,000万円以下)
・贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
・贈与を受けた翌年の3月15日までに対象住宅に居住すること(12月31日までに確認できない場合は不適用)
無申告にならないように注意する
親から子供、あるいは祖父母から孫への現金や預貯金の贈与は、手続きも簡単で比較的よく行われます。しかし、親子間の贈与は納税意識が薄くなり、申告を忘れてしまうおそれがあります。贈与を行った場合は、贈与を受けた人が贈与税の申告及び納税をしなければなりません。
所得税と同様に申告しなかった場合は、無申告加算税が科せられます。
無申告加算税
正当な理由がないにもかかわらず申告を怠った場合は、「無申告加算税」が科されます。
| 申告のタイミング | 贈与税額 | 加算税率 |
| 税務調査の連絡前に自主的に申告したケース | 区分なし | 5% |
| 税務調査の連絡後~指摘前に申告したケース |
50万円以下 50万円超 |
10% 15% |
| 税務調査で指摘を受けてから申告したケース |
50万円以下 50万円超 |
15% 20% |
| 短期間に繰り返して無申告または仮装・隠蔽がおこなわれたケース |
50万円以下 50万円超 |
25% 50% |
過少申告加算税
申告期限までに申告・納税したものの、本来納める税額よりも少なく申告していた場合
| 申告のタイミング | 贈与税額 | 加算税率 |
| 税務調査の連絡前に自主的に申告したケース | 区分なし | なし |
| 税務調査の連絡後~指摘前に申告したケース |
50万円以下 期限内申告税額と 50 万円のいずれか多い額を超える部分 |
5% 10% |
| 税務調査で指摘を受けてから申告したケース |
50万円以下 期限内申告税額と 50 万円のいずれか多い額を超える部分 |
10% 15% |
重加算税
財産を隠したり、書類の隠蔽、意図的な申告漏れがあったと認められた場合は、ペナルティでは最も重い重加算税が科されます。
| 申告のケース | 過去5年以内にペナルティ歴あり | 過去5年以内にペナルティ歴なし |
| 悪質な無申告のケース | 50% | 40% |
| 悪質な過少申告のケース | 45% | 35% |
延滞税
無申告ではないものの、納付期限までに贈与税を納付しなかった場合は、延滞税が科されます。
| 申請期限 | 税率 |
| 贈与税の申告期限~2ヵ月 | 年利2.4% |
| 贈与税の申告期限から2ヵ月経過後~ | 年利8.7% |
まとめ
贈与に関しては、たとえ親族間のやりとりであっても金額によっては贈与税の支払いが必要です。しかし、さまざまなシチュエーションで利用できる「贈与税がかからない方法」が存在します。
一方で親子間や夫婦間の贈与で納税意識が薄くなって無申告になった場合は、ペナルティが科されるので結果的に損することになります。
暦年贈与の基礎控除110万円を超える贈与の場合は、常に納税意識を持つことが求められますので注意しましょう。