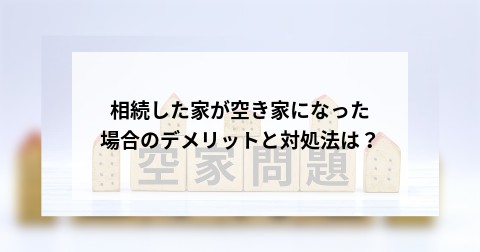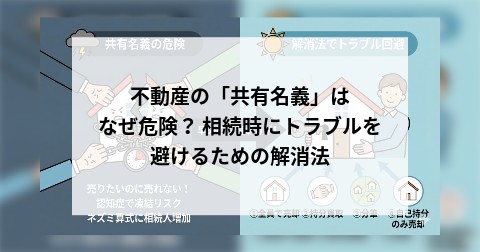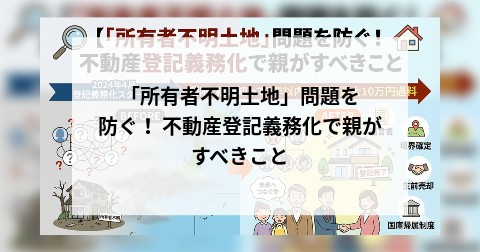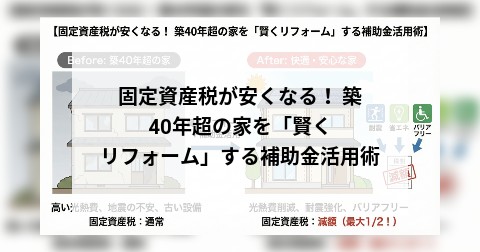リースバックとは?相続税対策として活用できる?
自宅を売却後もリースという形で住み続けられる、リースバックというサービスをご存じでしょうか?
今リースバックは、高齢者に多く選ばれている資金調達方法でもあります。
しかしながらよく契約内容を確認しないまま契約してしまい思わぬトラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。
そこで今回はリースバックのメリットや注意点、リースバック活用までの流れなどを詳しく解説していきます。

リースバックとは?
リースバックとは、自宅をリースバック事業者に売却して売却代金を受け取る一方、リースバック事業者と賃貸借契約を結び、家賃を支払って自宅に住み続ける仕組みです。
不動産の所有権は買主に移るものの、売却者は賃借人として家を使用できるため、生活環境を変えずに資金を確保できます。特に、まとまった現金が必要な場合や、相続対策としての活用が注目されています。

リバースモーゲージとの違いは?
リースバックは、自宅に住み続けながら老後資金を受け取れるという点で、リバースモーゲージとも比較されるサービスです。一方で、リースバックが不動産取引であることに対して、リバースモーゲージはローン商品であるため、根本的には異なるサービスです。
リバースモーゲージについては以下の記事を参照してください。
リバースモーゲージとは?メリット・デメリットや注意点などを解説
主な違いは下表のとおりです。
| 内容 | リースバック | リバースモーゲージ |
| 物件の所有権 | 売却先の不動産会社 | 本人 |
| 固定資産税の納税義務 | なし | あり |
| 資金用途 | 自由 | 投資や事業資金はNG |
| 年齢条件 | なし | 条件によるが65歳以上が多い |
| 対象物件 |
制限なし ※業者次第で工場、事務所等も対応可 |
一戸建て ※マンションを対象としたサービスも一部あり |
| 同居 | 可能 | 配偶者のみ |
| 契約終了後 | 買戻し可能 | 売却 |
リースバックのメリット
売却後も住み慣れた家に住める
リースバックの最大のメリットは売却後も住み慣れた家に住めることです。通常の不動産売却であれば、所有権が第三者に渡った時点でその家から退去する必要があり、引越し費用や手間がかかることに加えて、新しい生活環境に慣れるまで家族に負担がかかってしまいます。
家を所有するコストがなくなる
リースバックでは、家賃の支払いが加わる代わりに、住宅ローンの返済の他にもマンションの管理費・修繕積立金や固定資産税・都市計画税などの家を所有するコストの支払いがなくなります。
短期間で自宅を現金化できる
一般的な不動産売却方法に比べて、資金をスピーディーに得られるのもメリットです。
通常の不動産売却だと、家を売りに出してから成約するまで数カ月以上はかかるでしょう。興味を持つ買主が現れても、細部の条件を詰めている段階で破談となることも少なくありません。
その点、リースバックであれば交渉のストレスなく早い段階で売却が決まり、現金化ができます。
将来的に買戻しも可能
リースバックで売却した物件を条件次第では、将来的に再度購入することも可能です。
例えば、不動産売買の契約の際に買い戻し特約を付けることで、いくつかの要件はありますが、一度売った不動産を買い戻すことができます。
リースバックは相続税対策としても利用できる?
リースバックをすると相続の時に発生する問題を解決することができます。リースバックを相続対策に活用すると、以下のようなメリットがあります。
自宅の現金化により財産を公平に分割できる
複数の相続人がいる場合、不動産の相続は手間がかかりますが、リースバックで現金化済みであれば、そのような心配が無用となります。「亡くなったあとに誰が持ち家を継ぐのか」「不動産を含む遺産をどのように分けたら平等か」といった問題からくる揉め事を最小限に抑えられるでしょう。
相続税の負担を軽減できる
相続時に発生する相続税の額は、資産の評価額によって決まります。不動産を所有したまま相続すると、土地や建物の評価額は課税対象となり、相続税が大きくなります。しかし、リースバックを活用して不動産を現金化すれば、課税対象となる資産の評価額を抑えることができ、相続税を軽減できます。
また、リースバックを活用する場合にも、譲渡所得に対する「3000万円特別控除」などの税制優遇措置を利用することができ、課税対象となる金額を減らすことができます。
リースバックの注意点
売却価格が相場より安くなる傾向にある
リースバックは、基本的に自宅の売却価格が市場価格よりも安くなります。個人に売却する不動産仲介とは異なり、不動産業者が直接買い取りをするため、市場価格よりも安く買い取るためです。
また、リースバック運営会社は買い取った不動産を所有するリスクやコストを維持する点で、一般的な不動産買取よりも価格が安くなることも珍しくありません。
家賃の支払いが発生する
リースバックでは、家を売却した後も建物賃貸借契約を結ぶことでそのまま住み続けることができますが、毎月決まった家賃を支払わなければなりません。リースバックを検討する際は、売却価格に加え、売却後に支払う家賃も確認してください。
事前に相続人と話し合いが必要になる
リースバックをすると、家の所有権はリースバック会社のものになります。そのため、相続人が将来その家を所有したい・住みたいと考えている場合、勝手にリースバック契約をしてしまうと、後々トラブルになる可能性があります。契約を検討する前に、相続人としっかり話し合っておきましょう。
ずっと住み続けられるとは限らない
リースバックは、自宅に引き続き住むことができるサービスですが、希望する期間住み続けられるとは限りません。リースバックにおける賃貸借契約が普通賃貸借契約であれば、原則住み続けることができます。
一方で、定期借家契約の場合、ずっと住み続けられる保証はありません。貸主と借主の合意があれば再契約は可能ですが、あらかじめ、「必ず再契約をする」などの契約を結ぶことはできません。当初の賃貸借契約の期間を越えて家に住み続けたい場合は、定期借家契約ではなく、普通借家契約が締結できる運営会社を選ぶと安心です。
リフォームや建て替えを自由にできない
持ち家の場合、マンションなどの規約が定められている場合を除き、自由にリフォームや建て替えができます。しかし、リースバックを利用すると、不動産の所有者はリースバック運営会社になるため、リフォームや建て替えをしたいと思っても、運営会社の許可が必要です。
リースバックが向いている人はこんな方
リースバックを活用した相続対策は、次のような方に向いています。
- 住宅ローンの返済に不安がある人
- 今の生活や将来に向けて、まとまった資金が必要な人
- 相続問題を解決したい
- 将来的に買い戻したい人
住宅ローンの返済に不安がある人
リースバックは住宅ローンの残債があっても原則利用可能ですが、細かい条件や注意点があります。
リースバックを住宅ローンの残債ありで利用するには、アンダーローンの状態であることが基本です。アンダーローンとは、住宅ローンの残債が家の売却金額を下回っていることを指します。つまり、自宅の売却価格から売却にかかる諸費用を差し引いた金額が、住宅ローンの残債を上回っていれば、リースバックを利用できると考えてよいでしょう。
しかし、オーバーローンの場合はリースバックを利用できないので注意してください。
今の生活や将来に向けて、まとまった資金が必要な人
リースバックで得られる売却資金は、短期間で現金化がしやすく使い道も自由です。老後資金や子どもの成長にともなう教育資金、事業資金などを捻出したい場合もリースバックが役立ちます。今の住まいと暮らしを維持しながら、余裕ができた後に再び買い直せる場合もあります。
相続問題を解決したい人
子どもが進学や就職などで離れて住んでいる、結婚してすでに住居を所有しているなど、両親の自宅を引き継がないケースも増えています。将来的に自宅を遺す遺族が居ない場合、リースバックで遺産整理しておくのも相続対策の一つです。家族や親族への財産分与もしやすくなり、相続に関する手間やトラブルを未然に防ぐこともできます。
将来的に買い戻したい人
現時点では資金を得るためにマイホームを手放すとしても、将来的には愛着のある住まいを取り戻したいと希望する方もいるでしょう。数年間賃貸住宅として住み続けながら生活を立て直し、経済的に安定した時点で自宅を買い戻すことを計画している方にもリースバックはおすすめです。
リースバックの流れ
ここからは、一般的なリースバックの流れについては以下の通りです。
- リースバック事業者に相談
- 自宅の査定
- 買取金額の提示とリースバック条件の提案
- リースバック事業者との売買契約
- 決済
- リースバック事業者との建物賃貸借契約
- 家賃の支払い開始
リースバックを利用するには、通常の不動産売却と同じく、不動産権利証(登記識別情報)、不動産の資料、本人確認書類、住民票、印鑑証明書などさまざまな書類が必要です。当然ながら、書類に不足があると、手続きがスムーズに進まなくなってしまいます。必要書類はリースバック事業者によって異なるため、事前に確認して準備しておきましょう。
まとめ
リースバックは、自宅を売却した後も同じ家に住み続けられるので、「老後資金を確保したい」「住宅ローンの返済負担を減らしたい」という場合に活用できます。ただし、売却価格は市場価格より安くなり、ずっと住み続けられる保証はありません。契約してから後悔しないように、メリットやデメリットをよく理解したうえで、リースバックを利用するか検討しましょう。