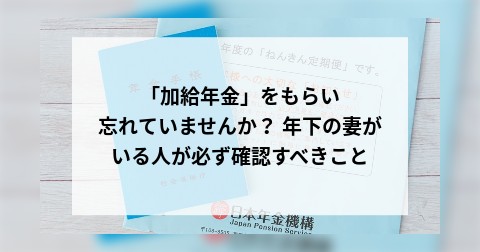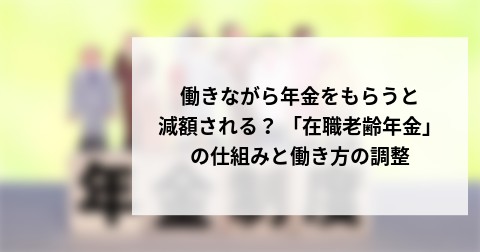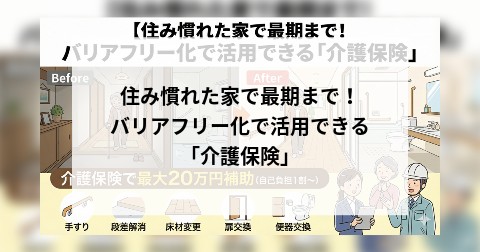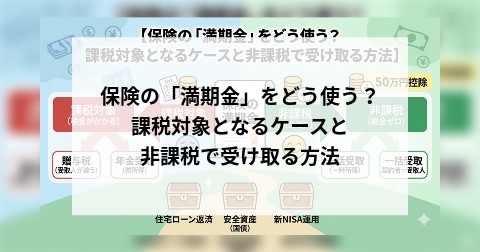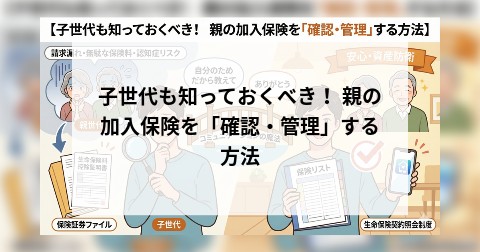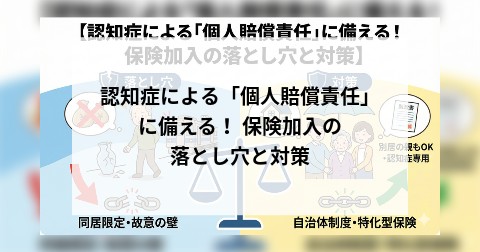60歳以降の厚生年金はどうする?加入のメリットデメリットについて
国民年金の保険料は原則20歳~60歳まで支払いますが、厚生年金は60歳以降も支払います。「老後にもらえる年金が少ない」と思うならば、60歳以降も厚生年金に加入して働くのがおすすめです。
本記事では、60歳以上の厚生年金加入に潜むデメリットとメリットなどをご紹介します。
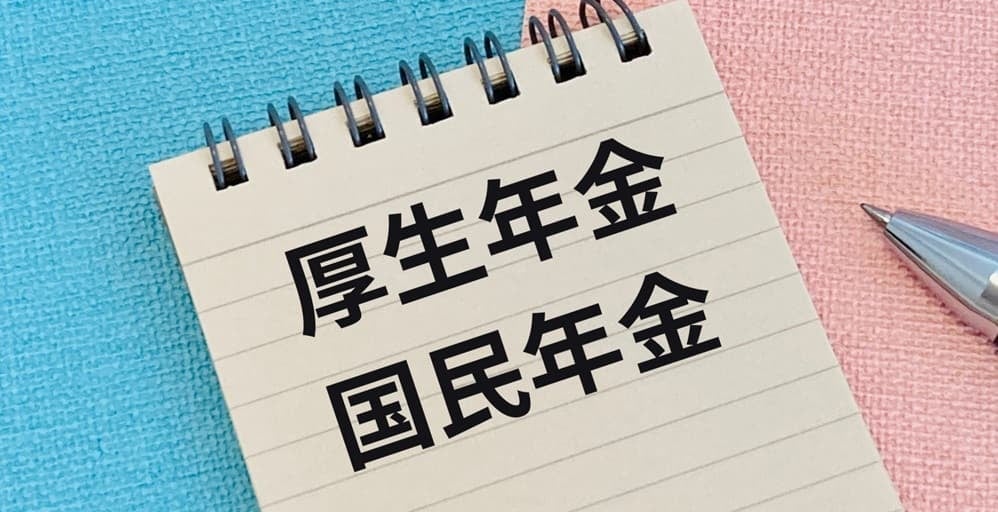
60歳以上の厚生年金の加入義務
日本の年金制度は2階建て構成になっており、1階部分が国民年金から形成される「老齢基礎年金」、2階部分が厚生年金保険から形成される「老齢厚生年金」という構成です。
国民年金は、原則としてすべての国民(20歳〜60歳)が加入対象で、保険料を40年間納めれば満額で老齢基礎年金を受給できます。
一方、厚生年金保険については、厚生年金保険に加入済みの事業所に勤務する従業員(70歳未満)が対象となる保険です。
つまり、60歳を過ぎて会社員として働き続けるのであれば、厚生年金保険に加入して70歳まで保険料を納付する義務があります。
60歳以上も厚生年金に加入するメリット
60歳以上でも働いている方が、被用者として健康保険などの公的医療保険制度や厚生年金保険などの公的年金制度に加入していることで得られる主なメリットには下記のものがあります。
- 将来受け取れる厚生年金の受給額が増える
- 扶養している配偶者がいる場合、配偶者の老齢基礎年金の受給額も増える
- 健康保険にも加入し続けられる
将来受け取れる厚生年金の受給額が増える
厚生年金は加入期間が長ければ長いほど、将来受け取れる年金額が増えます。
先ほど、日本の年金制度は、国民年金が軸の1階部分「老齢基礎年金」と厚生年金が軸の2階部分「老齢厚生年金」の2階建て構成ということを説明しました。
年金の1階部分である「国民年金」については、20歳から60歳までの40年間(計480ヶ月)の上限額の範囲内でしか受給できません。
一方、年金の2階部分である「厚生年金」については、上限が設定されていません。そのため、加入期間が長ければ長いほど、平均標準報酬月額や平均標準報酬額が増える仕組みになっています。
厚生年金に加入して保険料を納付している限り、その分が年金額に反映されます。つまり、2階部分の厚生年金が増えることで、年金全体の受給額が増えるという仕組みです。
働く期間が長く給与の支給額も多いほど、厚生年金の受給額は増えるということを覚えておきましょう。
配偶者(扶養)の老齢基礎年金の受給額が増える
60歳を超えて厚生年金に加入することで、配偶者(扶養)の老齢基礎年金の受給額が増額します。これは、被保険者の扶養に入っている配偶者や子どもがいた場合、加給年金額の受給額が増額するためです。
加給年金額は、厚生年金の被保険者が下記の2つの条件を満たしている場合に加算されます。
- 厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上
- 65歳で老齢厚生年金を受け取る時点(または特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受け取る年齢に達した時点)で扶養している配偶者または子がいる
加給年金額は、いわゆる年金における「家族手当」に該当するものです。被保険者に扶養家族がいる場合は、通常の老齢厚生年金にプラスして支給されます。
ただし、加給年金を受け取るには、配偶者や子どもが下記の条件を満たしている必要があります。
- 配偶者が65歳未満であること
- 子どもは18歳到達年度の末日まで(1・2級の障害状態にある子どもは20歳未満)
- 配偶者が被保険者期間20年以上の厚生年金を受け取る権利がないこと ・年収850万円未満(所得655万5000円未満)であること
厚生年金保険の加入期間が増えれば加給年金額もその分加算されるため、結果的に扶養家族の老齢基礎年金の受給額も増えることになります。
健康保険に加入できる
60歳以降も厚生年金に加入し続ける大きなメリットとして、健康保険に加入できることが挙げられます。
- 健康保険料の半額を会社が負担
- 傷病手当金や出産手当金制度の支給
- 扶養制度による世帯における保険料額の減額
上記のような健康保険へ加入することでのメリットを、現役世代の会社員と変わらずに得られます。老後はどうしてもケガや病気のリスクが高まるもの。傷病手当金の支給など、健康保険へ加入することで得られるメリットは大きいでしょう。
60歳以上で厚生年金に加入するデメリット
在職老齢年金制度による年金カットがある
60歳以降、老齢厚生年金を受け取りながら働くと、収入に応じて年金が減ってしまう「在職老齢年金」という制度があります。
在職老齢年金制度における年金カットの基準となるのが、いわゆる「51万円の壁」といわれるものです。
60歳以降に年金を受け取りながら働く場合、「老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額」と「総報酬月額相当額(月給・賞与(その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の1/12)」の合計額が51万円を超えると、年金が減額されてしまいます。
支給停止額の計算方法・シミュレーション
年金カット額は、以下の計算式で算出できます。
(老齢厚生年金(報酬比例部分)の基本月額+総報酬月額相当額-51万円)×1/2=支給停止額
【計算例・シミュレーション】
例1:基本月額10万円、総報酬月額40万円→年金カットなし
例2:基本月額15万円、総報酬月額40万円→年金カット2万円
例3:基本月額18万円、総報酬月額35万円→年金カット1万円
例4:基本月額14万円、総報酬月額51万円→年金カット7万円
保険料負担が継続する
60歳以降も厚生年金に加入する場合、現役世代と同様に厚生年金保険料を納める必要があります。
保険料は会社と折半で、給与から天引きされるため、年金カットと保険料負担のダブルパンチになるケースもあります。そのため、継続加入する際はしっかり検討したほうがよいでしょう。
国民年金への切り替えができない
60歳以降も厚生年金に加入して働く場合、原則として国民年金の任意加入被保険者になることはできません。
厚生年金の加入義務が優先されるため、仮に保険料負担の少ない国民年金(任意加入)で基礎年金のみを増やしたいと考えても、その選択肢はなくなります。
まとめ
60歳以上の厚生年金への加入について、厚生年金の基礎知識や加入義務の有無、メリットやデメリットなどについて解説しました。60歳を過ぎても会社員として現役世代と変わらず勤務するのであれば、厚生年金に加入が必要となります。
60歳以降の年金については、単純に「国民年金は任意」「厚生年金は義務」と覚えておくとわかりやすいでしょう。厚生年金へ加入すれば「年金額が増える」「健康保険へ加入できる」などのメリットを得られます。
しかしながら、「年金の一部(在職老齢年金)がカットされる」「保険料負担が継続する」などのデメリットもあるため、双方の特徴を踏まえて加入するか検討しましょう。