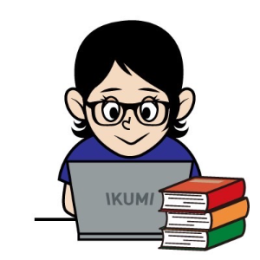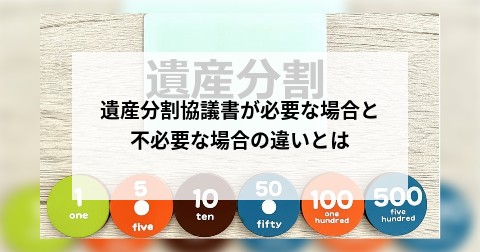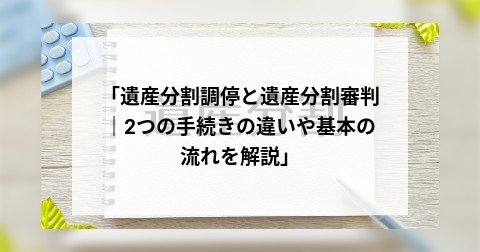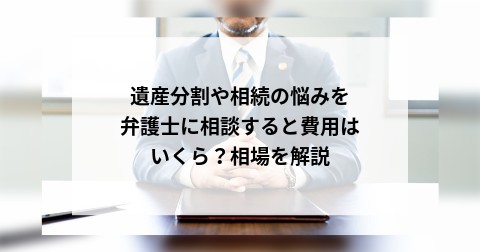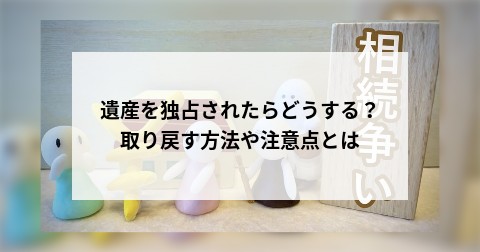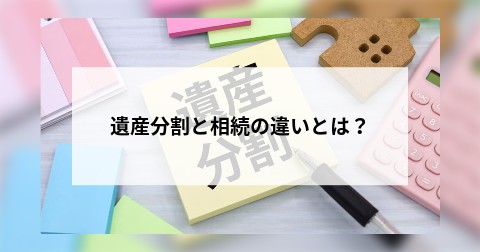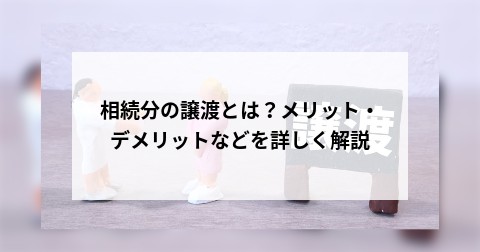遺産分割調停とは?|調停の手続の概要や注意点・相続についても詳しく解説!
被相続人(亡くなられた方)の相続財産について、遺産分割協議を相続人間で進めていても、話し合いが進まない場合はどのように対応すればよいのでしょうか。話し合いによる解決が難しい場合には「遺産分割調停」を検討してみましょう。そこで、本記事では遺産分割調停について手続の概要や、進める際の注意点を詳しく解説します。

遺産分割調停は、家庭裁判所に「申立て」することでスタートします。申立先の家庭裁判所は、以下2つから選択します。
|
① 相手方のうち一人の住所地を管轄する家庭裁判所 ② 当事者が合意で定める家庭裁判所 参考URL 裁判所 遺産分割調停 |
上記をわかりやすく解説すると、①は話し合いをしてほしい相続人が暮らす住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てすることです。たとえば、東京都新宿区に暮らす相続人が、埼玉県さいたま市に暮らす別の相続人に遺産分割調停に参加してほしい場合は、さいたま市を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。
②は相続人全員で「この家庭裁判所にしよう」と合意して決める方法です。東京都と大阪府にいる相続人が遺産分割調停をしたい場合、中間地点として参加しやすい愛知県名古屋市を選ぶこと、などが該当します。
なお、住所地を管轄する家庭裁判所は、以下裁判所リンクより確認できます。
参考URL 裁判所 裁判所の管轄区域
◆調停に必要な書類と費用
遺産分割調停に必要な書類と費用は以下です。
| 必要書類 | 入手方法 |
| ・申立書1通(および写しを相手方の人数分) |
・家庭裁判所リンクより入手可、記載例あり |
| ・被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本類 | ・相続人側で用意 |
| ・相続人全員の戸籍謄本 | ・相続人側で用意 |
| ・相続人全員の住民票(戸籍の附表でも可) | ・相続人側で用意 |
| ・遺産に関する証明書 | ・被相続人の財産がわかるものを相続人側で用意(例・預貯金通帳の写し、登記簿謄本等) |
| ※被相続人の子(および代襲者)が死亡している場合はその子や代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本類 | ・該当する方のみ相続人側で用意 |
この他、相続人のご状況によっては別途、準備必要な書類もあります。詳しくは家庭裁判所の以下リンクの「5.申立てに必要な書類」をご一読ください。
参考URL 裁判所 遺産分割調停 5.申立てに必要な書類
・費用
費用は被相続人1名につき、収入印紙で1,200円を用意します。
また、家庭裁判所が指定する郵便切手を用意する必要がありますが、各地によって異なるため、申立て前に確認しましょう。
◆調停の進め方とかかる期間
遺産分割調停は以下の流れに沿って行われます。
- 必要書類・費用を整え家庭裁判所へ申立て
- 家庭裁判所が呼出状を発送
- 調停期日の調整
- 調停開始
- 調停成立の場合は調停調書を作成して終了
- 調停不成立の場合は遺産分割審判へ移行
遺産分割調停の期間は、一般的に1年~2年程度とされています。
「令和5年司法統計 第45表 遺産分割事件数―終局区分別審理期間及び実施期日 回数別―全家庭裁判所」を参考にすると、審理期間(調停にかかった期間)の第1位は4,581件で1年以内、第2位は3,196件で2年以内です
遺産分割調停における3つの注意点
①調停が不成立となる可能性がある
遺産分割調停は、あくまでも「話し合い」による合意を目指すものです。調停に発展する背景は人それぞれですが、喧嘩のような状態に陥ると合意が難しくなるため、結果として「不成立」になる可能性があります。
不成立の場合は遺産分割審判に移行し、裁判官が証拠や相続人の主張の下に審判を下します。
②調停は長期化する可能性もある
遺産分割調停は先に触れたように1~2年の期間を要することが多く、短期間での調停成立が難しい場合があります。3年以内の調停も珍しいものではなく、その期間は遺産分割が決まらないこととなります。各相続人にとって、調停は重い負担となるケースも珍しくありません。
③相続税申告に影響するおそれがある
遺産分割には法的な期限はなく、1年かかっても5年かかっても問題はありません。しかし、相続にはさまざまな手続があり、期限が設けられているものがあります。たとえば、相続税申告は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」に行う必要があり、遺産分割調停が長引いていたとしても、申告・納税を行う必要があります。
遺産分割の内容が確定していないと、配偶者の税額控除等が使えなくなるなどのデメリットもあるため、遺産分割調停と並行して相続税申告の準備は税理士に相談しながら進めていく必要があります。(※)
(※)ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例は適用できます。
遺産分割調停はどんな時におすすめ?
遺産分割調停は長期化しやすかったり、相続税申告に影響するおそれがあるなど、デメリットと言える側面があります。では、どのような時なら遺産分割調停がおすすめできるのでしょうか。
話し合いでは解決が難しいケース
すでに遺産分割の話し合いの段階で相続人同士が衝突している、話し合いが並行している場合は、裁判官や調停委員がいる調停で話し合うことがおすすめです。第三者が介入することで冷静に意見を主張でき、意外にもスムーズに解決できるケースも少なくありません。
予想以上に早期に解決できる場合も多くなっています。
争いたい点があるケース
別の相続人に対し、意見を主張したい、争いたいなどの意向がある場合、早期に調停に移行させることで、話し合いが円滑になることがあります。
また、介護や扶養などで貢献していた場合、寄与分を主張することが可能です。寄与分の主張は「遺産分割調停」と「寄与分を定める処分調停」があり、併せて申し立てることができます。
話し合いに応じない相続人がいるケース
遺産分割は相続人全員で協議する必要がありますが、相続人に連絡をしても応じてくれないケースもあります。この場合、調停を申し立てると家庭裁判所が呼出を行ってくれるため、協議が進めやすくなります。
遺産分割調停は慎重に進めよう|相談できる人とは?
遺産分割調停は話し合いが円滑になる一方で、解説のとおりデメリットと感じられる点もあります。また、調停委員に対して自らの意見を主張する必要があったり、証拠を提出する場面もあるため、慎重に準備を重ねて臨むべきでしょう。では、遺産分割調停に臨む場合は、誰に相談ができるでしょうか。
弁護士
弁護士は遺産分割協議・調停・審判のいずれの代理人にも就任できるため、相談相手としておすすめできる専門家です。申立てをしたい方、申し立てられた方のいずれからの依頼も受けることができます。
申立てに必要な書類の作成、調停への同行や代理出席なども行ってくれるため、調停のベストパートナーと言えるでしょう。
税理士
遺産分割と並行して、相続税申告・納税の準備を進めたい場合は税理士への相談も欠かせません。相続税申告にあたっては、財産の評価を行うだけではなく、必要書類・納税の準備も行う必要があります。
申告期限を過ぎてしまうと延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生してしまうため、遺産分割で揉めていても申告準備が遅れないように注意しましょう。
まとめ
本記事では「遺産分割調停」について手続の概要や注意点を詳しく解説しました。遺産分割調停は長引くケースも少なくありませんが、相続税申告など留意すべき点もあります。一方で、相続人同士の話し合いが難航しても、調停に移行することで円満に終結できるケースも少なくありません。実際に調停に臨まれる際には、弁護士・税理士といった専門家に相談しながら進めましょう。