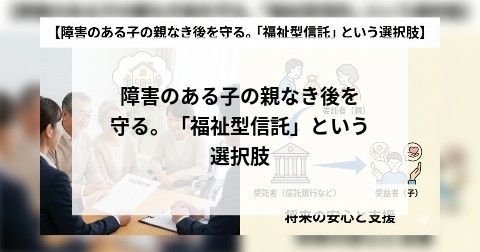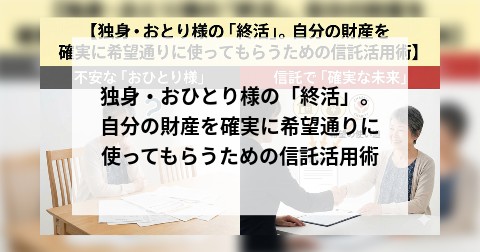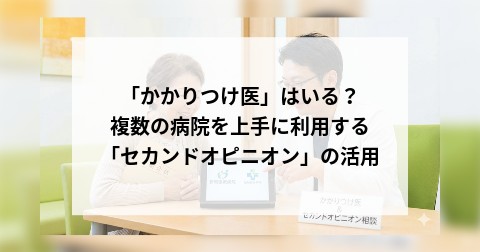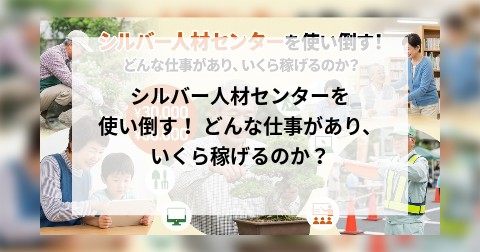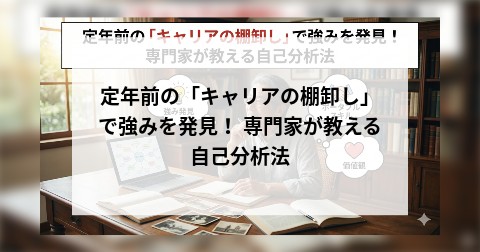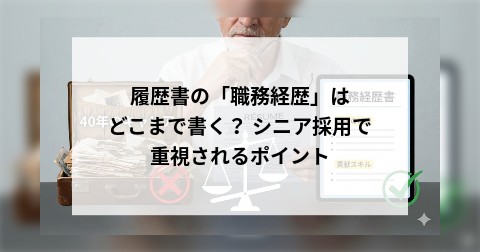年金生活で知っておくべき入院・医療費の負担を軽減する制度
誰しも急な体調不良や、突然のケガで入院することもあるでしょう。しかし、治療を受けたものの、高額な医療費が払えない場合にはどうしたらよいのでしょうか?
今回は老後にかかる医療費についてのほか、保険適用外の医療の自己負担額、将来備えておきたい医療費の目安についてご紹介します。
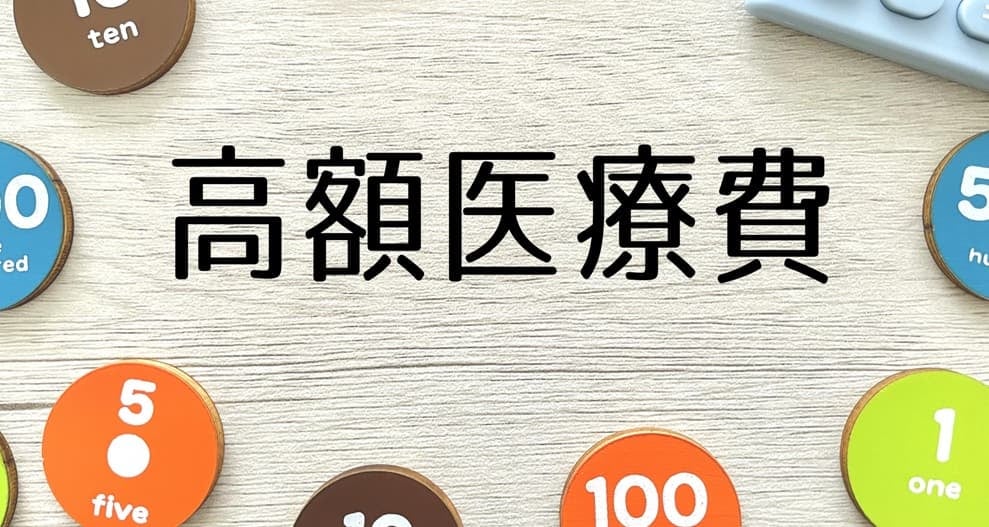
老後にかかる医療費はどれくらい?
令和5年に厚生労働省が発表した資料によると、日本人が生涯必要とする医療費は、総計2,695万円にもおよびます。男女別で見ても、男性で2,614万円、女性で2,781万円と2,000万円をこえています。
そのうち、年金受給が始まる65歳以上の医療費は1,604万円、つまり生涯医療費の57%が老後に集中していることになります。 特に70代後半から80代前半にかけて医療費がピークを迎える傾向があります。
65歳以上の医療費自己負担割合は?
65歳以上の医療費の自己負担割合は、所得に応じて異なります。 一般的な所得の方は 自己負担割合は1割 ですが、一定以上の所得がある場合は、負担割合が2割または3割となります。
老後の医療費負担を軽減する方法
老後の医療費負担を軽減するためには、さまざまな制度や方法があります。 高額療養費制度をはじめ、医療費控除や特例を上手に活用することで、自己負担額を減らすことが可能です。
以下では、これらの方法について詳しく説明します。
高額療養費制度
高額療養費制度は、医療費の減額制度のことです。通常、病気やケガで治療を受けた場合、医療保険証を病院に提示することで1~3割負担の支払いですみます。しかし、1~3割負担とはいえ積み重ねで高額になった場合に備えて医療費の上限金額を設け、負担を抑えるのが高額療養費制度です。
この制度は、月ごとに医療費の上限が決められており、その上限を超えて支払った分が、2~3ヶ月後に戻ってくる仕組みになっています。この自己負担の上限金額は、所得や年齢によって異なります。
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は75歳以上もしくは、65歳〜74歳までで一定の障害状態にある人が加入する医療保険です。医療費は69歳までは3割負担、70〜74歳は2割負担ですが、後期高齢者医療制度の被保険者になると、現役並み所得者以外は1割負担になります。
そのほか「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」を提示すると、入院時の食事代の負担が軽減されるほか、被保険者が死亡した際に葬儀を行った人へ葬祭費が支給されるなどの給付が用意されています。
75歳を迎えると自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となるため、加入手続きなどは特にありません。保険料は年金から天引きされるため、支払い忘れも起こらないでしょう。
医療保険への加入
医療保険に加入していると、公的医療保険の対象にはならない先進医療費や差額ベッド代などのお金をカバーできます。医療保険は一生涯保障する終身型と、一定期間保障する定期型に分かれており、特定の疾病に特化した商品や医療に関する全般に対応したものがあります。
保障も入院1日当たり1万円といった日額型と、実際の費用を保障する実費型があるため、自身の希望に応じて検討しましょう。ただし、医療保険は高齢になるほど保険料が高くなる傾向にあるため、本当に必要な保障だけを選ぶ必要があります。受け取れる年金の額が少ない、将来の貯蓄が足りない可能性がある人は、医療保険への加入をご検討ください。
医療費のための資金を確保する
老後の医療費や生活費を、年金だけで補うのは難しいでしょう。少しでも老後のお金に対する不安をなくすためには、早いうちから貯蓄や投資を活用して備えておきましょう。
貯蓄
老後の医療費や生活費の負担を減らすには、貯蓄を行いましょう。貯蓄をする際は、ただお金を貯めるのではなく、目的や目標額を決めると続けやすくなります。例えば、老後の生活や病気に備えるために、3年後までに300万円貯めるなどです。
目標や目的を決めたら、家計の見直しで収入と支出を確認し、毎月の貯蓄額を設定します。この時、目標金額に届かないからといって、無理な貯蓄をしようとするのはやめましょう。生活を切り詰めるような、無理な貯蓄は長続きしません。まずは目標を意識しつつ、無理のない範囲でコツコツと続けていきましょう。
iDeCo
iDeCoは個人型確定拠出年金で、公的年金とは別に、自分自身で用意をする年金制度です。自身で掛金を拠出し、運用商品を選定・運用します。通常、投資によって得た利益には税が加算されますが、iDeCoの場合は運用によって得た利益を、非課税で受け取れる税制優遇が用意されているのが特徴です。
ただし、運用益を引き出せるのは、原則60歳になってからと決まっています。そのため、老後に向けた資金を作りたい人におすすめです。
まとめ
老後に必要となる医療費の自己負担額や、自己負担額を減らすための方法についてご紹介しました。公的医療保険が適用される場合、老後の自己負担額は6〜8万円ほどとさほど高くありません。しかし、保険が適用されない治療やサービスを利用すると、自己負担額は大幅に増える可能性もあります。
少しでも医療費に関する不安を減らすためには、将来のための資産形成はもちろん、医療保険などの加入で備えておきましょう。また、利用できる公的制度についても事前に調べておくと、安心して生活を送れるでしょう。