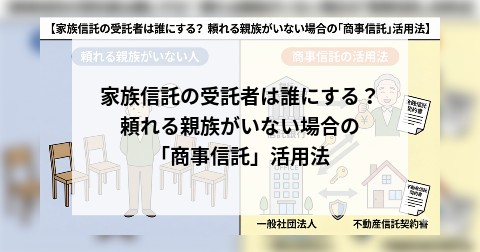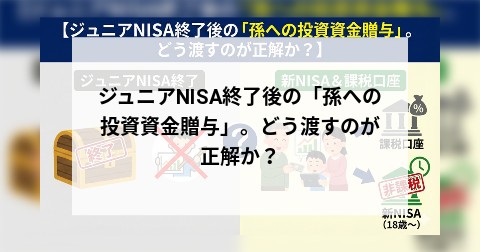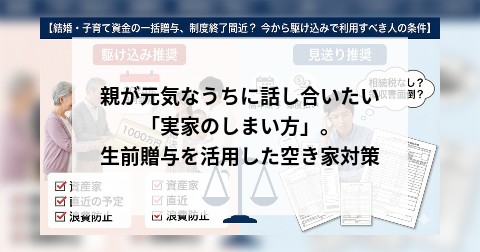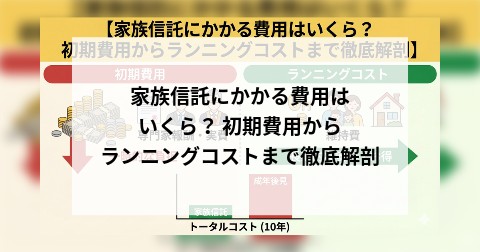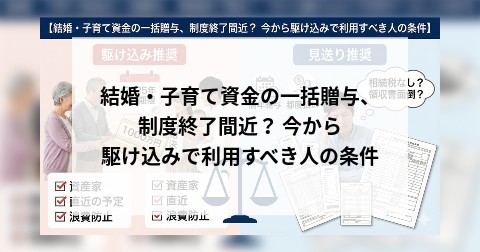漠然とした不安を解消!家族信託と生前贈与で始める「安心老後」の第一歩
近年、高齢化社会の進展に伴い、認知症などで判断能力が低下した場合に備えた財産管理の方法として、家族信託や生前贈与が注目されています。
ただ、家族信託と生前贈与は異なる性質を持つものであり、目的に応じて使い分けるべき制度になります。
そこで今回は家族信託と生前贈与のどちらの制度があっているのか、そもそも2つの制度にはどのような違いがあるのかについて解説しています。
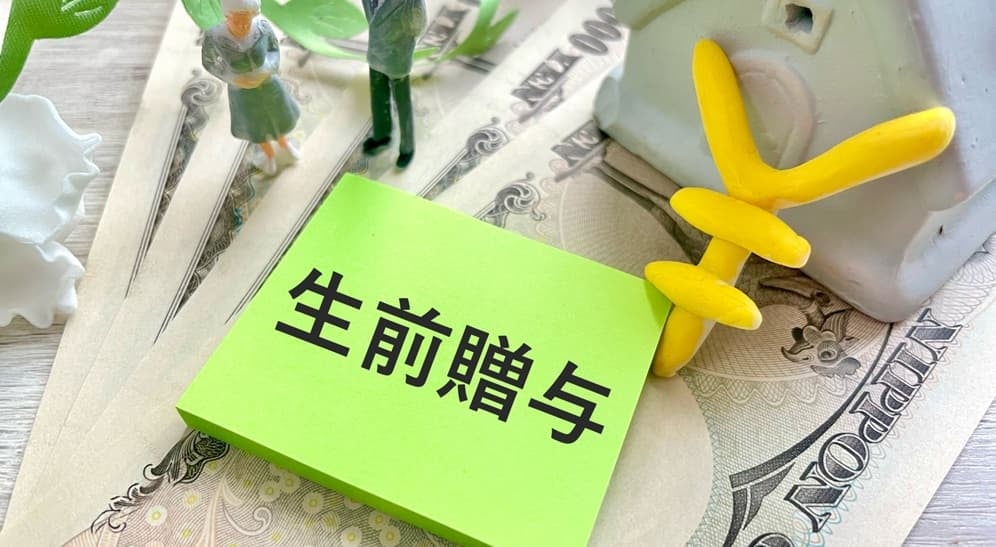
生前贈与と家族信託の違いについて
財産にまつわる権利には、管理する権利、運用する権利、処分する権利、そして財産から利益を得る権利がありますが、生前贈与と家族信託ではどの権利が親に残るか、という点に違いがあります。財産の管理を託すか、財産そのものを譲るかという点がポイントなのです。
| 生前贈与 | 家族信託 | |
| 内容 | 子が自由に運用・処分できる | 子が運用・処分できる 受益権(家賃など)は親に使用 |
| 移転される権利 (贈与者に残る権利) |
所有者としてすべての権利が 子に移転する |
家賃や売却代金をもらう権利は 親(贈与者)に残る |
| タイミング | 認知症になる前 | 認知症になる前 |
| 贈与税 | かかる | かからない |
| 相続税 | かからない | かかる |
| 不動産相続税 | かかる | かからない |
| 登録免許税 | 家屋評価額の2% | 家屋評価額の0.4% |
生前贈与は、家族信託では発生しない贈与税、不動産取得税がかかってしまいます。贈与税については、贈与額が高額になればなるほど税率が上がり最大で55%もの税金が取られてしまいます。また、不動産の登録免許税についても生前贈与は家族信託の5倍もの費用が必要となるため、注意が必要です。
家族信託と生前贈与の違い①:財産の所有権
家族信託も生前贈与も自分の財産を受託者や受贈者の名義にする点については同じです。
金銭の場合には受託者や受贈者の口座に振り込みを行いますし、対象の財産が不動産の場合には、両方とも所有権移転登記が必要となります。
ただし、家族信託の場合、受託者はあくまで委託者の委託に基づいて財産管理や運用を行う立場です。そのため、基本的に信託契約を結んだ目的を達成したとき、または信託を終了する理由が発生した場合には、受託者は委託者に信託された財産を返還しなければいけません。
対して生前贈与の場合、自分の財産を受贈者に渡した時点で贈与された財産の所有権は完全に受贈者に移ります。契約そのものに瑕疵がある等の事情がない限りは、移転した所有権等が戻るということは予定されていません。
家族信託と生前贈与の違い②:財産管理で得た利益の利用用途
家族信託では、受託者が財産管理や運用、処分を行って得た利益は、信託契約で指定されている受益者に還元されます。契約の内容によっては、受託者に財産管理や運用を行った対価として報酬を設定することもできますが、生じた利益はすべて受託者のものになるわけではないという点には注意が必要です。
一方で、生前贈与の場合、受贈者が贈与者から受け取った財産で財産管理・運用を行った結果生じた利益はすべて受贈者のものになります。
家族信託と生前贈与の違い③:贈与税の有無
家族信託では、受益者が財産を信託した委託者であるかどうかで贈与税が発生するか異なります。委託者が受益者である場合、贈与税は発生しません、このような信託のことを自益信託といいます。なお受益者が委託者以外であった場合には、利用用途や受け取る金額によっては受益者が贈与税を支払う必要があります。
生前贈与の場合、財産を受け取った受贈者は、受け取る金額、利用用途によって贈与税を支払う必要があります。
贈与税は、基本的にその年の1月1日から12月31日までの贈与された分にかかりますが、非課税枠が設定してあり、合算して110万円以内であれば、贈与税がかかりません。
生前贈与とは
「生前贈与」とは、自分が生きているうちに、贈与によって財産を特定の人に譲り渡すことです。
「贈与」とは、法律的には、「自分の財産をあげます(無償で譲り渡します)」と相手に示して、相手が「では、もらいます」と受け入れることで生じる契約のことです。
贈与がなされたとき、財産をあげた人のことを「贈与者」、もらった人のことを「受贈者」といいますが、贈与契約は、贈与者と受贈者が生きていなければできないので、当然、生前におこなわれるものです。その意味ではあえて「生前」贈与といわなくても、贈与=生前贈与であることは明らかです。
しかし、相続や遺贈(遺言で指定する財産承継)などの「自分の死後におこなわれる財産承継」と対比して、「生前におこなう」ということを特に強調したい場合に、あえて「生前贈与」という言葉が用いられることがあります。通常は、生前贈与=贈与を意味すると考えていいでしょう。
生前贈与はどんな人があっている?
生前贈与は以下に該当する方に向いているといえます。
- すぐに財産を渡したい人
- 暦年贈与を利用して、110万円ずつ長期で贈与したい人
- 相続時精算課税制度を利用して2,500万円以下の財産を贈与したいひと
ただし、不動産、現金など何を贈与するかによって不動産の名義変更や登録免許税など多額の税金がかかることもあります。生前贈与をする際には、専門家に相談してアドバイスをもらうことをおすすめします。
家族信託とは?
家族信託とは、財産を保有している人が自分で管理できなくなるときに備えて、家族に財産の管理権限を与える法的な仕組み、財産管理の手法のことです。
家族信託も生前贈与と同様に、認知症になる前であればいつでも利用することが出来る制度です。認知症になり子が親のお金を使用できなくなれば、大きな金銭的な負担がかかることも予想されます。
家族信託を利用することで、子が預金を下ろす、不動産を処分することが可能となり、不動産管理により得た利益は親が得られることから親の管理負担が減るというメリットもあります。
家族信託はどんな人があっている?
家族信託は税金が抑えられるため、多額の税金をかけたくない人に合っています。また、生前贈与では財産がすべて子のものになりますが、家族信託では親の老後・介護のために親の財産を使うことができます。管理・処分によって得た利益を親のために使いたい人には、家族信託が合っているでしょう。
生前に110万円以上の財産を引き継ぎたい人にも、家族信託はおすすめです。家族信託にもメリット・デメリットがあります。自分の状況に家族信託が適しているのか、専門家に相談してから決めると安心です。
まとめ
今回は家族信託と生前贈与のどちらの制度があっているのか、そもそも2つの制度にはどのような違いがあるのかについて解説しました。
家族信託や生前贈与は、うまく利用すればとても便利な制度である一方で、相続後のことを考慮しないと、後々残された相続人同士で争いになってしまう可能性があります。
特に家族信託は、利用する方それぞれで理想とする結果が異なります。したがって、自分の状況に合った信託契約を作成するには、豊富な法知識が不可欠です。
家族信託はテンプレートがありません。盛り込みたい内容によっては、契約がとても複雑になり、一般の方では難しい場合もありますので、専門家のサポートを受けられることをお勧めしています。