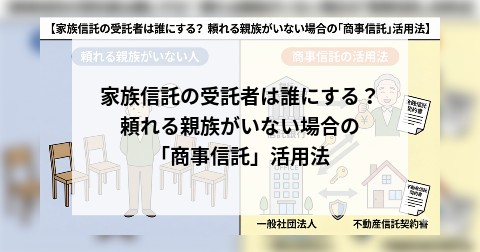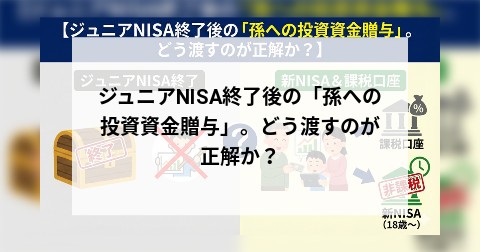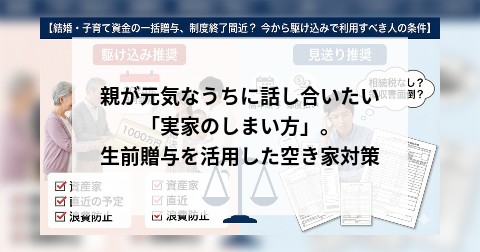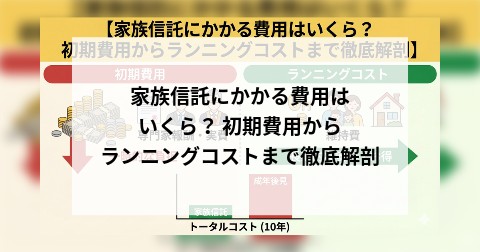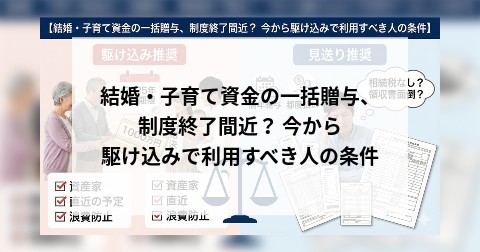成年後見人制度とは?法定後見・任意後見の違いや手続きの流れを詳しく解説
成年後見制度とは、認知症や知的障がいなどによって判断能力が十分ではなくなった人の預貯金や不動産などの財産を守るため、ご本人が安心して生活できるよう支援をする制度です。
成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2種類から成り立っており、今回の記事ではその違いや手続きなどを詳しく解説していきます。

法定後見と任意後見の違いとは
法定後見
法定後見は、本人の判断能力が不十分な者に適用される保護制度です。
認知症や精神病などで、判断能力が失われると詐欺の被害や預貯金の引き出しができないなど日常生活に支障をきたしてしまいます。
このような被害から法的に保護するために設けられているのが『法定後見』です。この法定後見は、判断能力の度合いで「後見」「保佐」「補助」の3種類に分けられています。
任意後見
任意後見は、本人の判断能力が十分なうちに将来的に任意後見人になる人との間で後見契約を行い、判断能力が衰えた後に後見契約の効力を発動させて後見を開始する制度です。具体的な保護・支援の内容は、任意後見契約の内容に依存します。
|
【法定後見】本人の判断能力が低下後に申立人が家庭裁判所に申立てることで後見開始 【任意後見】本人の判断能力が低下する前に後見契約を結び判断能力低下後に後見開始 |
法定後見制度の種類
残っている本人の判断能力の程度に応じて、下記の3種類の制度があります。
■後見
■保佐
■補助
後見|判断能力が欠けているのが通常の状態の場合
後見では、ほとんど判断能力を欠いた人を対象とし、判断能力の低さの程度でいえば最も重度なランクのため、サポートの度合いもかなり高くなります。
後見人は、本人の利益になることのみに権限を使うため、積極的な資産運用や相続税対策を目的とした生前贈与などはできません。
保佐|判断能力が著しく不十分な場合
保佐では判断能力が著しく不十分な人(重要な法律行為の判断が難しい人)を対象とし、家庭裁判所で保佐相当の審判を受けると被保佐人となり、保佐人が付きます。
保佐人は法律行為を円滑に行うため、同意権・取消権を与えられます。基本的に代理権は保有しませんが、家庭裁判所の審判によって認められた法律行為については、代理権も付与されます。
補助|判断能力が不十分な場合
補助は、判断能力の低さの程度では軽度なものですが、判断能力が不十分な人を対象とします。
補助人は保佐人より与えられる権限が少なく、重要な財産の処分や契約について、家庭裁判所が定めたもののみ同意権・取消権を保有しています。加えて特定の行為については、申し立てにより代理権を与えられる場合もあります。
法定後見人等の権限
後見人の権限
被後見人は、原則として自身の身の回りのことができない状態であるため、後見人は財産管理に関することなど基本的に全てについての代理権が認められています。
保佐人の権限
保佐は、自分で判断できる能力があるものの、法律で定められた一定行為については第三者の援助が必要な状態です。
保佐人には、同意権・取消権が認められています。なお、審判や本人の同意があれば代理権も認められています。
補助人の権限
補助は、後見や保佐と異なり大部分のことは自分で判断できますが、複雑な手続きになると援助が必要な状況です。
補助人には、同意権・取消権が認められていますが、同意・取消し対象行為は家庭裁判所が個別に決定します。
任意後見人の種類
任意後見契約を締結するタイミングから考えると、以下の3つの類型に分けることが可能です。
■即効型契約
■将来型契約
■移行型契約
即効型契約|任意後見契約締結後すぐに後見を開始するタイプ
即効型契約は、任意後見契約と裁判所への任意後見監督人選任の申し立てを同時に行い、即効で任意後見が開始する契約です。
即効で後見契約が発効する点がメリットですが、スピード重視のため本人が契約内容を十分に理解しないまま契約が結ばれ、トラブルになる可能性もあります。
将来型契約|判断能力が衰えたときに備えて任意後見契約を締結しておくタイプ
将来型契約は、本人が判断能力を有する時点で契約を締結しておき、判断能力が低下した際に任意後見監督人の選任を申し立てて後見が開始する契約です。
本人の判断能力があるうちに任意後見契約を締結できるのがメリットですが、契約から後見開始までの期間が長期化しやすいため、任意後見受任者が契約の存在を失念してしまうリスクがあります。
移行型契約|任意後見契約と委任契約を同時に結ぶタイプ
移行型契約では、任意後見契約と同時に移行前段階として他の契約を締結することが可能です。
移行型のメリットは、本人の判断能力が十分なうちに任意後見契約と委任契約を同時に結べるため、任意後見人に自分の意見を述べて関係を構築することができる点です。
一方で、任意後見人受任者が任意後見監督人選任の申し立てをせずに権限を濫用してしまう恐れがある点はデメリットと言えます。
任意後見人の業務や権限
財産管理
任意後見人の重要な役割の一つに、本人の財産を適切に管理する「財産管理」があります。財産管理の目的は、本人の財産を維持することです。したがって、投資などのリスクを伴う運用は認められていません。
身上監護
任意後見人のもう一つの重要な役割は、本人の生活を安定させる「身上保護」です。これには、医療や介護に関する契約など、生活に密接に関わる法律行為が含まれます。
法定後見の手続きの流れ
① 家族、四親等内の親族のうちの誰かを「申立人」として、家庭裁判所に「後見開始申立」の手続きを行います。(保佐、補助もほぼ同じ流れ)
② 家庭裁判所に申立書および関係書類一式を提出します。
③ 家裁の調査官が申立人と後見人候補者に面談調査を行います。
④ 家庭裁判所がご本人の家族などに、事実関係、親族間の紛争の有無、後見人候補者の適格性等を、書面や電話で確認します。
⑤ ご本人の判断能力、自立生活能力、財産管理能力などを確認するため、必要な場合は家庭裁判所が専門医による医学鑑定を実施します。
⑥ 家裁がご本人の面談調査を行ない、病状、申立内容、後見申立て理由などについて確認します。(「補助」、「保佐」の場合は、権限の範囲などについて本人の同意を確認します。「後見」で本人の意思疎通ができない場合は省略されます。)
⑦ 家庭裁判所は、提出書類、調査結果、鑑定結果などを審査し、後見を開始すべきか、また、後見人の選任などについて判断を行ないます。(後見人候補者が不適格な場合や親族間に争いがある場合は、第三者後見人を選任します。)
⑧ 家庭裁判所の裁判官が申立について決定(審判)を行い、申立人と後見人に決定内容の通知「審判書」を送付します。
⑨ 通知書が送付されて2週間後に通知内容が確定し、東京法務局へ審判決定事項が登記されます。
⑩ 後見人候補者は後見人としての仕事を開始します。
任意後見の手続きの流れ
① ご本人と任意後見人を引受けた人(以下「任意後見受任者」)とが後見人の契約を結ぶことを確認します
② ご本人と後見人が「任意後見契約書」の内容を確認します。
③ ご本人と後見人が公証役場に出向き、「任意後見契約公正証書」の作成を依頼します。
④ 公証人は以下の事項を確認し、契約内容の要点を説明した上で、公正証書任意後見契約書を作成します。
⑤ ご本人、後見人、公証人がそれぞれ公正証書に署名して、任意後見契約が成立します。
⑥ 署名捺印された公正証書・任意後見契約書は3通作成され、原本は公証役場に保管し、正本と謄本はご本人と後見人に渡されます。
⑦ 公証人は公正証書を作成したことについて、東京法務局への登記手続きを行います。
任意後見と法定後見の違い比較表
| 任意後見 | 法定後見 | |||
| 後見 | 保佐 | 補助 | ||
| 予め必要な手続き |
・任意後見契約書の締結 ・任意後見契約の登記 |
無し | 無し | 無し |
| 効力が発動する条件 |
・本人の判断力の低下 ・任意後見監察人が選任されたとき |
・親族等による家庭裁判所への申し立て ・後見開始の審判が確定したとき |
・親族等による家庭裁判所への申し立て ・補佐開始の審判が確定したとき |
・親族等による家庭裁判所への申し立て ・補助開始の審判が確定したとき |
| 本人の同意の有無 |
必要 但し、意思表示ができない程の判断力低下の状態は不要 |
不要 |
不要 但し、保佐人に代理権を与える場合は必要 |
不要 |
| 対象者 | 障害などにより、判断能力が不十分な状態にある状況の方 | 障害などにより、判断能力が常に欠く状態にある状況の方 | 障害などにより、判断能力が著しく不十分な状態にある状況の方 | 障害などにより、判断能力が不十分な状態にある状況の方 |
| 後見人の選任者 |
本人 但し、任意後見監督人は、家庭裁判所が選任 |
家庭裁判所 | 家庭裁判所 | 家庭裁判所 |
| 後見人が付与される代理行為 | 任意後見契約書で定めた行為 | 財産に関するすべての法律行為 | 家庭裁判所が審判した特定の行為 | 家庭裁判所が審判した特定の行為 |
まとめ
本記事では成年後見人制度の中で、法定後見人と任意後見人の違いやそれぞれのメリット・デメリット、手続きの流れについて解説しました。
任意後見制度は、自分が信頼できる人を後見人に指名できるので、認知症対策としては非常に有効です。しかし、申し立てがされないと効力が発生しなかったり、後見人による不正が必ずしも起きないとは言い切れない点には注意が必要です。
成年後見制度を検討されている方は一度専門家へご相談することをおすすめします。