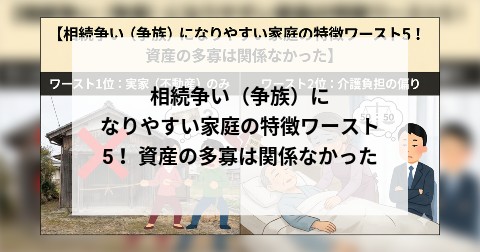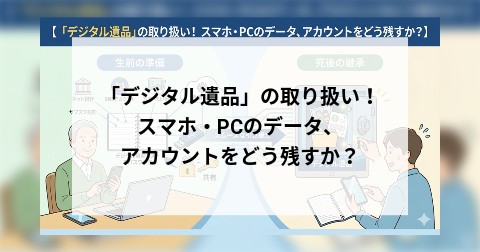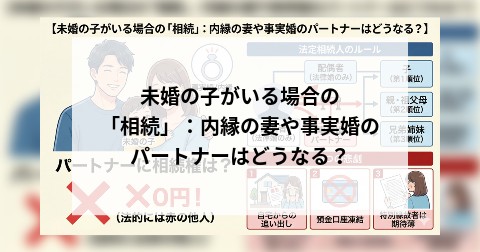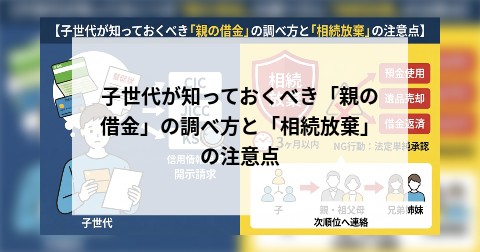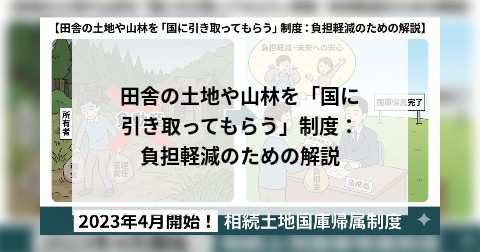相続放棄の基本的な手続き|自分でする際の注意点とは?
相続放棄について耳にすることはありますが、具体的で明白な理解の必要性を感じている方々もおられるでしょう。
本記事はそんな方々が正しい認識を深め、相続放棄を選択される際に必要な情報を提供できるように書かれています。実際に役に立つように分かりやすく記述していますので、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
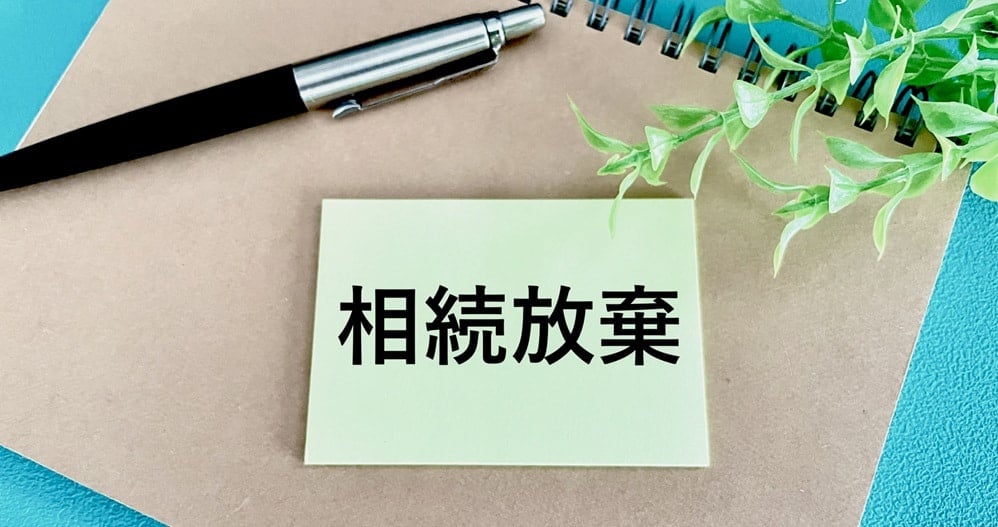
本記事から学べるポイント
|
・相続放棄とは相続人が持っている権利すべてを放棄することです。相続放棄を行うケースとしては、相続財産がマイナスになることや相続トラブルを避けたい時に行われます。 ・手続きには期限があるため早急に行う必要があり、家庭裁判所へ申し立てたり、必要な書類を準備したりするなど複雑な傾向がありますが、手順を踏むことで自分でも行えます。 ・自分で行う際に注意すべき点があり、相続放棄する前には相続財産にいっさい手を付けない、自分が相続放棄した場合の他の相続人に及ぼす影響を考える、相続放棄を一旦実行すると撤回できないことなどが挙げられるでしょう。 |
本記事はそうした内容をさらに詳しく分かりやすく説明していきます。
相続放棄とは
相続財産にはプラスのものもありますが、マイナスの借金や負債も含まれています。相続放棄とは、相続に関する一切の権利を放棄し、遺産を受け継がないことです。
相続放棄を検討するケースとは
相続放棄を検討する主なケースとして5つ挙げられます。それらを順番に解説していくことにしましょう。
①被相続人に多額の借金がある
故人が多額の借金を抱えていた場合、相続すると借金を引き継ぐことになります。
しかし、返済するのに自宅を売ったり自己破産したりする必要があるなら、相続放棄することでそうした悲惨な事態を免れられるでしょう。
②相続財産よりも負債の方が多い
全財産を調査した結果、財産も負債もあるが相殺するとマイナスになってしまう場合、相続放棄することで経済的な負担を負わずにすみます。
③相続トラブルを避けたい
遺産分割において相続人同士の争いが激しい場合やそうなる可能性が予想される場合、相続放棄することでトラブルに巻き込まれるのを避けられます。
④相続財産の管理ができない
相続予定の不動産が遠方で管理に通うのが難しい時や、維持費や税金が高くて支払えない場合は、相続放棄することで負担を避けられます。
ただし、近年の空き家問題が深刻化している現状を考えた時、空き家や土地が放置されると倒壊の危険や雑草が生い茂るなど近隣に迷惑がかかります。
それで相続放棄をしても、空き家や土地の管理義務は残りますので注意してください。
また、管理義務がある空き家や土地が遠方の場合は、自治体に相談し賢明な措置を取れるでしょう。
⑤故人との関係が希薄で付き合いがない
長年付き合うことがなく関係が希薄な親族の相続人になった時、財産や負債を受け継ぎたくないですよね。
そんな場合に相続放棄をするなら、遺産も受け継がず親族との関係を断つことができるしょう。
相続放棄の基本的な手続き
相続放棄の基本的な手続きの流れを説明していきます。
1.家庭裁判所への申立て
全財産を徹底的に調査して相続放棄をした方がいいと判断したら、最初に行うことは、故人が亡くなるまで住んでいた最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述」をします。
この場合、家庭裁判所に直接行かなくても、相続放棄申述書を郵送で取り寄せられます。
2.相続放棄に必要な書類
以下の書類を入手し、前述の家庭裁判所に提出します。
・相続放棄申述書(家庭裁判所で取得可能)
・被相続人の戸籍謄本
・申述人(相続人)の戸籍謄本
・住民票(相続人の住所確認のため)
3.申立ての期限を厳守
相続放棄するためには、期限内に手続きを完了しなければなりません。
期限は被相続人の死亡を知った日から3か月です。
期限を少しでも過ぎると相続放棄は認められないので注意が必要です。
4.家庭裁判所の審査
申述書の提出後、家庭裁判所から相続放棄にいたる詳細な理由などを問う照会書が送付されてくることがあります。
照会書には適正に回答し、必要書類に追加があるなら提出することで、審査を通過し正式に相続放棄が認められます。
5.相続放棄申述受理証明書の取得
相続放棄が認められると、その証明となる「相続放棄申述受理証明書」が家庭裁判所から交付されます。
そうして相続放棄の手続きが終了し、相続に関する問題から解放されます。
相続放棄の手続きを自分でする際の注意点
相続放棄を専門家に依頼すると、様々な書類を集め手続きを代行してくれるので大変助かります。しかし、数万から10万円ほど費用がかかります。
自分でする場合は数千円で済みますし、必要な注意点を押さえれば自分ですることも十分可能です。
では、相続放棄の手続きを自分で行う場合、どんな注意点があるでしょうか。6つの点を考えてみましょう。
遺産に一切手を付けない
相続放棄をする前に、遺産を少しでも使ったり処分したりすると相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなります。ほんのわずかでも、故人の預金を自分が使うために引き出すのは絶対避けましょう。
ただし、葬儀費用や故人の生前の入院介護などの費用は認められています。その場合は領収書や明細書を必ず残す必要があります。
期限を厳守する
前述しましたが、続放棄の期限は3カ月しか熟慮期間がありませんでした。
したがって、相続放棄には故人の全財産を調査し、負債の状況などを確認する膨大な作業をわずか3か月以内にしなければなりません。1日でも過ぎると認められませんので注意が必要です。
すべき大きな作業に対して3か月という期限は短いですから、身内が故人となったら早急に着手しないといけないことが理解できますね。
借金の有無を確認する
相続放棄するにあたり、本当に借金額がプラスの財産を上回っているか確認する必要があります。
借金の有無を確認するには、自宅の郵便物に督促状や契約書がないか調べたり、銀行通帳に定期的に返済している金額がないか調査したりできます。
また信用情報機関に問い合わることや、不動産登記簿で抵当権が設定されていないか調べることも可能です。
他の相続人と話し合う
自分が相続放棄をする場合、借金などの負債の財産も含め、相続順位の次の相続人が相続することになります。それで相続放棄を決断したら、まず家族と話し合い、及ぶ影響について明確にしておく必要がありますね。
また故人が借金のため連帯保証人をつけていた場合は、相続人すべてが相続放棄すると、連帯保証人が借金を背負うことになります。
ですから、せっかく故人を信用して連帯保証人になってくれた人に過剰な負担を負わせないため、相続人全員がよく考えて慎重に行う必要があるでしょう。
一旦、相続放棄をすると撤回できない
相続放棄を一度してしまうと、もう撤回はできません。
ですから期限までの短い間に、財産調査を徹底して行う必要があることが分かりますね。
なかには、相続放棄をした後で、多額のプラス財産の存在が分かる時があります。その時には後悔して諦めるしかないですから、相続放棄はよく熟慮して行いましょう。
専門家への相談も検討する
相続放棄の手続きを自分でする場合は、なにかと不安がつきものですね。そんな時は、弁護士や司法書士に相談してみましょう。
相談だけなら時間制で無料の場合がありますから、事前に事務所に問い合わせられます。
相続放棄は慎重に行うべき重要なことです。さまざまな状況を考えて適切な判断ができるように備えておく必要がありますね。
まとめ
本記事から、相続放棄を検討する5つのケースや自分で手続きをする際の基本的な流れ、そして注意点などを解説してきました。
相続放棄は決して軽く行うことではないことを、十部お分かりいただけたと思います。
それでも相続放棄を決断した場合に、基本的に必要な情報をお分かちできたのではないでしょうか。
本記事を参考にして相続放棄という重要な段階を、首尾よく踏んでいただけたらと願っています。