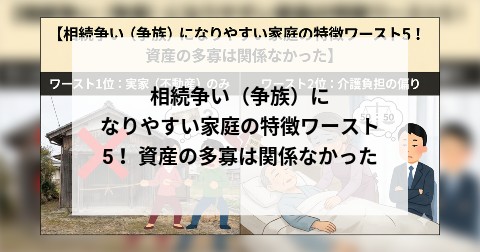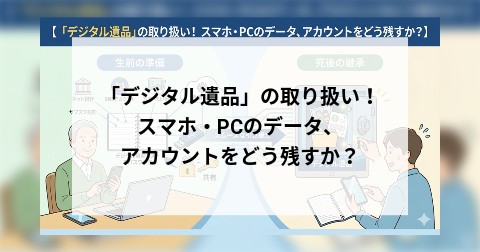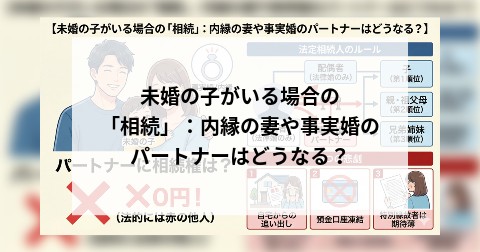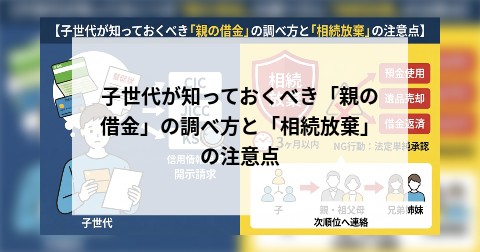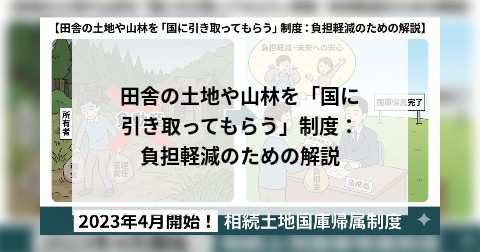相続財産調査とは!早くすべき理由と費用を抑えた士業の選び方を解説
愛する家族を亡くす経験は、大きな悲しみに暮れるものですね。ですが、現実は厳しくそんな悲しみの中でも、相続に関することは否応なく押し寄せてくるものです。
まず、相続が発生したらすぐに相続財産調査を行う必要が生じてきます。
本記事では、相続財産には何が含まれるか、またなぜ相続財産調査を早くすべきか、そして費用の負担を少しでも抑えた士業の選び方について解説していきます。
読者の方々が、スムーズで効率的に相続財産調査を終え、相続手続きを解決する一助にしていただけるなら幸いです。

相続財産調査とは?
相続財産調査とは、相続すべき財産が、どこにどれだけあるか全部を正確に洗い出すことです。相続財産にはプラスのものだけではなく、借金などのマイナス財産も含まれています。多額の遺産だと思っていたら、思いがけず借金の方が上回っていたということもありえますので注意が必要です。
さらに、土地などは、購入した時より金額が上がっていることが考えられ、相続財産調査には、相続するときの価値に改めて評価しなおすことも含まれています。
そうして、全部を洗い出したら、相続する財産をリスト化して一目で分かるようにしておきます。
相続財産の種類
相続財産の種類を具体的には大まかですが4つほどありますので以下で説明していきます。
1.動産
民法第86条「不動産及び動産」では、①土地及び定着物は不動産②不動産以外の物は、すべて動産とあります。
つまり、動産とは、不動産以外の財産すべてを指しています。
たとえば、銀行の預貯金、貴金属や家財道具、故人が趣味として収集していた骨董品などの美術品、そして自動車などは動産です。
2.不動産
不動産は、土地や建物のことですから分かりやすいですね。また、所有権が明確なもの以外に、賃借権や地上権も含まれることがありますので、注意が必要です。
3.有価証券や金融商品
株式や債券などの有価証券、さらに、FX、投資信託、保険積立金といった金融商品、さらにゴルフ会員権なども相続財産です。
4.負債
前述したように相続にはマイナス財産も含まれます。例えば、借金や住宅ローン、消費者ローンなどが対象です。
マイナス資産に関してはよく調査し、いつ、誰から、いくらの借金があるのか、しっかり把握しておくことが重要です。
相続財産調査を早急に行うべきなのはなぜか?
遺言書がある場合は、財産目録もリスト化されていることが多いのですが、遺言書がない場合は故人の財産を一から調査する必要があります。相続財産調査をできるだけ早急に進めることが大事な理由を2つ説明します。
遺産分割協議を円滑に進めるため
遺言書がない場合は、相続人全員が集まって遺産分割協議を開くことになります。遺産分割協議には相続人全員の出席が必須で一人も欠けてはいけません。
遺産分割協議では、財産を誰が、どれだけ相続するかを協議します。そのため、相続財産調査は遺産分割協議前に済ませておく必要があります。相続財産調査は相続の基盤となりますからできるだけ早く行う必要があります。
期限のある相続手続きがあるから
相続には意識すべき2つの期限があります。
相続放棄と限定承認の期限
相続の方法は3つあります。「承認」「放棄」「限定承認」です。そのうち「放棄」と「限定承認」は相続があることを知った日から3か月以内に手続きをしなければなりません。
プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合などには、「放棄」または「限定承認」を選択することになるため、できるだけ早く相続財産調査を行う必要があるのです。
相続放棄は一度してしまうと取り消すことはできません。後々大きなプラスの財産が見つかったことにより、後悔することのないような準備が大切でしょう。
また、故人が第三者の連帯保証人になっていた場合は、相続人が相続放棄をすれば、連帯保証人の地位を引き継ぎませんので、返済義務はありません。ただし、相続人自身が故人の連帯保証人になっていた場合は、相続放棄しても借金から逃れられませんので注意が必要です。
相続税申告の期限
相続税の申告・納付期限は、死亡を知った日から10か月です。
相続税には基礎控除額があります。、遺産の総額が(600万円×法定相続人の数+3,000万円)以下なら相続税はかからないので、申告の必要はありません。それ以上の遺産がある場合は、相続税の申告と納付の手続きが必要です。
相続税の申告漏れや遅延にはペナルティが課されますので、期限に注意をしましょう。
相続財産調査を依頼する場合の費用を抑えた士業の選び方
前述したように相続手続きには期限があり、期限内に相続手続きを行うためには士業の助けを求めた方がいい場合があります。
弁護士や税理士などの専門家に全てお任せすれば確実ですが、費用が高くなることが考えられます。司法書士と行政書士への依頼は費用が抑えらますが、できる業務の範囲が限られてきます。
そこで各専門家を組み合わせることで、費用を抑える方法を考えてみましょう。
弁護士
弁護士は相続税の申告・納付以外のほぼすべての業務を行うことができます。特に相続人同士のトラブルが予見される場合などには弁護士に依頼するのが良いでしょう。費用は10万円~30万円程度が相場ですが、相続財産が多いと費用が高くなります。
弁護士は基本、相続税の申告書類等を作成することはしないため、その後の相続税申告手続きは自分で行うか税理士に依頼することになります。費用を抑えるコツとしては、特に複雑な相続ではなくシンプルに相続財産調査から相続税の申告・納付をするのであれば最初から税理士に依頼するほうが費用は安くなるでしょう。
税理士
税理士は相続に関するスペシャリストで、法定相続人調査や相続財産調査から申告書作成までのすべてを業務として扱えます。
相続税の申告が必要な場合は、、税理士への依頼を検討しましょう。
もし、法定相続人調査や相続財産調査がそれほど困難でない場合は、そこまでは相続人が行い、財産の評価から相続税の申告書作成までを税理士に依頼すれば費用の節約となるでしょう。
司法書士
司法書士は、動産・不動産の名義変更や登記関係が主な業務です。
相続人が相続財産調査を行い、依頼する内容が不動産の名義変更や登記変更、預貯金や有価証券の払い戻しなどの手続きがメインであるならば司法書士への依頼が一般的で、費用も抑えられるでしょう。
行政書士
行政書士は、不動産の登記関係はできませんが書類作成のプロです。相続財産調査、預貯金の解約払い戻し、有価証券の名義変更、自動車の名義変更などはできます。
法定相続人の調査や相続財産調査のみ専門家に依頼したい場合には、費用面から考えると行政書士への依頼がおすすめです。
まとめ
故人を偲ぶ時間もなく、相続手続きの問題は押し寄せてきます。中でも相続財産調査は最も重要で手間のかかる作業です。
相続手続きには期限があるので、相続財産調査は早急に終えなければならないことをお伝えしてきました。
相続手続きが複雑になりそうな場合は専門家への相談を検討しましょう。ただし、専門家へ依頼すれば相応の費用がかかります。自分でできる部分とできない部分を明確にして、できない部分だけを専門家へ依頼すれば費用を抑えることができるでしょう。
付け加えるなら、被相続人は終活の一環として遺言書や相続財産目録を作成し、後に残された人が困らないようにしておくと残された人への助けになるでしょう。
この記事の監修者
山﨑裕佳子
ファイナンシャルプランナー
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者、証券外務員保有
通関士として通関業務、メーカーにて海外営業事務、銀行にてテラーなど経験し、FPの道へ。
2022年「FP事務所MIRAI」設立。「家計の見直しでMIRAIを変える」をモットーに、家計相談、金融記事執筆、書籍監修など、幅広く活動している。