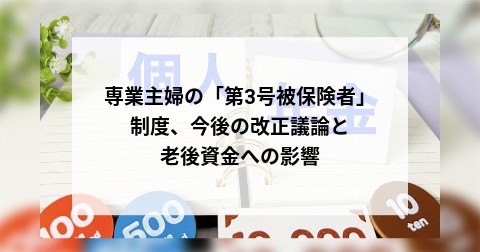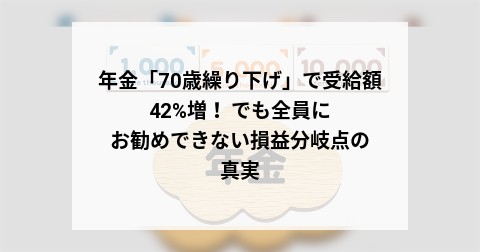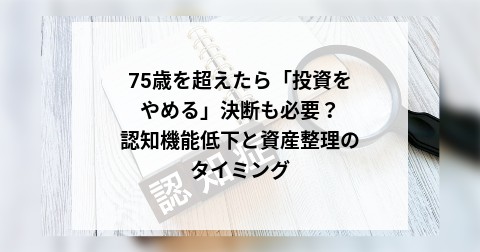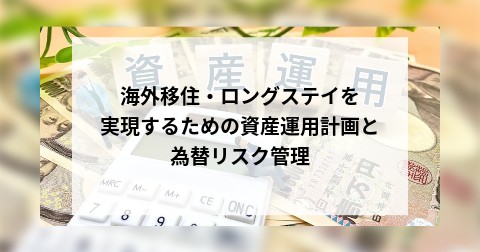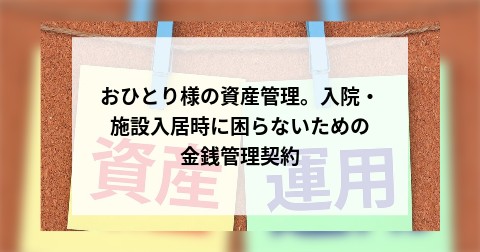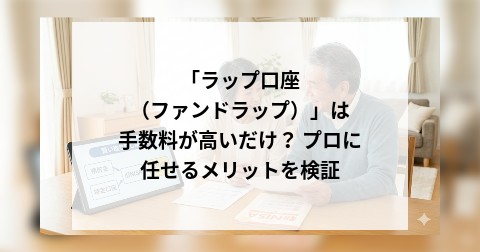老後資産に向けてミドルシニアから始める資産形成・資産運用とは?
年金だけでは老後に2,000万円が不足するという金融庁の報告書がきっかけで注目を集めた「老後2,000万問題」が話題になって久しいですが、今や4000万円でも足りなくなると言われています。
年金だけでは老後資金は十分とは言えない。貯蓄や資産の運用する必要性を感じつつも、暴落時のリスクを考えると簡単に踏み出せないという方も多いのではないでしょうか?
今回は、ミドルシニア世代から資産運用を始める理由や、おすすめの資産運用法についてご紹介しますので、これから老後の資金を作りたいと考えている方は、ぜひご確認ください。

資産運用を始める理由
資産運用とは、自分のお金を預貯金や投資に配分し、効率的に増やすことです。資産運用は、銀行などにお金を預ける預貯金と、株式や債券、投資信託などの金融商品を購入する投資に大別されます。
40代~60代は、仕事も収入も安定してくる時期です。収入が増加することでゆとりがうまれるため、貯蓄や投資に回せる資金も確保しやすくなるので着実な資産運用が可能です。
ミドルシニア世代からの資産運用でも、十分に老後の資金を確保できる可能性があります。会社員としての給料や年金以外の資金を確保したい人は、ミドルシニアのうちから資産形成を始めましょう。
資産運用のメリット
資産運用では、いくつかのメリットを得られます。複利効果や不労所得となる点など、資産運用のメリットを3つご紹介します。
不労所得を生み出すことができるようになる
資産運用により、不労所得を生み出すことができるようになる可能性があります。
投資信託の場合は複利効果でお金が増えていく、株式投資なら配当金でお金を得られるなど、一定の収入を確保できる可能性があります。万が一働けなくなった場合でも収入を得られるため、将来のために、お金を得るための手段は複数持ちましょう。
複利効果がある
複利運用の場合、複利効果があることも、資産運用のメリットです。複利とは運用益と元本を合計した金額に対する、利回りを計算する方法です。
資産運用によって得た利子を元本に加えて、さらに投資すると、資産運用の期間が長期であるほど、お金を増やせる可能性が高まります。これが複利効果です。
一方で、複利運用の場合、「損失が損失を生む」というマイナスの効果(当初の元本にプラスして運用した利子や配当金についても目減りしてしまう)が発生し、資金が減ってしまうリスクがあるという点には注意が必要です。
インフレへの対応にもなる
資産運用は物価が上昇する、インフレの対策になる点がメリットです。物価が上昇すると、ものの価格が上がるため、相対的にお金の価値が下がります。しかし、資産運用の商品によっては物価の上昇に伴って、資産価値が増加します。
資産運用のデメリット
魅力的なポイントが多い資産運用ですが、その一方で以下のように大きなデメリットも存在します。
元本割れを起こす可能性がある
資産運用は景気や経済の影響によって価格が変動するため、タイミングによっては利益を得られずに元本割れする可能性があります。また、掛金が保証されるわけではないため、資産運用に失敗した場合も損失が出てしまいます。
資産運用に時間を費やす必要がある
資産運用は短期間で大きな収益を得るのは非常に難しく、原則として長い期間を活用して資産を増やすものです。特に積立投資の場合は元本の金額が少ない時は、より増え方は遅くなり、元本が増えていくと複利効果で資産が増えていきます。
常に最新の情報を入手する必要がある
資産運用を続けるためには、情報収集が欠かせませんが、そのためには手間や時間がかかります。資産運用を行うには最新の情報を手に入れて、自身の今後の投資運用に加えていくのかなどの判断が必要です。
健全に資産運用するためのポイント
ミドルシニアが資産運用を成功させるためにはコツが必要です。以下のポイントを理解したうえで資産運用を始めましょう。
資産を増やすではなく資産の寿命を延ばす
資産運用と聞くと「資産を増やす」というイメージがあるかもしれませんが、特に老後が近い50代〜60代からの資産運用では「資産寿命を延ばす」という考え方が重要になってきます。資産寿命とは、老後生活をおくるにあたって、これまで形成してきた資産が尽きるまでの期間をいいます。
老後はリタイアや再雇用などで現役時代より収入が減り、支出のほうが上回ってしまうため、資産を取り崩しながら生活することが一般的です。
まだまだ働く期間が長ければ損失を取り戻せる可能性は高いですが、50代・60代では難しくなります。老後の資金を確保していくためには、少しでも資産の寿命を伸ばす方向で資産運用を活用しましょう。
分散投資を行う
資産運用を失敗しないためには、投資先や時間を分散させる分散投資が大切です。投資する資金や投資先をひとつに限定しないことで、価格変動による影響を抑えられます。
たとえば株価が下がっても、別の金融商品の価値が上がれば、運用している資産のトータルでは損失が出ることにはなりません。さまざまな事態を想定し、分散投資によってリスクを低減しましょう。
投資初心者でも始めやすい運用方法を選ぶ
確実な資産形成をするためには、運用方法の選択も重要なポイントです。とくに40代から老後資金の準備を始める場合は、目減りさせないよう、初心者でも始めやすいリスクの低い投資商品を選ぶことをおすすめします。
お金の悩みが解決できるサービス「オンライン家計相談」やお金に関する専門情報メディア「マネージャーナル」、不動産積立投資の「MIRAP」を主要事業として展開する株式会社シュアーイノベーションのこちらの記事もおすすめです。
老後資金が5,000万円必要って本当?
避けるべき投資方法
退職金の一括投資
退職金の一括投資退職金を使って一括投資をしようと考えている方もいるでしょう。しかし、退職金はまとまった資金が手に入る最後のチャンスとなる場合が多く、使い道で失敗はできません。
仮にそれが資産運用法として適切であっても、一度に全額を投資してしまうとその投資商品が仮に暴落した際には大変なことになってしまいますので、複数回に分けて投資して価格変動リスクを平均化することが適切です。
ハイリスク商品への投資
老後は「資産運用の時間があまりない」との考えから短期間で大きなリターンが狙えるような投資に目が向きやすい一面があります。特に50代以降は労働で収入を得られる期間が短くなるため、損失の補填が難しくなります。そのため、老後の資産運用には向いていません。
不自然に利回りの高い投資
利回りの高い投資は、短期間に老後資金を増やせる可能性があるため、魅力的に見えます。しかし不自然に利回りが高いものは、詐欺の可能性が高く基本的に関わるべきではありません。
一般的に資産運用の利回りは数%から高くても10%程度が相場です。それを大きく上回るような利回りをうたっている投資商品は現実味がありません。
ミドルシニアにおすすめの資産運用で活用したい制度
紹介する制度は、資産形成をする人を後押しするために、国が実施している制度です。賢く活用をして、より豊かな老後生活への資金作りに役立てましょう。
NISA・つみたてNISA
NISA(少額投資非課税制度)には国が定めた基準を満たす投資信託やETFを対象とする「つみたて投資枠」と上場株式やETFなどを対象とする「成長投資枠」があり、併用も可能です。非課税保有期間や口座開設期間は無期限・恒久化されており、ずっと非課税で投資できる点がメリットです。
NISAは2024年より新制度がスタートし、投資可能額が増え、期間の制限もなくなったため、自分に合った投資スタイルで活用することができます。
iDeCo
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、毎月一定額を積み立てて老後に受け取る資産を形成できるので効率的に老後資金の貯蓄を進めたいと考えている方にも向いています。
60歳になるまで一切の資産を引き出せませんが、掛金全額が所得控除の対象で運用益も非課税、受け取りの際にも大きな所得控除が受けられるなど、欠点以上に大きな利点があることが特徴です。
まとめ
今回の記事では、ミドルシニア世代におすすめの資産運用方法、活用すべき制度、注意点などをご紹介しました。
長期運用をするにあたり、40代、50代では遅すぎるということはありません。
40歳で運用を始めれば、年金が支給される65歳まで25年の期間があり、50歳開始でも70歳まで積み立てれば20年の運用期間が確保できます。
40代・50代はまだ人生の中盤です。今からでも全く遅くはありません。月々の生活費から資産運用をすることを検討していきましょう。
【PR】
お金に対して漠然と不安を抱えているのであれば「資産運用」を検討してみてはどうでしょう?
新NISAや投資に関する相談なら投資信託相談プラザのセミナーに参加してみては?
| 投資信託相談プラザの無料セミナーご参加はこちらから |
| 店舗またはオンラインでの個別相談はこちらから |