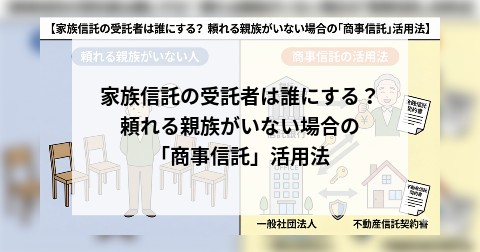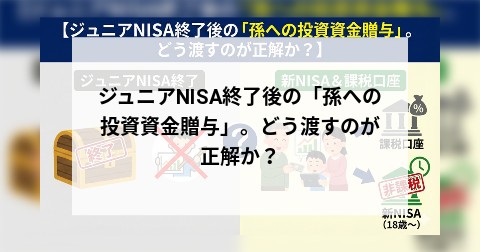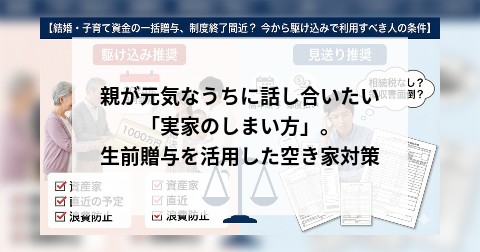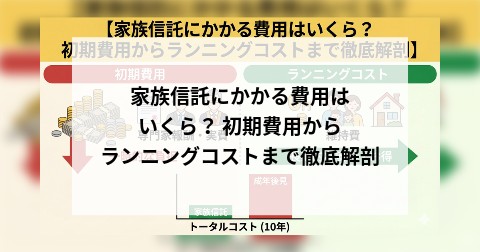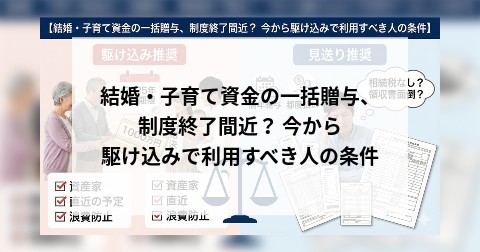「信託契約」って何?信託の仕組みとメリット・デメリットを徹底解説
高齢化が進む現代、認知症などの発症リスクもあり、相続の問題はもとより、老後の財産の管理の問題も深刻となってきました。
認知症対策としての財産管理方法については成年後見制度が、自分の死後の財産分配については遺言の制度がすでに存在していますが、近年注目されている方法として家族信託があります。
今回はこの家族信託の仕組みやメリットとデメリット、実際に利用する際に必要になる手続きや費用について、わかりやすく解説していきます。

信託契約とは?
信託契約とは、財産を持つ人が所有する財産の管理・処分・運用を信頼できる相手に託し、その相手が信託の目的に従って財産の管理・処分・運用を行う契約です。相手を信頼して財産を託すことから「信託」といいます。
財産を託す人を「委託者」、財産の管理などを任された人を「受託者」といい、託された財産から生じた利益を受け取る人を「受益者」といいます。受益者は委託者と同じ人でもよく、委託者と受益者が同じ場合の信託を「自益信託」といいます。
この信託契約には3種類の方法があります。3種類の信託契約について、下記に説明します。
契約による信託(契約信託)
「契約信託」では信託契約書を委託者と受託者で交わすことで、信託が開始されます。
信託契約に係わる契約書を必ずしも公正証書にする必要はありませんが、データで作成した契約書に不正(改ざん等)をされてしまう可能性を考えると、公証役場で日付入りの印を押して認証してもらうことが確実と言えます。
公証役場でのこの手続きは1通あたり700円程度と安価な費用で時間もかからずに完了します。また、確定日付があれば、第三者から見ても確実にその日に作成された契約書であると判断してもらうことができます。
遺言による信託(遺言信託)
遺言書を作成し、その中に「委託者の死亡により、信託を発生させる」という内容を記載することで遺言により信託を開始させることができます。これを遺言信託といいます。
もし遺言による信託をお考えの場合は、公正証書遺言で作成されることを強くお勧めします。自筆で遺言書を作成する際に、正しい形式で記載しないと遺言書自体が無効になるためです。
宣言による信託(自己信託)
自己信託とは委託者と受託者が同一人物(自分)による信託の事を指します。例えばAさんが自分の持つ財産を自らが受託者となり、管理、運用、処分をし、発生した利益をBさん(受益者)に渡すような場合が当てはまります。
自己信託証書を公正証書で作成するか、あるいは第三者である受益者に信託内容を確定日付が入った書面で信託されたということと、信託内容を通知することで「自分の財産を、自分に信託します」と宣言したとして、開始される信託が自己信託です。
他の信託契約と異なるのは、委託者も受託者も自分であることですが、自己信託を設定することでみなし贈与税の課税対象になりますので注意が必要です。
家族信託とは?
家族信託とは、信託法に基づき、財産の所有者が(委託者)、信頼できる人(受託者)に、資産等を預けて、その財産(信託財産)を管理・承継する制度です。
家族信託のメリット
家庭裁判所が関与しないから柔軟な対応ができる
家族信託も成年後見制度も、ともに将来的に認知症を発症した場合のリスクに備えられる制度で、誰かが本人に代わって財産管理をします。ただ、大きな違いに、成年後見制度では家庭裁判所に後見人の選任を申し立てする必要があることが挙げられます。家庭裁判所が関与するので、後見人の選任の条件は厳しいものになります。
一方、家族信託なら、家庭裁判所の関与なしで、受託者を選ぶことができるうえに、家族間で信託契約により財産が管理できます。より自由度が高いことがメリットの一つになっています。
遺言書よりも優先して適用される
家族信託は遺言書よりも優先して適用されます。遺言書・家族信託の両方とも、財産の承継先を生前に決めておくことができるのですが、もし遺言書に「実家の不動産は長女に」、また家族信託契約では「実家の不動産は長男に」と異なる内容になっていた場合、家族信託の契約書の内容が優先されます。これは生前に遺言の内容に抵触する行為を行うと、抵触した部分について遺言が撤回されたとみなされるためです。
認知症に備えられる
自身の相続の際、「配偶者に遺産を残す」といった内容の遺言書を作成しても、配偶者の判断能力が低下している場合、相続後の財産管理ができないリスクが発生してしまいます。
たとえば、配偶者が老人ホームなどに入っていれば月々の費用がかかり、配偶者に判断能力がないと賃貸借契約や更新などの手続きができない可能性もあるでしょう。
そこで、家族信託で「自分が亡くなったら受益者は妻に変更する」などと定めておくことで、受益者の変更にあたって遺言書や遺産分割協議書も必要とせず、配偶者の生活のために財産を利用することが可能になります。
二次相続の対策として有効
子どものいない家庭や再婚家庭でしばしば問題になるのは、「配偶者の兄弟姉妹」「前の配偶者の子ども」など、被相続人の直系卑属ではない人に相続権が生じてしまうリスクがあるということです。とくに先祖代々受け継いでいる土地が、直系卑属以外の他人に渡るのを避けたいという人は多くいます。
しかし、そうした事態が起こる可能性が高いのは、亡くなった方(被相続人という)の後に相続人が亡くなった二次相続以降で、この場合は遺言書でリスクを排除できません。
その点、家族信託であれば、受益権移転先あるいは信託終了時の資産承継先を「委託者自身の兄弟姉妹」や「現配偶者との間の実子」などと指定しておくことで、遺言書では不可能な二次相続以降での直系卑属以外の排除をすることができるのです。
倒産隔離機能がはたらく
家族信託には、倒産隔離機能がある点もメリットといえるでしょう。
倒産隔離機能とは、家族信託の財産と委託者・受託者の個人財産を分ける機能のことです。
「将来自分(委託者)や受託者が信託財産に関係のない多額の債務を負ってしまった場合でも、信託財産は差押えられない」というもので、将来何かがあった場合に対する備えになります。
ただし、注意点として、信託財産は受益者の「信託受益権」に形を変えているため、受益者が強制執行などを受けるケースでは、財産を差し押さえられる可能性があります。
共有不動産の相続問題を予防できる
共有不動産は、共同相続人全員が協力しないと処分できません。
そのため、将来的に複数の相続人が不動産を共同相続してしまうと、管理処分権の問題が生じる可能性があります。
共有者としての権利や財産的価値は平等にしたまま、家族信託によって管理処分権限を共有者の一人に集約しておくことで、いわゆる「不動産の塩漬け」を防止することができます。
家族信託のデメリット
受託者になっても身上を監護する権利がない
「身上監護権」とは、身の周りの世話ではなく、判断能力のない本人に代わって住居の確保や契約、介護・福祉施設やリハビリ施設への入退所するための手続きや、医療や入院に関する契約や手続きを行うことです。
信託の受託者にはこの「身上監護権」がありません。そのため、受託者は委託者の入院手続きや施設入所手続きをすることはできません。身上監護権が必要なら、成年後見制度を併用し、補完する必要があります。
節税対策にはならない
家族信託を利用しても直接的な節税効果は期待できません。
家族信託は認知症対策や、将来の財産の承継先を自由に設計できる制度としてメリットがあります。しかし、家族信託を組成したからといって、本来払うべき税金が減るわけではないからです。
遺留分の侵害に注意が必要
家族信託の内容を設計する際は、遺留分 を考慮する必要があります。
遺留分とは、法定相続人(配偶者・子・父母)に最低限保証された相続分です。
家族信託において、法定相続人の遺留分を侵害するような契約がなされていたとしても、配偶者・子・父母は遺留分があることを主張可能であり、遺留分にあたる金額を請求できます(民法第1046条)。
遺留分侵害のようなトラブルが起こらないようにするためには、相続発生時の財産承継について、相続人となる可能性がある人物全員と話し合うことが重要です。
まとめ
信託は、安全性が高く金銭以外の財産も信託の対象になるなど、使い勝手の良い制度です。最近では成年後見制度に代わる老後の資産管理方法として、家族間で信託契約を結ぶ家族信託も利用者が増加しています。
家族信託は、生前の判断能力があるうちから、財産の管理方法や相続先を決められる方法です。特に不動産や預貯金など、ある程度まとまった財産がある場合、認知症になる前に、信頼できる家族に財産の管理についてよく相談しておきましょう。